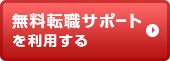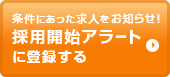大正製薬ホールディングス
「売り上げの8割」OTC注力の姿勢鮮明に…問われる医薬事業の立ち位置
2021/11/5 AnswersNews編集部 前田雄樹・亀田真由
OTC(一般用医薬品)と医療用医薬品の2本柱で事業を展開する大正製薬ホールディングス(HD)。相次ぐ買収で海外展開を強化するOTC事業は好調な反面、屋台骨だった抗菌薬の特許切れ以降、医薬事業の売り上げは低迷。収益構造が大きく変化し、OTCの売り上げが全体の8割を占めるまでに拡大する中、医薬事業の位置付けが改めて問われています。
OTC事業 売り上げの80%まで拡大
「鷲のマーク」で一般消費者にも広く知られる大正製薬。大衆薬メーカーのイメージが強い同社ですが、業績面でもOTC事業の存在感が増しています。
2020年度の大正製薬HDの連結業績は、売上高2820億円(前年度比2.3%減)、営業利益200億円(5.5%減)。全体としては減収減益となったものの、OTCを中心とするセルフメディケーション事業は売上高2269億円(3.1%増)と好調。連結売上高に占める割合は80.5%で、5年前に比べて18ポイントも上昇しました。

コロナ禍でインバウンド需要の低下というマイナス要因ががありながらOTCで好業績を保っているのは、海外で売り上げが急拡大しているから。大正製薬HDは19年5月、提携先のベトナム企業であるDHG(ハウザン製薬)を約118億円で連結子会社化。同7月にも米ブリストル・マイヤーズスクイブ傘下のOTC企業である仏UPSAを約1700億円で買収し、海外の事業基盤を強化しました。買収前の18年度は309億円だったセルフメディケーション事業の海外売上高は、20年度に3倍の925億円まで拡大。海外売上高比率も11.8%から32.8%へと上昇しました。

一方、国内OTC市場では、競争の激化によって苦戦を強いられています。
最大の主力品であるリポビタンシリーズは、高齢化やエナジー系ドリンクの登場で市場が縮小。20年度の売上高は458億円で、01年度の半分以下に落ち込みました。99年の発売以来、市場を独占し続けてきた発毛剤「リアップ」も、18年に相次いで後発品が発売され、ここ数年は伸び悩んでいます。
20年度はコロナ禍で消費者に感染症対策が定着したことで、感冒薬「パブロンシリーズ」が29.1%、咽喉薬「ヴィックスシリーズ」が28.3%の大幅減収となりました。消費者のニーズ変化を踏まえ、食品・スキンケア領域への投資や通信販売の強化が行なっていますが、主力ブランドの穴を埋め切れてはいません。
医薬事業 ピーク時の半分以下に
それ以上の苦境に直面しているのが、もう1つの柱である医薬事業です。
業績を支えてきた抗菌薬「ゾシン」「クラリス」の特許切れにより、医療用医薬品の売上高はピークとなった14年度から20年度の6年間で半減。抗菌薬に代わって主力品となった骨粗鬆症治療薬「エディロール」は、中外製薬との販売提携を終了し、21年4月で販売を終えました。ノバルティスファーマと共同で販売していた糖尿病治療薬「ルセフィ」を単独販売に切り替えたものの、反転の兆しは見えず、少なくとも向こう数年は減収が続くと考えられます。

18年には富士フイルムHDとの資本提携を解消し、富山化学工業(現・富士フイルム富山化学)株式の持ち分を富士フイルムHDに売却。翌年、海外のOTC企業を相次いで買収したことも重なり、OTC重視の姿勢を印象づけることとなりました。
ただ、大正製薬HDは「セルフメディケーション事業と医薬事業をバランスよく成長させながら、国際競争の中でも着実に成長・発展し続けられる強固な経営基盤の構築を目指す」としており、2本の柱は今後も維持する方針を示しています。
21年3月には、国内初のナノボディ製剤として、ベルギーのアブリンクスから導入した関節リウマチ治療薬オゾラリズマブを申請。これ以外にも、21年8月時点で精神・神経疾患領域を中心に臨床第2相(P2)段階で2品目、P1段階で3品目を国内外で開発しており、導入も含めてパイプライン拡充を急いでいます。医薬事業をどうしていくのか。難局の中、戦略が問われます。
【大正製薬ホールディングスに関する記事を読む】
・大正製薬ホールディングスの記事一覧
大正製薬ホールディングスへの転職をお考えの方はお気軽にご相談ください。