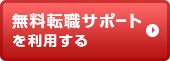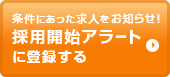第一三共
3つのADCで実現間近の「がんに強い第一三共」
2021/11/1 AnswersNews編集部 前田雄樹・亀田真由
大型化を期待する抗HER2抗体薬物複合体(ADC)「エンハーツ」を日本と米国、欧州で発売した第一三共。抗凝固薬エドキサバンの成長で高血圧症治療薬オルメサルタンのパテントクリフを乗り越え、がん領域に強みを持つ企業として新たなフェーズに入ろうとしています。エンハーツを含む3つのADCで収益源を確保し、次の成長の柱を確立できるか。いよいよ実力が問われます。
25年度に売上収益1兆6000億円
”がんに強い”グローバル創薬企業――。2025年ビジョンがいよいよ現実のものとなりつつあります。
2020年1月、第一三共は米国で抗HER2抗体薬物複合体(ADC)「エンハーツ」(一般名・トラスツズマブ デルクステカン)をHER2陽性乳がん治療薬として発売しました。同5月には日本で、翌21年2月には欧州で販売を開始。21年3月期には301億円を販売し、2020年度までに目標としていた「がん事業の立ち上げ」を達成しました。同社がADCの技術開発に着手したのは2010年。長年の研究が実を結びました。
エンハーツと抗TROP2 ADC「DS-1062」(ダトポタマブ デルクステカン)では、海外大手の英アストラゼネカとグローバルで戦略的提携を締結。提携の対価は最大129億ドル(約1兆4190億円)に上ります。大型提携に株式市場も大きな期待を寄せており、時価総額は一時6兆8000億円規模に拡大。全業種を通じて国内トップ10に入るまでに膨らみました(11月1日の時価総額は約5.6兆円)。
高血圧症治療薬オルメサルタン(日本製品名・オルメテック)の特許切れで低迷した業績も回復傾向にあります。21年3月期の連結業績は、売上収益9625億円(前期比2.0%減)、営業利益638億円(54.0%減)。ワクチンに関するサノフィとの提携を終了したことや、前の期に工場の売却益を計上していた反動で減収減益となったものの、注力するグローバル製品の売上収益は順調に拡大しています。

かつて世界で3000億円を売り上げたオルメサルタンが3分の1以下に売り上げを落とす中、業績回復に貢献しているのは抗凝固薬エドキサバン(国内製品名・リクシアナ)です。日本や韓国、欧州で順調にシェアを伸ばし、15年度に150億円だった売り上げは、5年で約11倍の1659億円まで拡大しました。今後はエンハーツが業績拡大を牽引していく見通しで、これに続くADCを順次、市場に投入することで、第一三共は25年度に「売上収益1兆6000億円(うちがん事業6000億円超)」の達成を目指します。
3ADCに最注力
25年度までの増収分のほとんどはがん領域からもたらされる計画。その大半を、エンハーツとDS-1062、抗HER3-ADC「U3-1402」(パトリツマブ デルクステカン)の3つのADCで稼ぐ算段です。
ADCとは、抗体に低分子化合物を結合させた薬剤。ADCに搭載する低分子医薬品を「ペイロード」、抗体とペイロードをつなぐ部分を「リンカー」と呼び、標的に対する高い選択性を持つ抗体をキャリア(運び屋)として使うことで、殺細胞効果を持つ低分子化合物を選択的に届けます。13年にはスイス・ロシュグループの抗HER2-ADC「カドサイラ」が実用化されるなど、通常の細胞への影響を抑えながら強力な抗がん剤を使える技術として注目されています。

第一三共のADC技術「DXd-ADC」の特徴は、ペイロードに新規作用機序のトポイソメラーゼⅠ阻害薬を採用していること。リンカーの安定性も高く、従来のADCに比べて強力な薬効を示しながら毒性を抑えることができると考えられています。
エンハーツは現在、乳がん(日米欧)と胃がん(日米)の適応で販売しており、25年度までにHER2低発現乳がん、HER2陽性/変異非小細胞肺がん、HER2陽性大腸がんなどへの適応拡大を見込んでいます。

DS-1062は「アクショナブル遺伝子の変異がない非小細胞肺がんに対する2次・3次治療」、U3-1402は「EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がん(3次治療)」で25年度までに承認を取得するのが目標。乳がんと非小細胞肺がんでは、3つのADCでほぼすべてのサブタイプの患者に治療を提供することを目指しています。
ただ、ADCの分野では近年、開発競争が活発化しており、グローバル大手の参入も相次いでいます。特にDS-1062は同作用機序の競合品「Trodelvy」(米ギリアド)がトリプルネガティブ乳がんを対象に米国で先行して販売されており、第一三共は肺がんでの開発を急いぐことで差別化を図る戦略をとっています。競合に対してどう優位性を確保していくのかは課題です。
新薬中心の収益構造へ
第一三共が21~25年度までの5年間で予定している研究開発費は約1.5兆円。そのほとんどは3つのADCに集中的に投入し、同じく5000億円を見込む設備投資も最大3000億円をADCの生産体制強化に充てる方針です。
ただ、ADC一本というわけではなく、それ以外の領域でも継続的に新薬を投入・育成し、新薬を軸とした収益構造を強化していく考えです。
すでに1600億円を稼ぎ出すエドキサバンは、24年ごろを想定するピーク時に年間2200億円以上まで売り上げを伸ばし、27年の特許切れまで安定的に利益を生み出す製品として期待しています。
このほかにも、疼痛治療薬「タリージェ」や、欧州で昨年承認を取得した高コレステロール血症治療薬「Nilemdo/Nustendi」などを中心に育成を強化。25年度には、売上収益に占める新薬の比率が米国と欧州でほぼ100%、日本で約80%、アジア/中南米でも約45%まで上昇するとみています。米国では売上収益の約95%をがん領域で稼ぐようになり、欧州で約45%、日本とアジア/中南米で約20%を予想。現在は売り上げ全体の半分以上を日本が占めていますが、25年度には海外が日本を上回る想定です。
同社はこの数年を「投資機会」と位置付けており、新薬で上げた収益を積極的に投資する姿勢です。開発投資を支えていくため、資産のスリム化も進めており。16~20年度には長期収載品や工場の売却などを通じて1632億円のキャッシュを創出しました。
2030年ビジョンを支える「次の柱」は
今でこそ順調な第一三共ですが、決して順風満帆だったわけではありません。
がん事業立ち上げの足がかりとしてエンハーツより前の発売を見込んでいた製品では、キザルチニブが欧米で、ペキシダルチニブが欧州でそれぞれ承認取得を逃しました。米国の疼痛事業も、中核としていた製品の開発を中止し、事業の見直しを余儀なくされました。
05年に第一製薬と三共が合併して以来、13年度に一度は売上高1兆円を達成したものの、そこから業績を思うように伸ばせなかった第一三共。約5000億円を投じて買収したインドの後発品大手ランバクシーは相次いで品質問題を起こし、結局、他社に売却しました。その間、業績を支えたオルメサルタンは特許切れを迎え、業績は停滞。復活をかけて打ち出したのが、がんを中心とする「創薬企業」への転換で、ADCのポテンシャルが足元の事業を引っ張っています。
第一三共は21年の中期経営計画を策定するにあたり、2030年ビジョンを「サステナブルな社会の発展に貢献する先進的グローバルヘルスケアカンパニー」とし、「がん領域でグローバルトップ10」「さらなる成長の柱が収益源の1つ」などを目標に定めました。
今後5年間はそのための成長ドライバーを見極めるのに充てられます。候補となるのは▽3つのADCとDXd-ADC製品▽第2世代・新コンセプトADC▽改変型抗体▽核酸医薬プロジェクト――の4領域。これ以外にも、米ウルトラジェニクスから導入した遺伝子治療薬や、臨床開発中の新型コロナウイルスワクチンで使用しているLNP-mRNA技術にも開発リソースを回したいといいます。3つのADCという足元の成長源をばねに「次の柱」を見出して持続的成長に繋げられるか。底力が試されます。