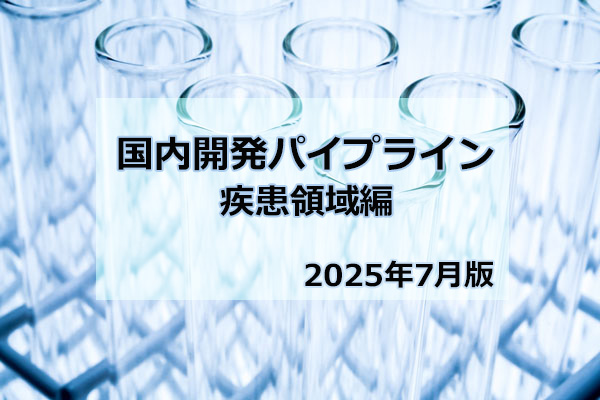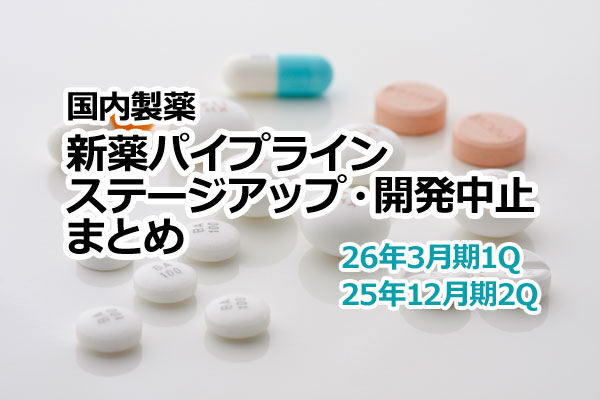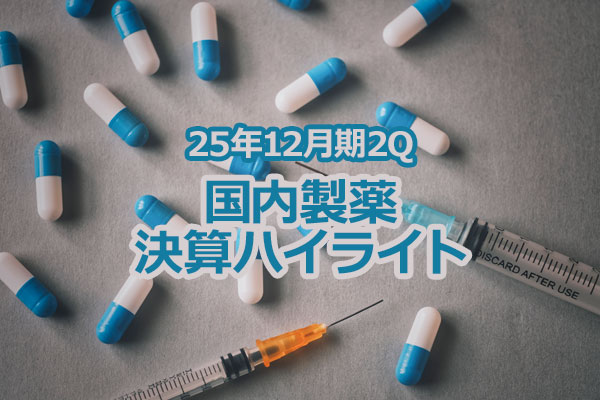次世代の抗体医薬と言われてきた抗体薬物複合体(ADC)や二重特異性抗体が、本格的な普及期に入ってきました。2024年は国内で承認された抗体医薬の4割をADCと二重特異性抗体が占め、今年も複数の品目が承認される見通し。大鵬薬品工業がADC技術を持つスイス・アラリスの買収を発表するなど、投資も活発です。
INDEX
24年は過去最多の7品目承認
2024年に国内で承認されたADCは2品目、二重特異性抗体は5品目。あわせて7品目は過去最多で、この年に承認された抗体医薬16品目の44%を占めました。

ADCでは、いずれもTrop-2を標的とする「トロデルビ」(一般名・サシツズマブ ゴビテカン、ギリアド・サイエンシズ)と「ダトロウェイ」(ダトポタマブ デルクステカン、第一三共)が承認。トロデルビはトリプルネガティブ乳がん、ダトロウェイはホルモン受容体陽性・HER2陰性乳がんが対象です。
二重特異性抗体は、濾胞性リンパ腫治療薬の抗CD20/CD3抗体「ルンスミオ」(モスネツズマブ、中外製薬)や多発性骨髄腫治療薬の抗BCMA/CD3抗体「エルレフィオ」(エルラナタマブ、ファイザー)、同「テクベイリ」(テクリスタマブ、ヤンセンファーマ)などが承認。5品目ともがんが対象で、うち4品目はがん細胞にT細胞をリダイレクト(誘導)することでがん細胞を攻撃する作用を持ちます。
一方、EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性非小細胞肺がん治療薬「ライブリバント」(アミバンタマブ、ヤンセン)は、がん細胞の増殖にかかわるEGFRとMETの2つの因子を標的としています。ヤンセンにとっては初の肺がん領域の製品で、今年3月にはEGFR阻害薬「ラズクルーズ」(ラゼルチニブメシル酸塩水和物)との併用療法がEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの1次治療を対象に承認されました。
開発活発、投資も相次ぐ
国内でこれまでに承認されたADCは13品目、二重特異性抗体は10品目。国内初承認はADCが05年、二重特異性抗体が18年ですが、20年以降の承認がそれぞれ7品目、8品目となっています。
05年に国内初のADCとして承認されたのは、ファイザーの急性骨髄性白血病治療薬「マイロターグ」。それ以降、中外製薬の「カドサイラ」や第一三共の「エンハーツ」、楽天メディカルの「アキャルックス」、アステラス製薬の「パドセブ」などが承認されています。今年3月にはジェンマブの「テブダック」が子宮頸がんを対象に承認を取得しました。

一方、二重特異性抗体は中外製薬が創製した「ヘムライブラ」が国内初。血液凝固第IXa因子と第X因子に結合し、欠損または機能異常をきたしている第VIII因子の機能を代替する血友病A治療薬です。10品目のうち6品目がT細胞のリダイレクトで、2つの異なる標的を同時に阻害するものとしては、ライブリバントのほかに加齢黄斑変性などの治療薬「バビースモ」(中外製薬)が承認されています。

今年も、すでに承認を取得したADCテブダックのほか、グラクソ・スミスクラインの多発性骨髄腫向けADCベランタマブ マホドチンや、ヤンセンの多発性骨髄腫向け二重特異性抗体トアルクエタマブが承認される見込みです。
開発も活発化しており、ADCは第一三共、武田薬品工業、MSD、アストラゼネカ、田辺三菱製薬、GSKなど、二重特異性抗体はアストラゼネカ、アステラス製薬、小野薬品工業などが国内で臨床開発を実施中。ほとんどががん領域ですが、二重特異性抗体は自己免疫疾患にも広がりを見せています。
特にADCの分野では大型買収も相次いでおり、米アッヴィは昨年、ADCを手掛ける米イミュノジェンを101億ドルで買収。米ファイザーも23年に米シージェンを430億ドルで、米ギリアド・サイエンシズも20年に米イミュノメディクスを210億ドルで買収しました。英アストラゼネカや米メルクは、有力企業の1つである第一三共と研究開発・商業化で大型の提携を結んでいます。
日本勢では、大鵬薬品工業が今年3月、ADC技術を持つスイスのアラリス・バイオテックを買収すると発表。小野薬品も昨年、韓国のリガケム・バイオサイエンシズと提携し、ADCの研究開発に乗り出しています。
AnswersNews編集部が製薬企業をレポート
あわせて読みたい
関連キーワード
オススメの記事
-

キッセイ、米社から甲状腺眼症治療薬を導入/参天、緑内障・高眼圧症薬ネタルスジルメシル酸塩を申請 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年7月30日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り