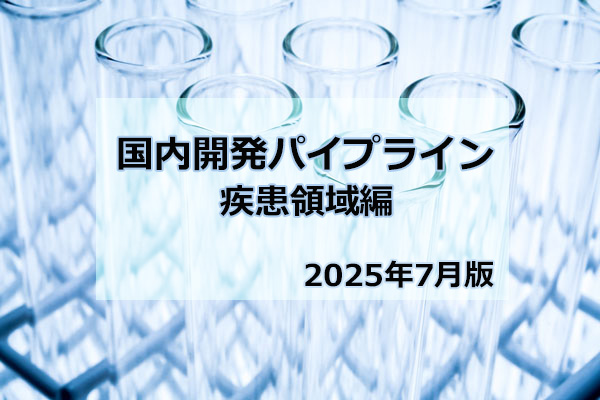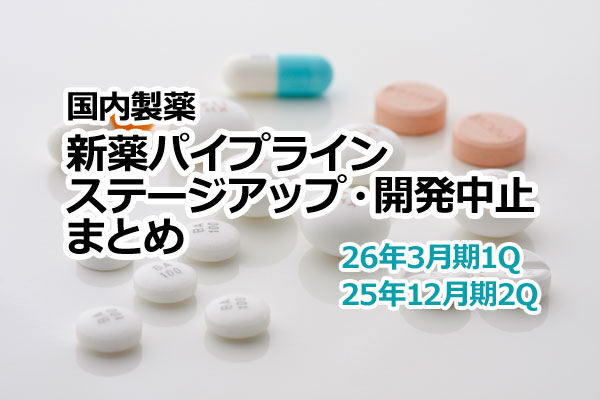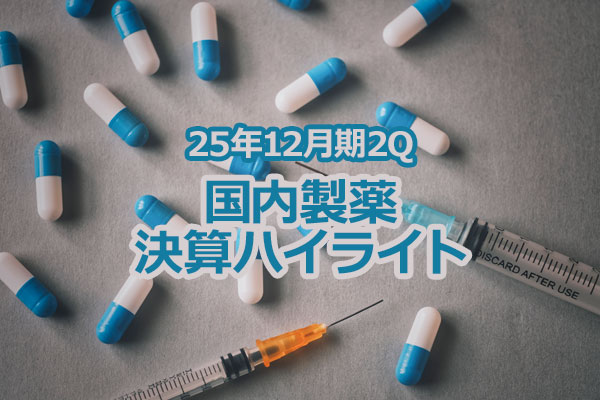2024年の国内医療用医薬品売上高トップは、薬価ベースで1851億円を売り上げたMSDの免疫チェックポイント阻害薬「キイトルーダ」だったことが、調査会社エンサイスが集計した月間スナップショットで明らかになりました。2位には第一三共の抗凝固薬「リクシアナ」が浮上し、いわゆる「共連れ」で市場拡大再算定を受けた「オプジーボ」(小野薬品工業)をわずかに上回りました。
MSD「昨年承認の適応が拡大に貢献」、オプジーボは再算定響く
上位10製品の顔ぶれは前年と同じ。10製品の合計売り上げ金額は1兆2094億円で、前年から8%増加しました。企業別では外資(中外製薬を含む)が7製品に上り、疾患領域ではがんが半数を占めました。売上高が1000億円を超えたのは8製品で、前年から2製品増えました。

トップのキイトルーダは売り上げを16%伸ばし、前年2位から順位を上げました。同薬は24年5月に「治癒切除不能な進行・再発の胃がんに対する化学療法との併用療法」と「治癒切除不能な胆道がんに対する化学療法との併用療法」の適応を取得。8月には「非小細胞肺がんにおける術前・術後補助療法」、9月には「根治切除不能な尿路上皮がんに対する1次治療」の適応も追加しました。成長は加速しており、月間売上高は12月に180億円を突破しました。
好調の要因についてMSDは、年間を通じて肺がん、腎細胞がん、トリプルネガティブ乳がんを中心に既存適応症での処方が堅調だったことに加え、「昨年新たに取得した適応症が売り上げ拡大に貢献した」としています。
同じ免疫チェックポイント阻害薬のオプジーボは対照的に13%の売り上げ減となり、前年首位から3位に後退。同薬効の「バベンチオ」に腎細胞がんの適応が追加されたことで類似薬として再算定を受け、4月に薬価が15%引き下げられたことが響きました。小野薬品によると、オプジーボ全体の中で腎細胞がんに使用される割合は「10~20%程度」にすぎません。同社は「他社製品の市場拡大による薬価引き下げには合理性がなく、イノベーションが反映されていない制度」だと強く非難しています。
市場拡大再算定の共連れルールをめぐっては、24年度の薬価制度改革で免疫チェックポイント阻害薬とJAK阻害薬を対象から外すことになりました。しかし、除外ルールの適用は同年5月が1回目となる四半期再算定からとされ、オプジーボはぎりぎりのタイミングで引き下げを受けることになりました。
リクシアナ好調、デュピクセントは急成長
国内市場では20~23年の4年間、キイトルーダとオプジーボが首位を奪い合う構図でしたが、そこに割って入ったがリクシアナです。第一三共にとっては国内の最主力品で、同社によると経口抗凝固薬4剤でのシェアは24年3月期で47.2%と5割近くを占めています。月間売上高でオプジーボを抜いたのは4月で、その後は2位を譲ることなく推移。同社は24年4~9月期決算発表時にリクシアナの通期売上収益予想を上方修正しました。今年2月には「慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者における血栓・塞栓形成の抑制」の適応追加の承認が見込まれています。

成長著しいのが、アトピー性皮膚炎などの治療薬「デュピクセント」(サノフィ)です。売上高は前年から51%増え、順位も前年10位から一気に5位まで上昇しました。23年6月に4つ目の適応となる「既存治療で効果不十分な結節性痒疹」の承認を取得。サノフィは「本来の製品力が評価されている」と強調します。
23年10月からは、それまで単独で行ってきたプロモーションを、創製元である米リジェネロンの日本法人との共同販促に切り替えました。24年4月には慢性閉塞性肺疾患(COPD)の適応追加を申請。これに合わせリジェネロンは販売体制を強化する方針で、さらなる売り上げ拡大に取り組みます。同年11月には3度目となる市場拡大再算定によって薬価が8.7~13%引き下げられましたが、11月と12月も月間100億円を超える売り上げを維持しています。
SGLT2阻害薬「フォシーガ」(アストラゼネカ)は前年と同じ8位ですが、売上高は22%増で1000億円に乗せました。今年は後発医薬品の参入が見込まれますが、適応は2型糖尿病のみで、慢性心不全や慢性腎臓病ではまだ後発品を使うことはできません。フォシーガの売り上げ全体に占める2型糖尿病の割合は半分を下回る程度とみられます。
アストラゼネカからは、抗がん剤「タグリッソ」が6位、免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」が7位にランクイン。1000億円超の製品を3つ持つ唯一の企業となりました。
※売上高はエンサイスの月間スナップショットを引用〈転載禁止〉