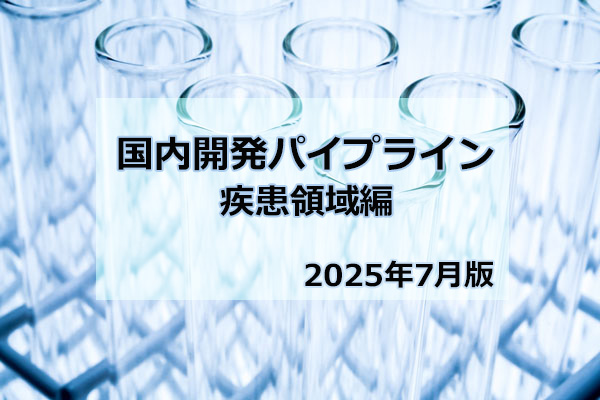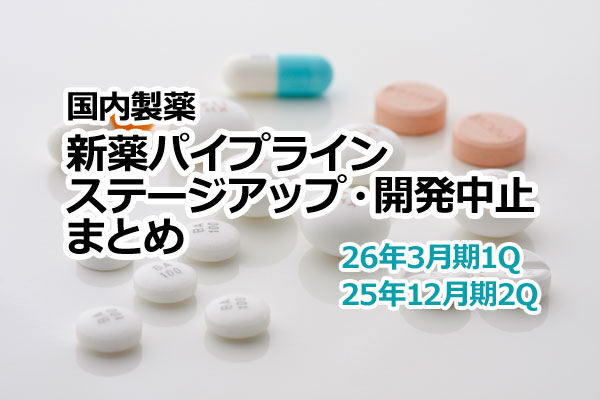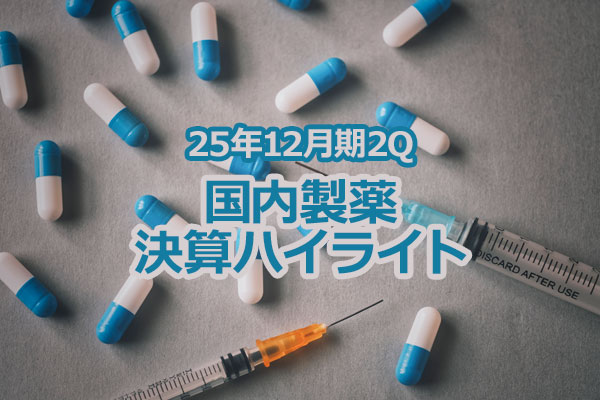大量に作られる医師向けコンテンツ、使われないのは誰のせい?|数字は語る―製薬営業・マーケティング
更新日
山下篤志:Veeva Japan コマーシャルストラテジー バイス・プレジデント

MRの削減、医師の働き方改革、医療機関による訪問規制、デジタルの浸透、マルチチャネル・オムニチャネル化…。変化する製薬企業の営業・マーケティングの「今」を象徴する数字の背景を読み解き、「これから」を考えます。
制作量は急増、でも使われるのはごく一部

▼Veeva フィールドトレンドレポート:
https://www.veeva.com/jp/pharma-biotech-field-trends/
製薬企業が医療従事者への情報提供に使うコンテンツの制作量が急増しています。Veevaのデータによると、製薬企業のコンテンツ作成量は2018年から20年にかけて全世界で約3倍に増え、その後も増加傾向が続いています。
なぜここまで飛躍的にコンテンツの量が増えているのか。理由はいくつかあります。専門性の高い医薬品が増え、製薬企業が提供する情報そのものが高度化・複雑化していますし、医師の情報に対するニーズも多様化しています。コロナ禍でMRが医師に会いにくくなったこともコンテンツの増加に拍車をかけました。
コンテンツの有効な活用は、リアルまたはオンラインでの面談の効果を高めます。Veevaの米国のデータでは、MRが医療従事者との面談中にデジタルコンテンツを使用した場合、そうでない場合と比べて新規処方数が2.5倍になることが示されています。
ただ、製薬企業が制作するコンテンツの77%はほとんどあるいは全く使われておらず、面談でのコンテンツの使用率も39%にとどまります。現状では、大量に作られたコンテンツの大半が医療従事者とのコミュニケーションに活用されておらず、作る側のマーケティング部門、使う側の営業部門の双方に取り組むべき課題があると考えています。
使われない理由は?
コンテンツが使われない理由としては、「有用なコンテンツがない」「MRが使う必要がないと判断している」「コンテンツの存在が把握されていない」といったことが考えられ、まずはそれを各社できちんと把握することが必要です。理由は会社によっても違うでしょうし、使われていないコンテンツの種類や内容も各社さまざまだと思います。
個人的には、コンテンツを使うかどうかはMRの判断に委ねられているケースが多く、結果として大半のコンテンツがあまり活用されない状況に陥っているのではないかと思っています。もちろん、最前線で日々、医師と接するMRが、医師のニーズを踏まえた上で使う/使わないを判断するのは良いことです。ただ、コンテンツの意図がきちんと伝わらないまま「これは使えない」「この医師には合わない」と判断しているとしたら、もったいないなと思います。
作る側としては、各コンテンツを医師のジャーニーに落とし込んだ上で、何を意図して作ったのか、どんな医師に使ってほしいのかといったことを営業現場に伝えていくことが必要です。MRはそれを理解した上で使う/使わないを判断し、使わないのであればその理由をフィードバックすることが重要でしょう。前回、オムニチャネル化に向けた営業とマーケティングの連携についてお話しましたが、コンテンツにおいても両者が協力して医師のニーズに応じた現場でも使いやすものを作っていくことが求められます。
MRの数が減り、1人あたりの対応範囲が広がる中で、これからもMRが一人ひとりの医師の反応を見ながらコンテンツの出し分けを細かく判断するのは難しくなるかもしれません。デジタルチャネルのアクセスログやAIを活用しながらMRの判断を支援していくことが必要になってくるでしょう。
医師の情報に対するニーズは多様化しており、全ての医師にヒットするコンテンツを作ることは不可能です。ある程度の無駄は仕方ないのかもしれませんが、だからといってそれをどこまでも許容できるわけではありません。効率化に向けては、コンテンツを要素ごとに細分化(モジュール化)し、医師のニーズに応じて組み合わせて使う「モジュラーコンテンツ」の検討が進んでいくでしょう。
| 山下篤志(Veeva Japan コマーシャルストラテジー バイス・プレジデント)大学卒業後、システムエンジニアやITコンサルタントとしてヘルスケアなど様々な分野のプロジェクトに携わる。前職の製薬企業ではCRM導入プロジェクトをリードし、オムニチャネル促進にも尽力。製薬業界全体のDXに貢献したいとの思いから2022年にVeevaに入社し、製薬企業のコマーシャル部門の支援に取り組む。製薬業界とITの両分野に精通し、セミナー登壇やメディア寄稿も多数。
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/atsushi-yamashita-47965686/ |