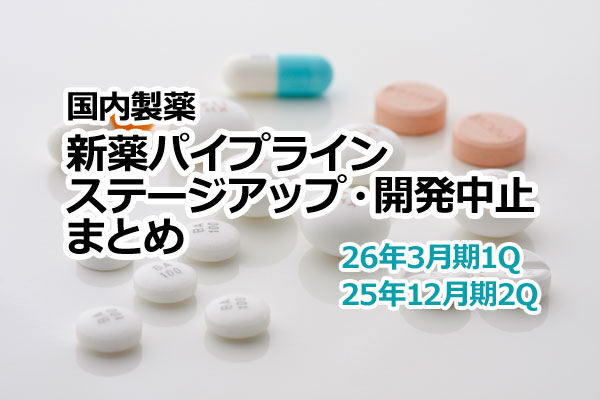記者会見したPhRMAのシモーネ・トムセン在日執行委員長
米国の製薬業界が、薬価制度をめぐる日本政府の「手のひら返し」に不満を強めています。米国研究製薬工業協会(PhRMA)のシモーネ・トムセン在日執行委員長(日本イーライリリー社長)は4月8日の記者会見で「岸田政権でイノベーション促進への期待が高まったが、石破政権で薬価中間年改定が行われ完全に裏切られた」と批判。政府が今年度設置する「官民協議会」も、薬価制度の見直しがなければ「無駄な努力になる」と警告しました。
「石破政権で期待裏切られた」
「われわれも突然の政策変更に困っているし、驚いている。アドホック的な決定で、非常に予見が難しかった」。トムセン氏は会見で、石破政権が2025年度中間年改定を行ったことに強い不満を表明しました。
前任の岸田政権では、製薬業界に政策的な強い追い風が吹きました。ドラッグ・ロスが顕在化し、日本の医薬品産業の国際競争力低下が叫ばれる中、政府は24年度の薬価制度改革でイノベーションに対する評価を拡充。同年7月には、国内外の製薬企業や業界団体を首相官邸に招いて「創薬エコシステムサミット」を開催し、ドラッグ・ロス解消と創薬力強化に向けた政策目標を発表しました。海外から開発投資を呼び込むための策を検討する「官民協議会」の設置も打ち出されました。
こうした経緯もあり、25年度の中間年改定をめぐっては、一時、廃止の機運も高まりました。しかし、岸田氏の後を継いで昨年10月に発足した石破政権は、予定通り中間年改定を行うことを決定。過去2回の中間年改定より対象品目は減ったものの、特許期間中の新薬では全体の4割以上が対象となり、中間年改定では初めて新薬創出加算の累積額の控除も行われました。
トムセン氏は「岸田政権でイノベーションを促進するような政策をとろうということになり、会員企業は日本への投資を増やそうと考え始めた。しかし、石破政権は中間年改定を行い、十分な協議なしに累積額の控除を導入した」と指摘。「(岸田政権で見られた改善への)良い弾みが全てなくなってしまった」と話しました。
欧米P3の新薬、7割が国内開発未着手
PhRMAによると、2014~23年に欧米で発売された新薬のうち245品目が日本で発売されておらす、その半数(124品目)が日本では開発未着手。欧米で臨床第3相(P3)試験が行われている新薬候補601品目のうち、7割(404品目)は日本で開発が行われていません。
さらに、新薬の研究開発に対する投資は、15年から23年にかけて世界でほぼ倍増したのに対し、日本は6%の伸びにとどまっています。この間、世界の新薬への研究開発投資に占める日本のシェアは8.0%から4.2%に半減。世界の投資は30年に15年比142%増となる一方、日本は15%増の予測で、世界シェアは3.8%まで縮小すると見込まれています。
トムセン氏は「日本はドラッグ・ロスの危機に直面しており、事態は加速的に悪化している。研究開発投資も世界に劣っていて、ギャップはさらに拡大していく」と指摘。予見性と透明性を欠く日本の薬価制度がこうした事態を深刻化させているとし、特許期間中の医薬品の薬価を維持する制度改革が必要だと訴えました。
政府は官民協議会を今年夏ごろに開く予定です。トムセン氏は「政府とのパートナーシップで課題解決を図りたい。創薬エコシステムサミットや官民協議会の開催には意を強くしている」とする一方、「創薬、薬事規制の調和、バイオベンチャーのエコシステムなど、官民協議会で話せることはたくさんある。ただ、最終的には薬価の前向きな制度改革がなければ無駄な努力になる」とクギを刺しました。
日本の薬価制度には米国政府も貿易の観点から問題意識を示しており、非関税障壁としてトランプ大統領の関税政策をめぐる協議の俎上に載る可能性もあります。外圧にもさらされる中、中央社会保険医療協議会(中医協)の薬価専門部会では6月ごろから26年度薬価制度改革に向けた議論が始まります。
あわせて読みたい
オススメの記事
-

ウルトラジェニクス、LC-FAOD治療薬トリヘプタノインを申請/MSD、21価肺炎球菌ワクチン「キャップバックス」承認 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年8月8日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り