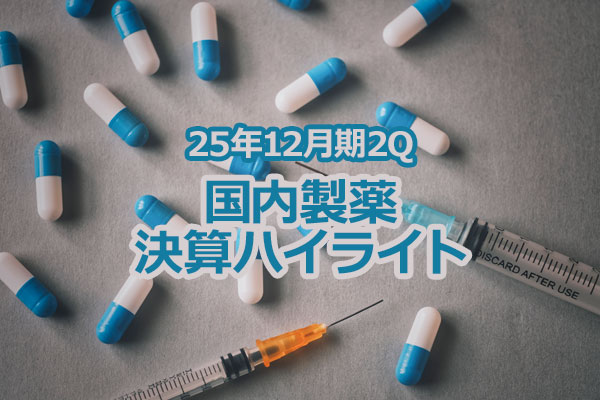2021年度に続き「乖離率が平均の0.625倍超」の品目が対象となる23年度の薬価改定。中間年改定の根拠となっているのは16年12月のいわゆる「4大臣合意」ですが、そこには「価格乖離の大きな品目」を対象に行うと明記されています。乖離率が平均より小さい品目まで対象にすることが4大臣合意の趣旨から外れているのは明白です。
INDEX
根拠不明の「0.625倍超」
2度目の中間年改定となる今年4月の薬価改定は、乖離率(薬価と市場実勢価格の差)が全医薬品の平均の0.625倍を超える品目が対象です。昨年9月取引分を対象に厚生労働省が行った薬価調査の結果、平均乖離率は7.0%だったので、対象となるのは乖離率が4.375%を超える品目。数にすると1万3400品目で、薬価基準に収載されている全医薬品の69%に相当します。
2023年度改定の対象範囲をめぐる議論では、▽平均乖離率の0.5倍超▽0.625倍超▽0.75倍超▽1倍超▽2倍超――について対象品目数や薬剤費削減額の試算が示され、検討が進められましたが、結局は前回の中間年改定を踏襲し、0.625倍超とすることで決着しました。
ちなみに前回は、厚労省が▽平均乖離率の1倍超▽1.2倍以上▽1.5倍以上▽2倍以上―の試算を示す中、政治レベルの協議で0.625倍に決まりましたが、その理由は「0.5倍と0.75倍の中間」。そこにさしたる根拠は見当たりませんし、決定プロセスも透明性を欠いていました。そのような形で決まった「0.625倍超」が今回も引き継がれたことになります。

今回の改定によって削減される薬剤費は約3100億円に上ります。物価高騰や供給不安への特例措置として不採算品再算定による薬価引き上げ(対象品目は1100品目)が、同じくドラッグ・ラグへの特例的な対応として新薬創出・適応外薬解消等促進加算対象品目の引き下げ幅緩和(対象品目は150品目)が行われ、こうした対応を行わない場合の機械的な試算と比較すると影響は1730億円圧縮されました。
製薬業界に一定の配慮がなされた形ですが、それでも薬価収載されている医薬品のおよそ半分で薬価が引き下げられます。特例措置の恩恵を受けられない企業では影響が大きくなりそうです。
「医療の質向上」は実現したか
そもそも、中間年改定の根拠となっている「4大臣合意」(16年12月に官房長官、厚労相、財務相、経済財政相が決定した「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」と題する文書)には「価格乖離の大きな品目について(中間年の)薬価改定を行う」と書かれています(カッコ内は筆者による補足)。
平均を下回るものを「大きい」と言うのは、一般的な感覚では理解しがたいものです。平均乖離率の0.625倍超を対象とした中間年改定は、4大臣合意から想定される範囲を超えていると言わざるを得ません。日本製薬団体連合会は昨年12月、23年度改定の対象について「4大臣合意の趣旨から大きく逸脱したものであり遺憾」との声明を発表しました。業界からは「話が違う」との声も聞かれますが、それも無理はありません。

4大臣合意には、中間年改定のほか、▽年4回の新薬収載の機会を活用した市場拡大再算定の実施▽創出加算の抜本的見直し▽費用対効果評価の本格的導入▽薬価算定プロセスの透明化――などが盛り込まれ、18年度以降これに沿って薬価制度の見直しが行われてきました。
一方で昨今、医薬品供給の土台は揺らいでいます。台頭する新興バイオ医薬品企業を中心に、海外の製薬企業が日本市場を敬遠する動きが鮮明になり、新薬が日本に入ってこない状況を指す「ドラッグ・ロス」への懸念が顕在化。供給不足は長引き、後発医薬品を中心に多くの品目が出荷を停止あるいは制限しています。
関連記事:揺らぐ医薬品供給の土台…「ドラッグ・ラグ」再燃、長引く供給不足|製薬業界 回顧2022(1)
4大臣合意では、「『国民皆保険の持続性』と『イノベーションの推進』を両立し、国民が恩恵を受ける『国民負担の軽減』と『医療の質の向上』を実現する観点から」中間年改定を含む薬価制度改革に取り組むと明記されています。はたして、一連の改革で「医療の質の向上」は実現できたのでしょうか。昨今の状況は、決してそうではないように映ります。
改定対象は4大臣合意を逸脱しながら、4大臣合意を根拠に中間年改定を続けるのは無理があります。「国民皆保険の持続性」と「イノベーションの推進」の両立や、「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」の実現につながっているのか、立ち止まって検証する必要があるのではないでしょうか。なし崩し的に進めるのではなく、4大臣合意の趣旨に立ち返るべきです。