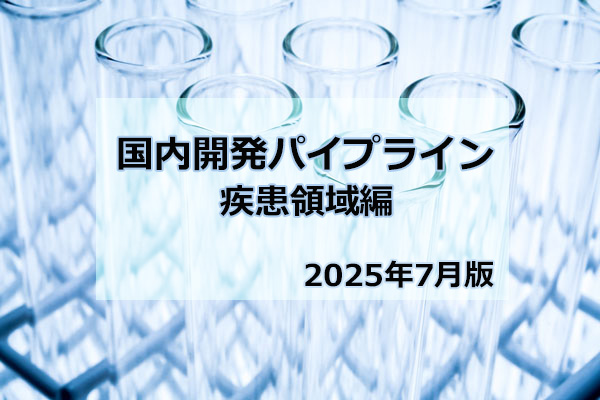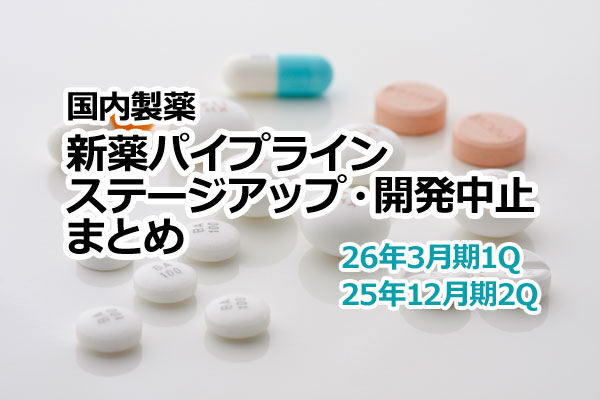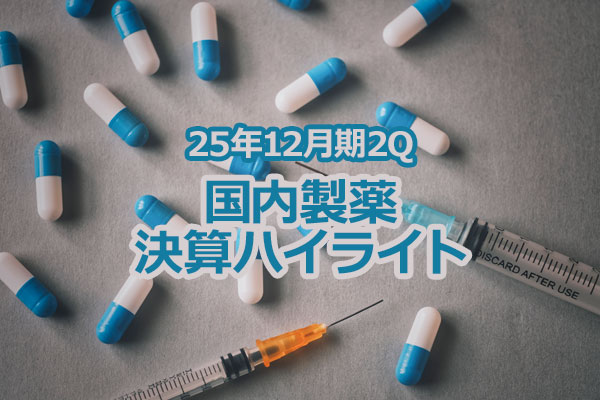前回は、イノベーション創出には新技術や発想の「掛け算」が大切だと書きました。異なる技術や発想を掛け合わせるには、さまざまな技術や発想が出会い、交わる環境が必要であり、流動性を高めていくことがそうした環境をつくる鍵の1つとなります。
ヒト、モノ、カネ、チエをリアルとバーチャルの両方で流動させることがイノベーションにつながると考えていますが、重要なのはやはりヒトでしょう。
米トランプ政権による科学研究予算の削減などがトリガーとなり、米国の研究者が国外に流出していると伝えられています。中国や韓国といったアジアにも移動してきているそうです。中国では海外留学から戻ってきた人を「海亀」というスラングで呼ぶそうですが、最近では米国から帰国した研究者が中国のバイオテックで成功する事例も聞かれるようになってきました。さらには、そうした動きが欧米の経営者を惹き付けている可能性があり、アジアにおけるバイオ技術の振興や投資拡大に寄与するかもしれません。
地域間のみならず、組織間、部門間、異分子間での人の移動は、交流、観察、質問、関連付け、そして実験を生みます。これらは、クレイトン・クリステンセンらが言うところの「イノベーター」の輩出条件に合致します。
1つの会社で勤め上げることを否定しているわけではありませんし、ジョブホッパーになることを推奨しているわけでもありません。
ただ、加速度的に技術や社会が変化する中、よほど意識を強く持って過ごさないと、世界に取り残されるようになっている気がしています。ソフトウェア同様、時代は人にも高頻度でバージョンアップを重ねていくことを要請しています。
1つの企業で勤め上げようと思っても、企業そのものが短命となってきています。S&P500指数に新規採用された企業が除外されるまでの平均期間は、1950年代は約60年でしたが、2010年代には15~20年程度になっていると言われています。
リストラも必要なモメンタム
製薬産業あるいはライフサイエンス産業は安定産業と考えられてきました。しかし、昨今では国内製薬企業の度重なるリストラや(被)買収劇が報じられています。
私を含め、特に昭和世代の人間からすると決して心地よいニュースではないかもしれません。意図せず所属先が変わった人もいると思います。思いがけず職を失ったり、職場が変わったりすることは、多くの人にとってストレスです。
一方、産業界全体からすると、必要となるモメンタムなのかもしれません。個人にとっても、長期的にはプラスになる可能性もあります。
最近、国内屈指の大手製薬企業からスタートアップに転職した方から連絡がありました。話を聞くと「好きな研究に取り組めている」「前の会社では認められなかった自分のやりたかったことが体現できている」と、目を輝かせて話してくれました。傍から見ても、前職時代より楽しそうに見えました。前回、「『初志貫徹』とは最初に掲げた北極星を追い続けることであり、その過程やアプローチに固執することではない」と書きましたが、1つの組織にとどまり続けるのとは違う種類の初志貫徹もあるということです。
蛇足ですが、転職した人の中には「前の会社では~」と前職を引き合いに出してものを語る「ではのかみ」になってしまう人も少なくありません。本人に悪気はなかったとしても、多くの場合、煙たがられてしまうので意識したほうが良いと思います。せっかく流動した先でそっぽを向かれてしまっては、技術や発想の掛け合わせは生まれません。「前の会社では」「海外では」「他社では」とつい口を出したくなる気持ちもわかりますが、「うちはうち、そとはそと」(自省も込めて)。異なる技術や発想が出会い、交わるには、まずは人と人とが互いに謙虚な姿勢で信頼関係を築いていくことが大切です。
日本の製薬業界でも、兼業を認めたり、社外での活動を後押ししたりする企業が増えてきました。こうした取り組みも流動性を高めていくことに役立つでしょう。社員が社外のさまざまな人とつながり、新たなインプットや刺激を得ることは、組織にとっても有用です。
企業も流動起こす仕組みを検討すべき
すでに社内異動、兼業、出向などは存在すると思いますが、特例的にピンポイントに行われるものだったり、企業都合によるものであったりするものが多いのではないでしょうか。社員の自律意思に基づいて流動が可能になるような施策を企業は検討すべきかと思います。例えば、次のような取り組みなどどうでしょう。
▽越境学習プログラムの制度化
他の企業、スタートアップ、NPO、大学、行政機関などへの一定期間の「留学」や「兼業」を制度として設けることで、社員が自発的に多様な経験を積める環境を整備します。「ライフサイエンス×AI」「医療×地方創生」など、特定のテーマを持った公募型のプログラムにすれば、企業にとってもリターンのある投資と位置付けやすくなります。
▽社内タレントマーケットプレイスの導入
社内の人材とプロジェクト案件をマッチングする「タレントマーケットプレイス(社内兼業制度)」を整備し、所属部署にとらわれず個々の興味や専門性に基づいた短期・中期的な越境を促進します。社員が「別部署の1割業務」にチャレンジすることで、新たなスキル習得や異文化理解につながります。専門化と分業化が進む製薬企業では、隣の部門が何をしているかわからないといった状況に陥りがちですが、この取り組みは「サイロ病」への処方薬にもなり得ます。
▽社外メンターとのマッチング支援
兼業・越境の前段階として、信頼できる社外人材(起業家、研究者、業界リーダーなど)との1on1やメンタリングの機会を社費で支援する制度を設けます。閉じた人事評価から離れ、オープンな視座を持つ外部との接点が、個人の自律的キャリア意識を育み、流動のモチベーションにつながります。
▽独立カーブアウト
さらには、戦略的理由から撤退する事業・パイプラインのカーブアウト機会を模索することにも力を入れるべきかと思っています。産業特性から企業の重点領域から外れるアセットが出てしまうのはやむを得ずとも、それらは他企業でインキュベートされる可能性があります。
こうした取り組みには「ノウハウが流出するのでは」との懸念もありますが、守秘義務契約に記載すること、信頼する組織や人々とのワークシェアリングを実施すること(裏返すと、社員も胸を張って兼業をうたえるようにすること)で、リスクを抑えながら流動を起こすことができると考えます。
人の流動による技術や発想の掛け合わせとともに、日本の製薬産業の閉塞感を打破する鍵がもう1つあります。それは、建設的な破壊です。次回はそのことについて書いていきたいと思います。
| 増井慶太(ますい・けいた)インダストリアルドライブ合同会社、BAIOX株式会社CEO。ヘルスケアやライフサイエンス領域の投資運営、M&A仲介、カンパニー・クリエーション、事業運営に従事。東京大教養学部卒業後、米系経営戦略コンサルティング企業、欧州製薬企業などを経て現職。 ウェブサイト:https://www.industrialdrive.biz/ X(Twitter):@keita_masui LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/keita-masui/ Note:https://note.com/posiwid |