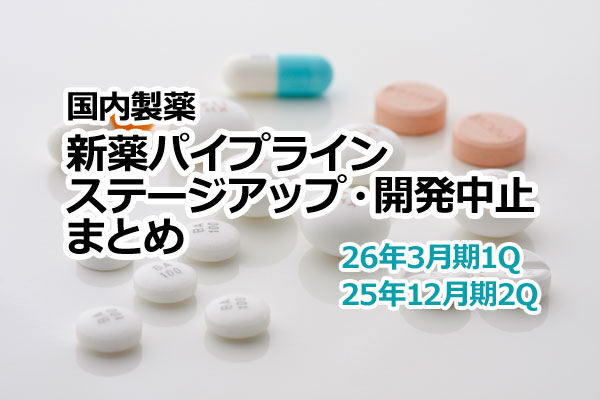製薬業界で、製造機能のデジタル化に対する期待が高まっています。新規モダリティの台頭による製造機能の高度化、品質問題への対応、収益低下に伴う生産性向上の圧力などが背景にあり、製造データの活用やデジタル技術を使ったスマートファクトリー化が注目を集めています。医薬品製造のデジタル化の現状と展望について、デロイト トーマツ コンサルティングで製薬企業の製造機能の改革を支援する上西洋一パートナーと岡部亮一ディレクターに聞きました。
「データはある」だけど「使えていない」
――製薬企業から、製造データの活用やスマートファクトリー化に関する相談が増えているそうですね。
上西洋一氏(デロイト トーマツ コンサルティング・パートナー):製薬業界をとりまく環境の変化を背景に、製造機能の改革に対する機運が高まっています。
新薬メーカーでは新規モダリティへの対応が求められています。新規モダリティを立ち上げていくには、従来の医薬品とは異なるバリューチェンの構築が必要です。たとえば、細胞・遺伝子治療の場合、遺伝子の導入や細胞の培養などものづくりも非常に難しい。一方で治験の規模は小さく、限られた治験薬製造の中でいかに安定した製造条件を導き出すかが課題となっています。
加えて、後発医薬品メーカーでは、品質の確保・向上や安定供給が大きな課題となっている一方で、製造現場では人手に頼ったオペレーションがまだまだ多く、かつ人材の採用・育成にも苦労しています。
こうした背景から、先発・後発問わず製造の生産性向上が求められるようになってきました。課題の一部は製造データを有効に活用することで解決できる可能性があり、引き合いが増えている状況です。
岡部亮一氏(デロイト トーマツ コンサルティング・ディレクター):従来、製薬企業の工場は、安定供給の観点から稼働率を6~7割に設定し、それで市場に十分量を供給できて収益も確保できるというモデルで、生産性に対する優先度は高くありませんでした。しかし、供給不安が起こり、収益性も低下する中、製薬企業の工場も他の製造業と同じように生産性が問われるようになってきています。
技術的なアプローチももちろんありますが、昨今ではデータやデジタルを活用した課題解決のニーズが高まっており、そういったプロジェクトが増えています。課題の大きさと取り組みの難易度から、工場からのボトムアップより本社発信でのプロジェクト立ち上げが多く、経営層からの改革の必要性・課題感を強く感じています。
――医薬品製造におけるデータ活用・デジタル化の現状について、どのように見ていますか。
岡部氏:製薬企業の製造部門はかなりのデータを持っています。業界の特性上、証跡として残しておかないといけないので、各社ともMES(製造実行システム)やLIMS(ラボ情報管理システム)といったシステムを導入し、そこに製造関連データをストックしています。
ただ、それらは基本的には、トラブルや品質問題など何かあった時に参照するためのもので、定常的に可視化・分析・活用することが前提にはなっていません。それゆえにデータ利活用が進んでいないのが現状です。皆さん「データはある」と言われますが、「使っていますか?」と聞くと「使ってない」と。そんな状況です。そういった意味では、医薬品製造工場にはデータ活用のポテンシャルがまだまだあると感じています。
上西氏:データ化という点では大手を中心に進んでいるものの、利活用という点ではまだチャレンジがあります。工場専任のデータサイエンティストを配置する企業も出てきていますが、元のデータが使える状態になっていないので、分析をしても結果が現場の感覚とズレてしまい、話が噛み合わないこともあります。いかにデータを意味のある形に整理し、データレイクに格納していくかが、大手も含めて課題になっています。
データを十分に活用できていないために、製造現場の実態を正確かつ迅速に把握できていない企業も多いのではないかと思います。
例えば、後発品メーカーは1つの製造ラインで何種類もの製品をつくるので、計画も複雑になりがちです。結果として、実際に工場で行われている製造と、プランナーが手元のエクセルで見ているものに乖離が生じやすく、そのエクセルを集約して「これが現場の最新状況です」と経営に報告しても、それは現場の実態を反映していないものになってしまいます。安定供給に向けて、より正確かつ柔軟な生産計画の見直しが必要となっている一方、経営は適切な意思決定ができず、誤った判断をしてしまいかねません。

デロイト トーマツ コンサルティング上西洋一パートナー(右)と岡部亮一ディレクター
システムはデファクト化し業界全体で底上げを
――製薬業界は他業界に比べてデジタル化が遅れていると言われてきました。データの活用やスマートファクトリー化を進めていくには何が必要ですか?
上西氏:製造機能はいまや単なるコストセンターではなく、ビジネスの継続性や競争優位性を左右する重要な要素です。お話してきた通り、データやデジタルを使って製造現場を可視化し、効率化・コスト削減を追求していくことは間違いなく重要です。
加えて、新規モダリティの立ち上げ、CMO/CDMOの活用、業界再編に向けた他社との連携・統合など、ビジネスのトランスフォーメーションを推進していくには、製造機能を従来とはちがう見方で評価をしていく必要もあります。そのことを経営層が認識し、改革をリードしていくことが重要です。
とはいえ、システムを導入したり、設備を変更したりするにはお金もかかるので、投資余力がない企業もあると思います。特にシステムについては業界全体でデファクト化し、安価に導入できるようにしていくべきですし、われわれもそれをやっていきたいと考えています。
個人的には国の支援も必要だと思っています。最近では、ワクチンとバイオ医薬品のデュアルユース製造設備や、安定供給のための後発品の製造設備などに補助金が付けられています。これも重要ですが、システムへの投資も支援していただきたい。そこで得られたデータの一部は、行政もモニタリングできるような枠組みにすれば、製造現場への立ち入り検査・査察の対象を効率的に炙り出すこともできるかもしれません。結果として、国全体として医薬品の品質や安定供給の確保に役立てることもできます。
各社ばらばらに取り組むのではなく、業界あるいは国を挙げて、デジタルを通じて生産性や品質管理体制を底上げしていくことが必要なのではないでしょうか。
岡部氏:もう一つの考え方として、製薬業界ではなく他業界について学ぶということも今後は重要になってくると感じます。
製薬業界はある意味では特殊なビジネス環境に置かれており、特有の制約もあるため、業界の常識に縛られている部分があります。ただ、効率化の手法やデジタル技術・データの活用など、他業界では当たり前に行われていることが参考になるケースもあるのではないでしょうか。
製薬という特殊性はある一方、考え方など取り入れられるものはあるはずです。製薬企業と議論していると、よく「ほかの製薬企業はどうしているか」と聞かれますが、横だけではなく、その外側も見ていくことも重要です。
――データやデジタルの活用は、後発医薬品産業の再編に向けても1つのカギになりますか。
上西氏:昨年、厚生労働省の検討会が報告書をまとめ、再編に向けた方向性が示されました。ただ、われわれが後発品メーカーを行脚している中では、まだまだ業界の声に耳を傾けていく必要があると思っています。
もちろん行政も、薬価や薬事などさまざまな面で取り組みを進めていますが、それでも後発品メーカーには再編に後ろ向きな声も少なくありません。理由の1つとしてよく聞かれるのが、各社の品質管理体制のギャップです。ここに大きな開きがると、再編後に自社と同じレベルまで引き上げるのは非常に大変で、そこまでして製造のキャパシティを増やす必要があるのかという声も聞かれます。
デジタル化だけで解決できるわけではありませんが、業界全体として製造のケイパビリティを上げていかないと、再編によってキャパシティは間に合ってもケイパビリティは足りないという状況になってしまい、供給問題の解決には必ずしもつながらないと感じています。
あわせて読みたい
オススメの記事
-

ウルトラジェニクス、LC-FAOD治療薬トリヘプタノインを申請/MSD、21価肺炎球菌ワクチン「キャップバックス」承認 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年8月8日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り