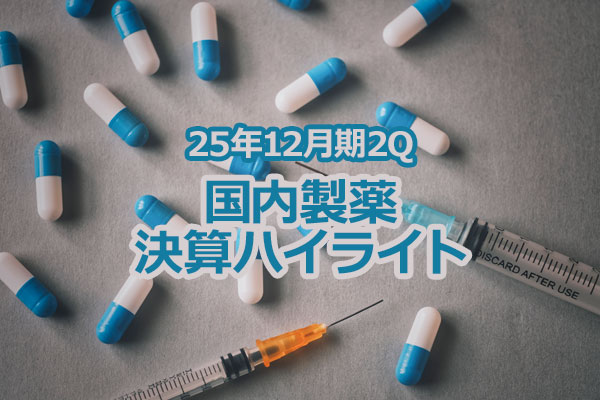アストラゼネカが売上高国内トップに肉薄しています。2024年の薬価ベース売上高(IQVIA調べ、販促会社レベル)は前年比3.3%増の5141億円で2位となり、首位・中外製薬との差は約190億円まで詰まりました。切れ目ない新薬の発売や適応拡大により、この5年間で業績が着実に拡大。抗体薬物複合体や二重特異性抗体など新たなモダリティも開発の最終段階に入っており、主力のオンコロジー領域を中心にさらなる攻勢をかけます。
首位・中外とは190億円差
アストラゼネカがIQVIA集計による販促会社レベルの売上高ランキングで2位となったのは、23年に続いて2年連続。23年はトップの中外と500億円の差がありましたが、1年で一気に半分以下まで縮めました。5年前の19年は3787億円でランキングは5位。この間の年平均成長率は6.3%で、市場全体の1.6%を大きく上回っています。
主力の抗がん剤「タグリッソ」、がん免疫療法薬「イミフィンジ」、SGLT2阻害薬「フォシーガ」はいずれも薬価ベースの売上高が1000億円を超え、24年の製品別売上高トップ10に入っています。3製品の合計売上高は3189億円に上り、全体の62%を占めました。ただ、イミフィンジは昨年2月に特例拡大再算定で25.0%、同年8月に用法用量変化再算定で11.1%の薬価引き下げを受け、年間売上高は1.1%の減収を余儀なくされました。
売り上げを疾患領域別に見てみると、「呼吸器・免疫疾患」が18%増、「循環器・腎・代謝疾患」13%増と好調だった一方、「ワクチン・免疫療法」は15%減。イミフィンジがブレーキとなった「オンコロジー」も1%減でしたが、5年前と比べると65%増加しており、24年は同領域で売上高トップに躍り出ました。

24年は、乳がん治療薬「トルカプ」(ピーク売上高予想103億円)、RSウイルス感染症予防薬「ベイフォータス」(同179億円、売り上げは共同開発したサノフィが計上)の2つの新薬を発売。日本が世界初承認となった新型コロナウイルス感染症の発症抑制薬「カビゲイル」は、予防薬のため保険上の扱いが決まっていません。
グローバルは30年に売上高800億ドル目標
英アストラゼネカの24年のグローバル売上高は前年比21%増の540億7300万ドル。30年にはこの約1.5倍に当たる800億ドルを目指しています。薬価ベースの国内売上高と直近の為替レート(1ドル=143円)をもとに日本の占める割合を計算すると6.6%となり、仮にこの比率が30年まで維持されれば国内売上高は7500億円程度に拡大することになります。
ただ、こうした試算は為替レートに左右されることもあり、堀井貴史社長は4月14日の業績発表会見で「引き続き新薬を届けることで、グローバルに対して従来と同じような貢献をしていきたい」と述べるにとどめました。グローバルでは30年に向けて20新薬の発売を目指しており、日本でも遅れることなく市場投入していきたい考えです。
一方で、30年に向けては減収要因もあります。フォシーガは2型糖尿病の適応の特許が今年4月で満了。後発医薬品は8月承認・12月薬価追補収載の可能性があります。売り上げに占める2型糖尿病での使用割合は5割に満たず、かつ‟虫食い“での参入になるとはいえ、少なからず影響を受けるとみられます。残る適応症の慢性心不全と慢性腎臓病でも28年5月に特許切れを迎える見通しで、薬価ベース1000億円を超えたブロックバスターも30年に向けて徐々に市場を明け渡していくことになります。

アストラゼネカの堀井貴史社長
ADCや二重特異性抗体などP3、肥満症にも参入
アストラゼネカは19~24年に国内で13の新薬と29の適応拡大の承認を取得。30年までには新薬と適応拡大をあわせて40以上の承認取得を目指すとしています。
現在、日本で進行中の開発プロジェクトは103に上り、臨床第3相(P3)以降が61を数えます。領域別ではオンコロジーが66と半分以上を占め、循環器・腎・代謝や呼吸器・免疫疾患などの「バイオファーマ」が37あります。
今後は、注力領域のオンコロジーを中心にモダリティを拡張し、新たに「ウエイトマネジメント」への参入を目指します。

新たなモダリティでは、オンコロジーで6つの抗体薬物複合体(ADC)が臨床開発段階にあります。胃がんを対象に開発中の抗CLDN18.2 ADC「AZD0901」(開発番号)がP3試験、卵巣がんでの承認取得を目指す抗FRα ADC「AZD5335」がP2試験を実施中。ADCは特に開発競争が激しい分野ですが、大津智子研究開発本部長は「複数の自社抗がん剤を(ペイロードとして)活用できることが特徴」と説明。「この分野をリードしたいという並々ならぬ思い」があると話しています。
ADCの開発では、病理組織標本を顕微鏡ではなくデジタル画像で観察する「デジタルパソロジー」の導入も模索。効果が得られやすい患者を的確に選別できる取り組みも進めており、そのために専門チームも設置しました。ADC開発では第一三共と提携していますが、自社品の開発も加速させます。
オンコロジーではさらに、次世代がん免疫療法として2つの異なる免疫チェックポイント分子を標的とする二重特異性抗体や、CAR-T細胞療法、二重特異性抗体によるT細胞エンゲージャーを開発。CAR-T細胞療法はまだP1試験の段階ですが、PD1とTIGITをターゲットとするrilvegostomigや、がん細胞のCD19とT細胞のCD3に結合するAZD0486といった複数の二重特異性抗体がP3試験に入っています。
肥満症 経口GLP-1などP2
新たなフォーカス領域とするウエイトマネジメントでは、経口GLP-1受容体作動薬「AZD5004」(P2)や、長時間作動型アミリンアナログ「AZD6234」(P2)など、開発準備中のものも含めて複数の新薬候補を抱えています。肥満症治療薬は将来的に市場規模が1000億ドルに達するともいわれ、開発競争は熾烈。先行するAZD5004やAZD6234は、既存製品に対する競争優位性を見極めながら開発を進めていく考えです。
同社は心不全など循環系疾患を得意分野とする中で、そうした疾患の原因となるウエイトマネジメントに問題を抱える患者が多いことから参入を決めたといいます。