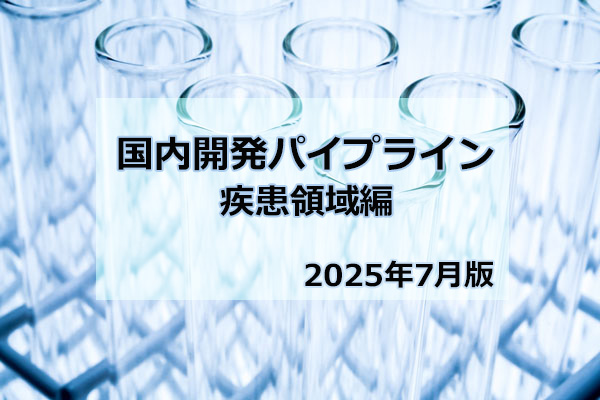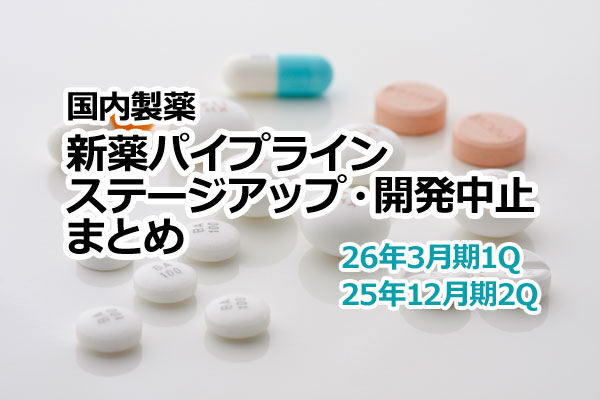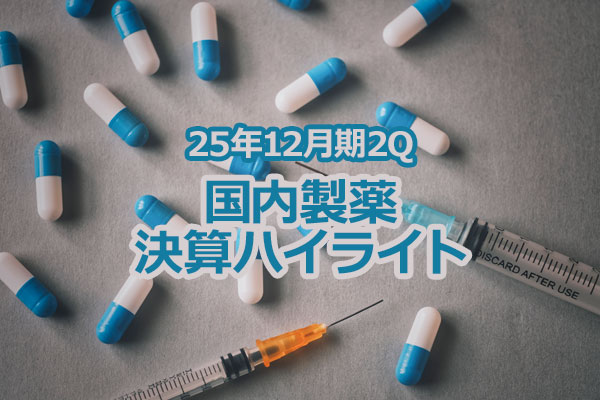アステラス製薬は2月21日、投資家や報道関係者向けに開いたサステナビリティ・ミーティングで、経営戦略に紐づいた組織・人材への取り組みについて説明。女性管理職比率など株式時価総額に影響を及ぼす非財務指標や従業員エンゲージメントの現状、次世代リーダー候補の育成策などを明らかにしました。同社は2025年度までの経営計画で「時価総額7兆円」を目標に掲げていますが、株価は低迷しています。今後、必要な改善を進めて企業価値の向上に結び付けたい考えです。
女性管理職比率、時価総額と正の相関関係
アステラスではこれまで、ESGの取り組みとしてさまざまな非財務活動を行ってきました。ただ、それらが企業価値の向上にどの程度つながっているかは定かではなく、ステークホルダーから疑問の声が寄せられることもありました。
そこでアステラスは、非財務活動の中から「人材・組織」と「コーポレートガバナンス強化」の2つに焦点を当て、取り組みと企業価値との関連性を調査。東証プライム上場企業約1700社の公表データを使い、独自の分析で時価総額に関連する指標を抽出しました。その結果、時価総額には「純利益」「総資産」「営業キャッシュフロー」「平均出来高」「売上総利益率」といった財務指標が強く影響を与えるものの、その次に位置するのは「女性管理職割合」であることが明らかになりました。
女性管理職割合と時価総額の関係を試算すると、25~40%の間で上昇が示唆されたといいます。一方、同社の「経営基幹職に占める女性社員の割合」は、24年6月時点で18%とギャップがあります。国内の女性管理職割合については改善を進めてはいますが、管理職候補に男性と女性がいた場合、無条件に女性を選ぶといった手法は取ってこなかったことも要因にありそうです。
岡村直樹社長CEOは「機会は均等に平等に、実際に人選や指名にあたっては個人の能力や過去の経験、仕事に対する意欲などを公平公正に評価する」と強調。女性管理職を増やすことそのものを目的とするような「本末転倒がないように注意する」としました。取締役会メンバーの女性割合は24年6月に45%(11人中5人)に達しており、政府の「女性版骨太の方針2024」で示された「30年までに30%以上」をクリアしています。
管理職比率が上昇すると時価総額は減少
女性管理職割合のほかに時価総額と正の相関関係が見られた非財務指標は「従業員の働きがい」「企業経営状況への社員の評価」「取締役に支給された報酬の平均額」など。一方、男女あわせた全体の「管理職比率」は、時価総額と負の相関関係にあることが示唆されました。
アステラスの分析によると、管理職比率が1%上昇すると翌年度の時価総額が0.33%、額にして約92.4億円減少するといいます。同社は組織をフラット化して迅速な意思決定を行うため、社長からの階層数を6段階以下にとどめるとともに、スパン・オブ・コントロール(1人のマネジャーが管理する部下の人数)を6人以上とすることを目指しています(24年4月時点では5.9人)。岡村社長は「管理職比率(の高さ)が企業価値とは反対であり、(自社の考えは)間違った方向ではなかった」と話しました。
21~25年度の経営計画の達成に向けては、経営戦略に基づく人材採用と育成にも力を入れています。実際の経営課題に挑戦する次世代リーダー育成プログラムを開始しており、社内外の優秀な人材をできるだけ早い段階で採用・登用し次長クラスに配置。タレントを社内で育てながら、さらに上のポジションに昇格させています。
次世代リーダー候補には「ネクストジェネレーション・リーダーシップ・プログラム」による6カ月間の研修が行われます。グローバルから選抜された50人が参加し、座学ではなく、実際のビジネスに直接インパクトを出せる実践的な課題に対して6カ月かけて解決策を検討。経営陣に発表し、承認された提案はビジネスプロジェクトとして動き出します。杉田勝好副社長人事・コンプライアンス担当は「タレントを育成するだけでなく、次世代リーダー候補の知恵を結集し、ビジネスの成長にすぐに生かせる取り組み」と話します。
相次ぐ変化、社員に「疲れ」も
アステラスは年1回、従業員の会社に対する意識・愛着心を調べるグローバル・エンゲージメント・サーベイを実施しています。これまでは主な項目でスコアを着実に上げてきましたが、24年度の調査では「エンゲージメント」に関わるスコアが前年度の71点から69点へと2点低下。具体的には「会社は従業員と十分なコミュニケーションをとっている」がマイナス6点、「会社の従業員に対する昇進の方針や制度を理解している」がマイナス5点、「会社は率直で正直なコミュニケーションを行う」がマイナス4点などとなりました。

杉田副社長は「さまざまな組織や制度の大きな変更を迅速に推進してきた中で、従業員の理解を深める対応が十分でなかった」と振り返りました。同社は23年度の早期退職や、24年4月の国内営業組織見直しなど、組織面での改革を相次いで実施。杉田氏は「トップマネジメントやシニアリーダーの思いをきちんと現場社員に伝えるといった、変化に関するコミュニケーションがうまくできていないという課題が浮き彫りになった」とし、スコアの低下を真摯に受け止めると話しています。
エンゲージメントを高めることは人材の潜在能力をフルに発揮させるとともに、優秀な人材の流出を防止することになります。岡村社長も「次から次へと変化するので、社員が疲れているとの声が聞かれる。きちんと対処し、組織にダメージを残したり、持っていたケイパビリティを失ったりしないように注意しながら進めたい」と語りました。
中山美加社外取締役は「ここ1~2年の人事的施策や組織改編を見ると、回答自体は従業員の素直な気持ちを反映しており、一時的には自然な流れと受け止めている」と分析。従業員に会社の方向性を理解してもらう原動力にできるとの期待感を示しています。
アステラスの株式時価総額は2月26日終値で約2兆7000億円。経営計画で成果目標に掲げた株式時価総額7兆円とは、なお大きな乖離があります。
AnswersNews編集部が製薬企業をレポート
あわせて読みたい
オススメの記事
-

キッセイ、米社から甲状腺眼症治療薬を導入/参天、緑内障・高眼圧症薬ネタルスジルメシル酸塩を申請 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年7月30日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り