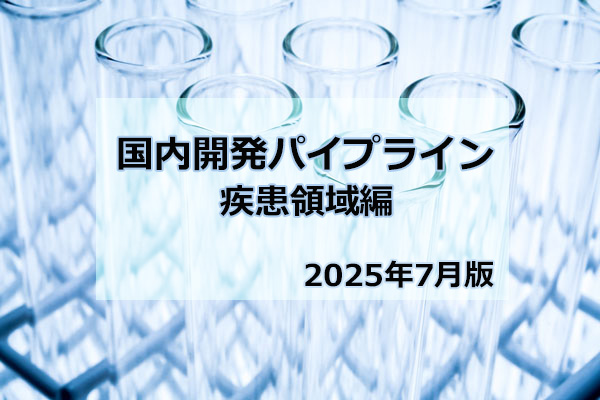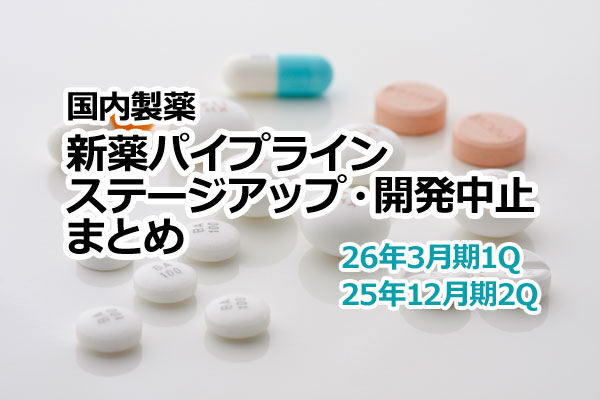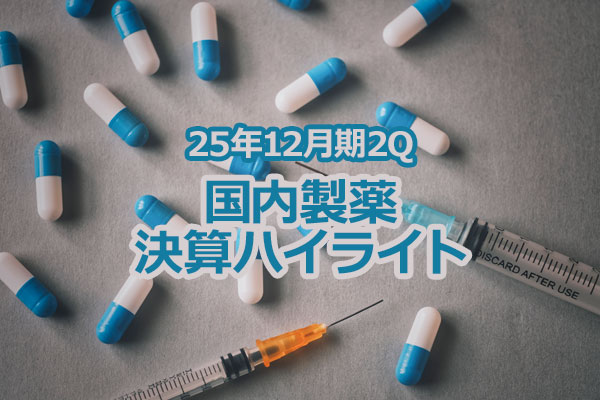2024年12月に決算期を迎えた国内製薬4社の業績が出そろいました。売上収益は4社あわせて11.8%増となり、中外製薬を除く3社が2桁増収を達成。大塚ホールディングス(HD)と鳥居薬品の業績は、中期経営計画を上回る進捗を見せています。
中外、海外売上収益が初めて国内上回る
中外製薬は売上収益が1兆1706億円で、伸び率は4社の中では最も低い5.3%となりました。ただ、昨年10月に発表した修正予想は上回り、売り上げ、利益ともに過去最高を更新。営業利益は5420億円と初めて5000億円台に乗せました。前期に812億円を計上した新型コロナウイルス感染症治療薬「ロナプリーブ」の政府納入がなくなったものの、血友病A治療薬「ヘムライブラ」のロシュ向け輸出が947億円増の3035億円まで拡大。国内事業の2桁減収を海外売り上げでカバーしました。
この結果、海外売上収益が初めて国内を上回り、その比率はおよそ6対4となりました。ヘムライブラ以外では、抗がん剤「アレセンサ」も輸出を拡大。関節リウマチなどの治療薬「アクテムラ」は23~24年に欧米でバイオシミラーが参入しましたが、浸透スピードは緩やかで増収を確保しました。

逆に国内は、ロナプリーブによる一過性の売り上げ増を除けば、ここ数年の業績はほぼ横ばいです。24年12月期は、がん領域の主力である「テセントリク」が0.2%減で、バイオシミラーの影響を受ける「アバスチン」は32.1%減と落ち込みました。業績好調の中外でさえ、国内での成長は難しいのが現実です。
営業利益は、ロナプリーブがなくなって自社品の比率が上がったことで、原価率が42.3%から33.9%に大きく改善。営業利益率は6.8ポイント増の46.3%まで上昇しました。ここでも輸出が貢献しており、為替による押し上げ効果が699億円ありました。
協和キリン、1000億円突破のR&D費が利益圧迫
協和キリンは売上収益が12.1%増でしたが、コアベースで開示する営業利益は1.4%減となりました。低リン血症治療薬「クリースビータ」や抗がん剤「ポテリジオ」といったグローバル戦略品は順調に成長しましたが、研究開発費が前期比314億円増えて1000億円を初めて突破。増収を打ち消しました。
研究開発費の増加は、アトピー性皮膚や結節性痒疹の適応で臨床第3相(P3)試験を進めている抗XO受容体抗体ロカチンリマブ(一般名)の開発進展や、昨年の英オーチャード買収などが要因。ただ、宮本昌志社長CEOは「成長投資が最優先」としており、25年12月期は前期をさらに上回る1070億円の研究開発費を見込んでいます。
販売面では北米市場が著しい伸びを見せています。海外売上収益比率は21年に50%を超え、24年は72%まで拡大。そのけん引役が北米で、24年は売上収益全体の44%にあたる2204億円を売り上げました。25年の業績予想は減収減益ですが、北米はクリースビータとポテリジオの拡大によって引き続き売り上げを伸ばす見通し。一方、全体の3割を切った日本事業は停滞が続いており、宮本氏は「日本事業が今まで通りにいかないということは考えている。パイプラインも見た上で今後どうしていくか考える」と話しています。

同社の中期経営計画は今年が最終年。「コア営業利益率25%以上」などとする財務KPIは、研究開発投資がかさむことなどから未達となりそうで、26年以降に持ち越します。同社は現中計と同時に発表した2030年ビジョンに向けて事業構造の再構築を進めており、引き続き踏み込んだ研究開発投資を行っていく考え。ただ、自社単独で進めるのは「骨・ミネラル」「血液がん・難治性血液疾患」「希少疾患」に絞り、それ以外は外部とのパートナーシップを活用していくことにしています。
大塚HD 5カ年の中計、初年で中間目標クリア
大塚HDは24年から5カ年の新たな中計がスタート。中計では、抗精神病薬「レキサルティ」と抗がん剤「ロンサーフ」を「コア2」と称して成長のけん引役に位置付けています。
24年の業績は、この2製品が期待以上の実績を上げるなどした結果、売上収益は15.4%増の2兆3299億円となりました。営業利益は、米国子会社に関わる税負担の軽減があり2.3倍に増加。売り上げと各段階の利益はいずれも過去最高を更新しました。
医療関連事業の売上収益は17.1%増の1兆6290億円に達し、アステラス製薬や第一三共に迫っています。コア2以外にも、持続性抗精神病薬「エビリファイメンテナ」と腎疾患治療薬「ジンアーク」が拡大。国内も5.6%増の4349億円と堅調でした。
大塚HDは今期も増収を見込みますが、研究開発費の増加やジンアークの特許切れもあってコア営業利益に相当する事業利益は前期を下回る見通し。純利益も前期にあった米国子会社の税負担軽減がなくなることで19.9%減を予想しており、決算発表後に株価は急落しました。
中計では28年の売上収益を2兆5000億円、事業利益を3900億円に設定しています。為替の前提は1ドル=130円、1ユーロ=140円で、実際には円安に振れたこともあり、すでに折り返しにあたる26年の目標額はクリアしました。医療関連事業の今期売上収益は1兆6450億円と増収を予想。1月1日に就任した井上眞社長は、「ジンアークの特許切れ影響(770億円減)は、直近のトレンドからある程度の上振れが期待できる」と話しました。

4期連続増収の鳥居薬品、中計目標引き上げ
鳥居薬品は着実に業績を回復させています。19年にギリアド・サイエンシズに抗HIV薬を返還して20年にボトムを迎えましたが、その後は4期連続して増収を確保。24年度はアレルゲン領域で「シダキュア」「ミティキュア」がともに2桁増となり、計242億円を売り上げました。競合が激しいアトピー性皮膚炎市場でも「コレクチム」が19.7%増の88億円と健闘しています。20年4月発売の同薬は、ピーク時予想が7年度目50億円でした。
今期は、研究開発費と新製品の販促費がかさむことで、営業利益を39.7%の大幅減と予想。ただ、ローリング方式で毎年更新している中計では、計数指標を昨年の更新時より高く設定しました。将来の導入品獲得に向けた投資を考慮して研究開発費控除前で算出している営業利益は、24年実績の96億円を27年に110~120億円と想定。売上高も604億円から730~760億円まで伸ばしたい考えです。計画策定にあたっては主力品「シダキュア」が26年に薬価の市場拡大再算定を受けることを前提にしています。
同社は2030年に向けた長期ビジョンで、同年に「売上高800億円超」「過去最高の営業利益(133億円、研究開発費控除後)更新」を目指しています。

AnswersNews編集部が製薬企業をレポート
あわせて読みたい
オススメの記事
-

キッセイ、米社から甲状腺眼症治療薬を導入/参天、緑内障・高眼圧症薬ネタルスジルメシル酸塩を申請 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年7月30日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り