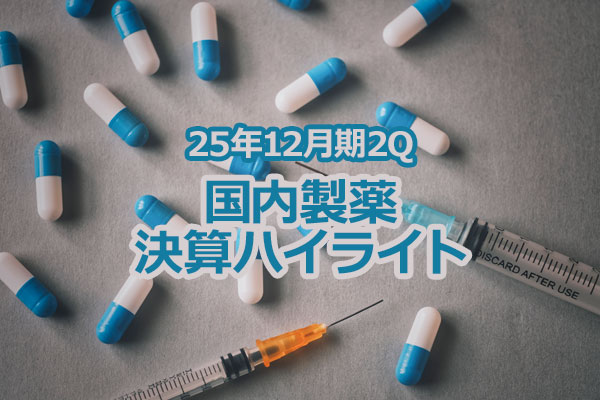国内の大手製薬企業が相次いで人事制度の改革を打ち出しています。経営環境が変化する中、各社は何を目指してどのような制度をつくり上げようとしているのでしょうか。
採用・育成、専門人材に照準
第一三共と塩野義製薬は昨年末、サステナビリティに関する説明会で自社の人的資本戦略を説明。中外製薬は今年1月から新たな人事制度の運用を始めました。
3社に共通するのは、社員の主体的なキャリアデザインを重視する点です。会社はより効果的な人材マネジメントを行い、社員に主体的な成長と挑戦を促すのが基本。グローバル人材やデジタルトランスフォーメーション(DX)人材といった高度専門人材の確保も急務で、各社とも働く場としての魅力を高めることで優秀な人材を引き寄せたい考えです。
企業の競争力の源泉は人であり、人的資本経営への注目も相まって従業員への投資は重要性を増しています。優秀な人材は社内での育成とともに外部からの獲得も必要で、評価・報酬体系をはじめとする人事制度の見直しによってエンゲージメントの向上を目指していることも共通しています。
塩野義、専門人材の経験者採用が大幅増
各社が人材確保で再も重点を置くのが、高度専門人材の採用と育成です。中外製薬は高度専門職のキャリアパスをあらためて体系化し、ポジション数を従来の2.5倍に増やしました。同社は2030年に向けた成長戦略で「デジタル人材やサイエンス人材など戦略遂行上の要となる高度専門人材の獲得・育成・充足に注力する」としており、23年度の有価証券報告書によると高度専門人材の充足率は69%となっています。
第一三共は「バイオ(抗体製造、プロセス開発、品質管理・保証、薬事、製造)」「グローバルビジネス」「DX」の3分野を、獲得・育成を強化すべき専門人材と定義。これら3分野で26年度に計260人+α(バイオ関連の未定部分)を確保したい考えです。23年度の獲得実績は計99人にとどまっており、3年間で約3倍増が目安となります。人材の増強に向け、社内公募(キャリア・チャレンジ制度)を行うとともに、育成のために10億円規模の投資も予定しています。

塩野義はキャリア採用を戦略的に行っていく方針を掲げています。「DX」「IT」「グローバル」の各実務経験者を中心に採用活動を強化。従来は年間十数人程度の採用にとどまっていましたが、24年度はすでに50人を超える人材を獲得しました。同年に行った早期退職(301人が応募)も新陳代謝を促すのが狙いの1つで、中期経営計画達成に向けた人材ポートフォリオに変革していきます。
バイオ人材やDX人材はどの企業でも不足しており、キャリア採用も容易ではありません。社外からの獲得と社内での育成をどのように実現して充足率を高めていくのか、各社の抱える課題の1つと言えそうです。
中外 ジョブ型全社員に、異動は原則手挙げ
等級、評価、報酬の制度設計も見直しが進みます。塩野義は23年度に等級制度を変更しました。成長や貢献ができていない人が高いグレードにいることでポジションが詰まり、チャレンジ精神のある若手が満足する処遇を受けられなくなるリスクを防ぐのが主眼です。見直しでは、等級を洗い替えして現在の役割に応じた職務グレードに割り当てる(再格付け)とともに、ハイパフォーマーの処遇を引き上げました。これにより、より高い役割にチャレンジする人を増やしたい考えです。
等級を決める評価は従来、複数年度の積み上げ方式でしたが、よりチャレンジを促すため単年度評価に変更しました。たとえば研究職の場合、複数年度だと一度の失敗でそれまでの実績が「ご破算」になってしまうのではないかといった不安の声が上がっていました。単年度評価に見直すことで、1年で次のグレードにステップアップすることが可能になり、昇格も最短4年でできるようになりました。働き方改革にも着手しており、1日の所定労働時間を45分短縮して7時間とし、選択週休3日制や副業基準の緩和もスタートしています。

第一三共、日米欧で等級・報酬共通化
第一三共は24年度に成果創出や人材育成を主眼とした新評価体系を導入。25年度には日米欧で職務・職責に応じた世界共通の等級・報酬体系を構築します。国や地域で異なる制度のままでは連携がうまくいかないこともあるためで、抗がん剤「エンハーツ」などの抗体薬物複合体(ADC)による急速なグローバル化に対応します。一方、女性の登用は遅れており、女性上級幹部比率は25年度目標の30%に対し24年9月時点でまだ11%にとどまります。
中外は、幹部社員に導入済みのジョブ型人事制度を全社員に適用。異動も原則ジョブポスティング(手挙げ)とすることで、若手でも早期に上位の役職に就くことを可能にしました。ポジションはすべて要件を明確化し、空席は社員に公開。会社主導ではなく「社員の自律的意思に基づく異動」へとシフトし、主体的なキャリデザインを促します。あわせて、26年度には定年を実質撤廃し、会社が認めれば年齢の上限なく正社員と同じ処遇を受けられることになります。
3社はいずれも2030年に向けた長期ビジョンを掲げており、人的資本を向上させる新たな人事制度の構築は、ビジョン達成に向けた戦略の実行に不可欠な要素と言えます。人材を重視する姿勢を強く打ち出し、中途・新卒問わず優秀な人材の獲得につなげることが共通した目標とも言えるでしょう。
第一三共の西井孝明社外取締役(味の素顧問)は昨年12月に開かれた同社のサステナビリティに関する意見交換会で、グローバルマネジメント体制を牽引するリーダーの育成が課題だと指摘。そうした人材が「2030年ビジョンの実現=次期中期経営計画策定に中心的役割を果たすかどうかを期待しつつ注視する」と話しました。次世代の経営に向け、人事・組織改革は急ピッチで進みます。