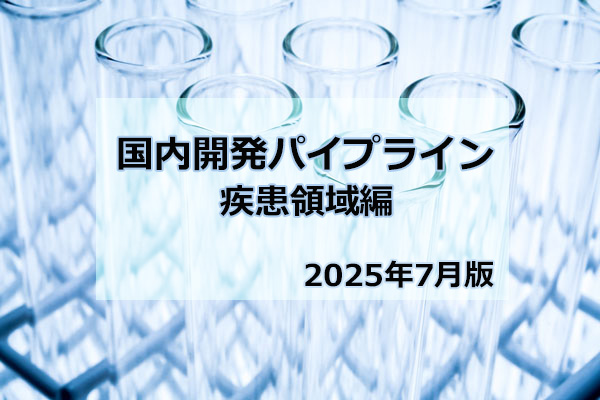経営不振に陥っている住友ファーマが、社長の交代を含む経営陣の刷新を発表しました。2024年3月期に3150億円の最終赤字を計上し、今期も3期連続となる純損失を見込む同社。新体制で立て直しを図りますが、再成長への明確なシナリオはまだ見えていません。
「本当にこんなに伸びるのか」と言われていた「基幹3製品」
住友ファーマは5月14日、木村徹専務執行役員が6月25日付で社長に昇格する人事を発表しました。副社長には住友化学専務執行役員の酒井基行氏が就任する予定。住友ファーマは体制刷新の理由について「早期の業績回復と再成長を果たすため、住友化学から人的支援を受け、新たな社長・副社長を中心とする経営体制に移行することにした」と説明しました。
同社の2024年3月期の業績は、売上収益が前期比43.4%減の3146億円で、最終利益は3150億円の赤字(前期は745億円の赤字)となりました。前期1985億円を売り上げた抗精神病薬「ラツーダ」が特許切れで96.6%減の67億円と落ち込み、これに代わる製品と位置付けた「基幹3製品」(前立腺がん治療薬「オルゴビクス」、子宮筋腫・子宮内膜症治療薬「マイフェンブリー」、過活動膀胱治療薬「ジェムテサ」)の販売も想定に届かず。マイフェンブリーの特許権や北米事業ののれんなど計1800億円の減損損失を計上し、赤字が膨らみました。

新体制で特別顧問に退く野村博社長は5月14日の記者会見で「コスト削減もしながら基幹3製品を成長させていくということで、われわれとしてできる限りのことはやっているということはご理解いただきたい」としつつ、自身の退任については「結果がすべて」とコメント。厳しい局面で社長を引き継ぐ木村氏は「売り上げが基幹3製品でしっかり回復してくれば再度、成長路線に乗れる。必ず再建できると信じている」と話しました。
中計は見直しへ
住友ファーマが昨年5月に発表した27年度までの5年間の中期経営計画では、23年度を底に業績をV字回復させ、27年度に売上収益6000億円程度、コア営業利益として400億円程度を確保する計画でした。牽引役に据えた基幹3製品は、19年に英ロイバントの子会社を買収して獲得したもので、24年度に2000億円程度まで売り上げを伸ばす想定でしたが、直近の予想はこれを700億円ほど下回ります。
中計公表時点から基幹3製品の販売想定に懐疑的な見方はありました。中計の説明会ではアナリストから「本当にこんなに伸びるのか」との声が上がり、野村社長は「買収時にポテンシャルは検討している。われわれの手元に来たからには伸ばしていく努力をしっかりやっていこうということでこのような目標設定にしている」と応じていました。中計のシナリオは早くも崩れ去っており、同社は新体制の下で見直しを行う方針です。

関連記事:ラツーダクリフに直面する住友ファーマ、中計で描いた「V字回復」の現実味
研究開発費を半減
25年3月期の業績予想は、売上収益3380億円(7.5%増)、コア営業利益10億円。基幹3製品の販売拡大とコスト削減でコア営業利益の黒字化を見込む一方、当期利益はマイナス160億円と3期連続の最終赤字となる見通しです。
基幹3製品は合計で前期比48.3%増の1308億円を計画。これまで計画の未達が続いており、アナリストからはまたも達成可能性を質す声が出ましたが、野村氏は「われわれがこれまでつくってきたガイダンスとはレベルが違う予想だ」と達成に自信を示しています。25年度には1800億円程度まで伸びる想定です。
基幹3製品の拡販とともに取り組むのが、合理化です。米国子会社では23年度に2度のリストラを行い、約2200人いた人員を1200人まで削減。研究開発費も減らし、あわせて1080億円のコストを削減します。
パイプライン絞り込み
研究開発費は23年度の909億円から500億円に圧縮。売上収益に対する比率は15%を切る水準まで下がります。今年1月時点で22品目あったパイプラインは、開発を中止したり他社に導出したりして17品目に絞りました。
住友ファーマは従来、精神神経領域を重点領域の1つとしていましたが、今年3月、大塚製薬と共同開発していた統合失調症治療薬候補ウロタロントなど2品目を大塚の単独開発に切り替えると発表しました。今後はがんと再生・細胞医薬に集中する方針で、がん領域では骨髄線維症治療薬「TP-3654」と急性骨髄性白血病治療薬「DSP-5336」の開発に注力。TP-3654は27年度、DSP-5336は26年度の発売を目指しており(いずれも日米)、ピーク時にそれぞれ1000億円規模と500億円規模の売り上げが期待できるといいます。

国内、リストラに含み
研究開発は製薬企業にとって価値創出の源泉であることは言うまでもありません。同社は「各領域でメリハリの利いた投資配分を行うとともに、グローバルで新たなオペレーティングモデルを確立する」としていますが、研究開発費を半分に減らすという荒治療は同社の将来の成長にどんな影響を与えるのでしょうか。住友ファーマは25年度の研究開発費も24年度と同水準に抑える方針だといいます。
国内事業の先行きも不透明です。23年度の国内売上高は37.6%減の1147億円で、24年度の予想は1003億円(12.6%減)と厳しい状況が続いています。国内の営業体制については従来、販売提携によって人員を維持していく方針を示していましたが、社長に就任する木村氏は「販売品の導入も非常に力を入れて進めているが、なかなか難しいのが日本市場の現状」と説明。住友化学が示す「日本事業の体制スリム化」については「直接、人員削減を意味しているわけではない」としつつ、「売り上げが下がっていく中で過剰感が出てくると思う」とリストラに含みも持たせました。
がんとともに研究開発投資を集中させる再生・細胞医薬は、24年度中に住友化学と立ち上げる新会社に分離し、住友化学主導で事業化を進めることになっています。住友化学の岩田圭一社長はさらに、4月30日の説明会で「薬をつくる、あるいは導入品を選ぶというところで住友化学が貢献できる余地は極めて少ない。導入にも金もかかるが、今の住友化学には出す余裕はない。そういうことが可能となるような最適なパートナーはどこかということも選択肢にあるし、その結果としてシェアが変動することもある」と話し、出資比率(現在は51.76%)を変更する可能性にも言及しました。
会社のかたちが大きく変わる可能性もある中、再成長への明確なシナリオはまだ見えていません。