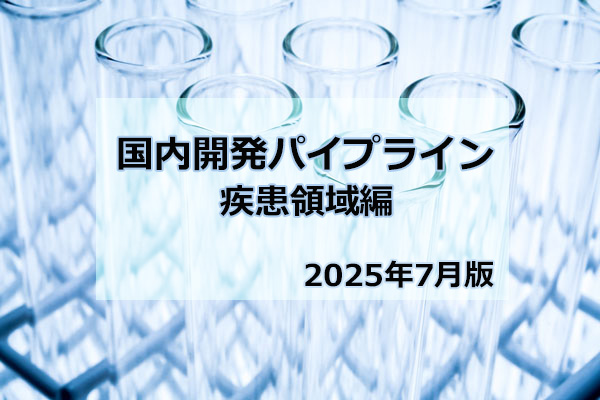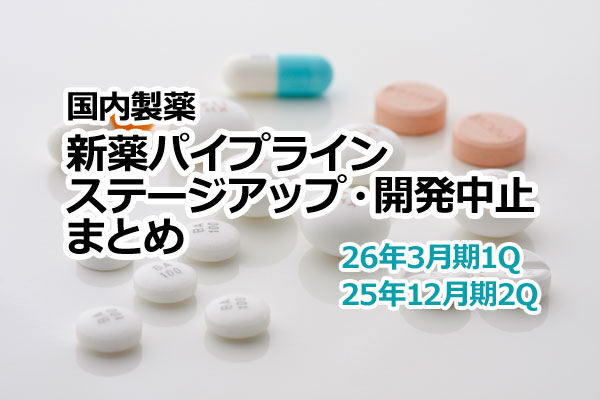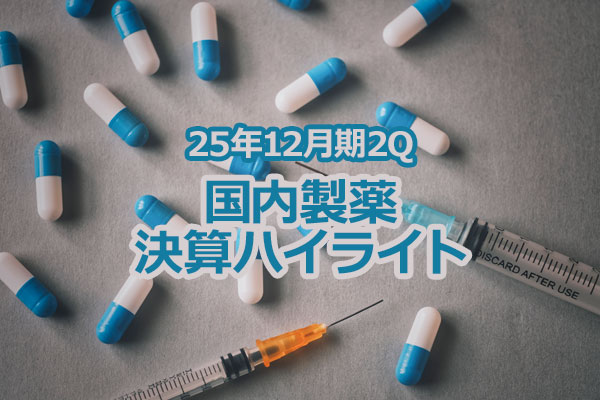10月に行われたアストラゼネカと患者団体のイベントの様子(同社提供)
新薬開発で「患者中心主義(Patient Centricity)」や「患者・市民参画(Patient and Public Involvement=PPI)の重要性が叫ばれる中、製薬企業の間で臨床試験をめぐる情報格差の解消に向けた取り組みが広がりつつあります。アストラゼネカは10月、がん患者団体とともに臨床試験情報の提供のあり方を考えるイベントを開催。現状の課題と解決策を議論しました。
検索サイトを公開
アストラゼネカは、2025年までのビジョンの1つに「患者中心のビジネスモデルのパイオニア」を掲げており、研究開発では、その実現に向けて▽患者のニーズを反映した開発▽患者にやさしい治験▽患者中心の医薬品開発の社内外への情報発信――の3つを柱に取り組みを進めています。

イベントのテーマとなった「臨床試験の情報格差」をめぐっては、臨床試験関連のITサービスを提供するスタートアップBuzzreachと協力して、アストラゼネカが国内で行う臨床試験の情報を検索できる患者向けサイト「Search My Trial for AstraZeneca」を今年2月にオープン。疾患領域、実施エリア、年齢、性別などを指定して検索することができ、参加できる治験がなかった場合も、キーワードと患者自身の情報を登録しておくと将来的に関連する治験が公開された段階で通知を受けとることができます。
臨床試験の情報は、試験を行う医療機関ごとにウェブサイトや院内に掲出されることが多く、患者自ら求める情報にアクセスするのは簡単ではありません。探していた情報が掲載されているサイトにたどり着いたとしても、英語で書かれていたり、専門用語が多様されていることも多く、理解が難しいことも多々あります。
製薬企業の間では近年、自社の臨床試験情報をわかりやすく患者向けに提供しようとする動きが広がっており、ファイザーもBuzzreachを通じてアストラゼネカと同様の検索サイトを展開。アステラス製薬や第一三共、日本イーライリリーなども国内の患者が臨床試験情報を一覧・検索できるサイトを公開しています。
jRCTは「患者にも、医師にも使いにくい」
国内の臨床試験情報を検索できるサイトとして代表的なものに「jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)」がありますが、イベントではCSRプロジェクト(CSR=Cancer Survivors Recruiting)の桜井なおみ代表理事がその使いにくさを指摘。jRCTは国内のあらゆる治験の情報が網羅され、更新性も担保されている一方、検索にはコツが必要で、専門的な表現も多く、患者にとっては検索しにくい上にわかりにくいのが現状です。
jRCTをはじめ、国内の臨床試験情報サイトの多くは使い勝手が良いとは言えず、桜井氏は「患者だけでなく、医療者・研究者も情報を探せていない」と話し、「同じ病院でも、隣の医師がどんな治験を進めているのかわかっていないこともある」と課題の深刻さを指摘しました。
桜井氏は今年、ほかの患者団体とも連携して「臨床試験にみんながアクセスしやすい社会をつくる会」を設立。jRCTの改修を厚生労働省に働きかけています。厚労省とは2025年度をめどに使いやすいサイトに見直すことで合意しており、今後、ユーザーの声も聞きながら詳細を詰めていくことにしています。これとは別に、日本製薬工業協会も今年3月、「治験の探し方~jRCTのみかた~」という患者向けの資料を公開。個別企業のみならず、患者団体や行政、業界団体を巻き込んだ動きが広がりつつあります。
手元にカードを揃えるために
患者にとって治験は貴重な治療選択肢の1つです。天野慎介氏(全国がん患者団体連合会理事長兼グループ・ネクサス・ジャパン理事長)は、それを「トランプのカード」と表現し、患者やその家族から相談を受けたときは「まずは手元にどんなカードがあるか調べて」と伝えているといいます。そこで重要になるのが「今持てるカードがすべて患者の手元に届いているかどうか」ですが、標準治療のない希少がんや難治がんでは、患者自ら治験について調べることや、主治医からの情報提供に限界があるのが実情です。
配偶者をスキルス胃がんで亡くした経験を持つ轟浩美氏(希望の会理事長)は、「そもそも、治験を経て標準治療が作られていることがもっと知られなければ、情報サイトがあったとしても理解に結びつかない」と指摘。「告知を受けたときに『標準治療はありません』と言われましたが、その時は治験や臨床試験というものが存在し、自分で探せるとは知らなかった」と自身の経験を振り返りました。同じような状況で、治験と間違えて民間療法に行ってしまう患者も決して少なくないといい、治験そのものの啓発の重要性を強調しました。
轟氏はまた、患者のリテラシーの向上につながるとして「治験結果をわかりやすくまとめたレイサマリーを被験者以外にも公開してほしい」とも要望。海外で公開が義務付けられていることもあり、被験者や市民に向けた検索サイトは存在しますが、情報を手にしやすいかというと、必ずしもそうではありません。アストラゼネカは来年以降、臨床試験情報サイトでレイサマリーを公開することを考えていると応じました。
マッチングの仕組みを
イベントでは、理想は「治験のマッチングサービス」だと参加者の意見が一致。参加の条件を満たした段階など、患者が必要なタイミングでプッシュ型の情報提供を受け取ることができれば、患者は機会を逃すことなく選択肢を増やすことができるようになります。
一方で、マッチングにはハードルもあります。桜井氏は、海外でこうしたマッチングを行うサイトに登録した際、現在の治療薬の用量の入力を求められたことを明かしました。その時はたまたまカルテの情報開示請求をしていたため入力できたといいますが、そうしたケースは多くはありません。桜井氏は「そういう情報があるのは電子カルテ。マイナンバーカードはこういうところに有効活用できるのではないかと思う」と話しました。
眞島喜幸氏(日本希少がん患者会ネットワーク理事長/パンキャンジャパン理事長)は、欧米の取り組みに感化され、標準治療のない希少がん患者向けのマッチングシステムの構築を試みた際、治験自体が少ないことでつまづいたと話しました。現在、国立がん研究センター中央病院のMASTER KEY プロジェクトと連携し、治験の情報を伝えるイベントを行っていますが、大勢を変えるには及ばないとしました。
臨床試験の情報をわかりやすく届けることは、患者の臨床試験への参加を促し、ひいては新薬開発の加速につながります。業界、行政、患者が協力して取り組みを進めていくことが重要です。