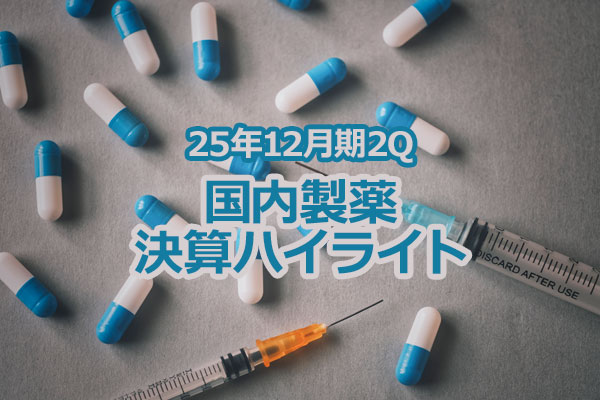がん免疫療法薬「オプジーボ」の特許料をめぐり、ノーベル賞受賞者である本庶佑・京都大特別教授と小野薬品工業が争っていた裁判で、先月、和解が成立しました。法廷では互いに激しく主張をぶつけ合っていましたので、どうなることかと心配していましたが、和解という形で決着したのは、本庶氏と小野薬品だけでなく、日本の産学連携にとっても良かったのではないかと思います。
ご存知の通り、オプジーボは本庶氏の研究室で発見された「PD-1」(免疫応答にブレーキをかける分子)をもとに開発され、「免疫チェックポイント阻害薬」としてがん治療の新たなコンセプトを示した薬剤です。従来のがん治療は基本的にがんそのものを直接狙うものでしたが、免疫チェックポイント分子の研究は「患者さん本人の免疫を利用してがんを叩く」という新しい治療の切り口をもたらしました。オプジーボは米ブリストル・マイヤーズスクイブと小野薬品によって開発され、今やがん治療に欠かせない薬剤として世界中で使われています。
そんな画期的新薬をめぐる本庶氏と小野薬品の軋轢が表面化したのは2019年。本庶氏はこの年の春、記者会見を開いて特許の対価を引き上げるよう訴え、その翌年には、競合薬を開発した米メルクから小野薬品が得る特許使用料の40%を支払うと提案されたのに1%しか支払っていないとして、訴訟に踏み切りました。以来、両者の対立は産学連携の課題を象徴する事例として注目を集めるに至っています。
特許使用料の妥当性
両者が2006年に交わした契約では、小野薬品が直接販売するオプジーボの売上高の0.5%と、他社から受け取るオプジーボ関連のロイヤリティの1%を、ライセンス料として本庶氏に支払うとされていたそうです。ロイヤリティの料率は企業ごと、案件ごとによって異なり、相場を求めるのは難しいですが、一つ言えるのは、こうした契約は「後々の揉め事を回避するためのもの」であるべきだということです。当事者に「あのときの契約は不当だった」と感じさせてしまえば、訴訟沙汰に発展し、企業のイメージに傷がつきます。加えて、小野薬品の場合、米メルクとの特許侵害訴訟も抱えていました。その行方によっては、小野薬品が大きな損害を受け、株主から激しく突き上げられる事態になることもあり得たわけです。
ちなみに、今回の問題を企業の研究者の立場から見てみると、正直な話、「おいおい勘弁してくれよ」と言いたくなる案件です。研究現場のあずかり知らないところ(契約の部分)で、会社を揺るがす大問題になってしまったのですから。訴訟によるイメージの悪化で、(国内だけでなく国外も含む)アカデミアとの共同研究がやりにくくなるのでは、と懸念した研究者もいたことでしょう。
製薬業界では近年、創薬のタネをベンチャーやアカデミアに頼る傾向が強くなってきています。製薬企業が社外の発見や技術を使って新薬を開発する流れは、今後もどんどん加速していくことでしょう。それに伴って、発明の対価が妥当かどうかという問題も、ますます重要になります。
発明の対価をめぐって企業と研究者が対立し、紛争へと発展するケースは少なくありません。ノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏が、青色発光ダイオードの開発をめぐって元勤務先と訴訟合戦を繰り広げたことを記憶している人も多いでしょう。
特に医薬品は開発に巨額の費用がかかる上、失敗のリスクも高く、企業が「対価はなるべく低く抑えておきたい」と考えるのは自然なことかもしれません。一方で、対価の支払いをめぐって研究者といがみ合う姿は企業イメージを悪化させ、それによって失うものも少なからずあります。後々の揉め事を避けるという観点から、企業は発明に十分な対価を支払っているかを慎重に検討する必要がありそうです。
アカデミアの知財化力
今回の訴訟が浮き彫りにしたもう一つの課題が、知的財産に関するノウハウや人材がアカデミア側に不足していたことです。当時の京都大も例外ではなく、PD-1に関する特許は大学ではなく本庶氏本人が小野薬品と共同出願しています。
研究者自身が特許の重要性を認識することは大切ですが、多忙な大学教授にそれを求めるのも酷な気がします。後の紛争を避けるには「その道のプロ」に任せるのが最善ですが、学外との交渉をカバーできる知財担当部署があり、専門人材が業務を担当しているという大学はまだまだ多くありません。このような状態では、研究者が企業に提示されるまま不公平な契約を締結してしまうこともありえます。ビジネスの世界は甘くないですから。
日本では、研究の知財化やビジネス化について研究者を教育する体制も整っていません。特許出願前に学会や論文で発表してしまい、知財化できなくなってしまったというトホホ話は、昔から「アカデミア研究現場あるある」として語られています。製薬業界で創薬のタネを社外に求める流れが加速する昨今、このあたりのサポート体制の整備は急務だと感じます。
国内企業で働く一研究者としては、企業とアカデミアが安心して手を組める環境が整備され、産学連携が活発化することを願ってやみません。
| ノブ。国内某製薬企業の化学者。日々、創薬研究に取り組む傍らで、研究を効率化するための仕組みづくりにも奔走。Twitterやブログで研究者の生き方について考える活動を展開。 Twitter:@chemordie ブログ:http://chemdie.net/ |
AnswersNews編集部が製薬企業をレポート
あわせて読みたい
オススメの記事
-

キッセイ、米社から甲状腺眼症治療薬を導入/参天、緑内障・高眼圧症薬ネタルスジルメシル酸塩を申請 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年7月30日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り