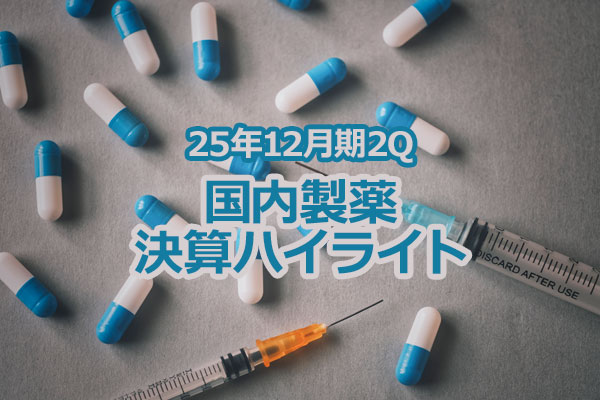ここ数年、注目を集めている「分散型臨床試験(DCT)」。来院に依存しない臨床試験の形が、新型コロナウイルス感染拡大とともに世界で広がっています。日本でも、訪問看護やオンライン診療を活用した治験が増えていて、DCT専門のチームを立ち上げる医療機関も出てきました。訪問と来院を組み合わせた「ハイブリッド型」を中心に普及の足音が近づいてきています。
コロナ禍でDCTが加速
塩野義製薬が急ピッチで開発を進める新型コロナウイルス向けの経口抗ウイルス薬「S-217622」。先月27日に国内で始まった臨床第2/3相(P2/3)試験は、患者が医療機関に来院して行う従来の形式に加え、宿泊療養施設などに医師・看護師を派遣して行う「訪問型」が導入されています。同薬が対象とする軽症患者・無症候感染者が多くいる宿泊療養施設に治験を実施する側が足を運ぶことで、被験者をスムーズに確保し、開発を迅速に進めるのが狙いです。
被験者の来院に依存しない臨床試験は「Decentralized Clinical Trial」(DCT=分散型臨床試験)と呼ばれ、昨今、国内外で取り組みが加速しています。米IQVIAの調査によれば、2020年に世界で実施された4000試験のうち、65の試験がDCTを活用。18年と比べるとその数は2倍以上に増えました。DCTを構成する1要素である遠隔診療(電話診療)だけで見れば、グローバル大手50社の8割以上が実際の治験に採用しており、すでに世界ではDCTの普及期に入ったという見方もあります。国土の広さなどを背景に普及が先行する米国では、DCTの市場規模が21年から28年にかけて年率5.7%で成長し、28年には115億ドルまで拡大するとの予測も出ています。

DCTの遅れによるラグを懸念
日本でも、DCTの要素の1つである訪問看護を活用した治験が増えています。3Hクリニカルトライアルは昨年、9件の在宅治験を受託しましたが、今年は9月時点ですでに20件以上実施。同社の滝澤宏隆代表は、「コロナの影響で急激に案件が増えたのは間違いない。以前の業界は『必要性はわかるが変えられない』というジレンマを抱えていたが、それがあるべき姿に変わってきた」と話します。
同社が行う在宅治験は今のところ、希少疾患や新型コロナウイルス感染症など、医療機関に直接足を運びにくい患者を対象としたものが中心。海外のベンダーとも連携し、グローバルで計画されるDCTを日本で実施するための受け皿となるべく、取り組みを強化しています。DCTは海外が先行しているため、3Hクリニカルトライアルへの依頼者の多くも外資メーカーですが、今年に入って内資メーカーにも動きが出てきているようです。
同社がDCTに力を入れるのは、導入の遅れがドラッグ・ラグにつながるのではないかと危惧しているからです。今や日本で行われる臨床試験の8割以上が国際共同治験となっており、DCTに対応できなければグローバル治験から日本が外されてしまいかねないといいます。
医療機関でもDCT専門チームが
東京センタークリニックの長嶋浩貴院長も、同じ危機感を抱いています。
新型コロナの感染拡大を契機に、同院では独立したDCTチームを立ち上げ、クリニックでの一般診療を続けながらDCTを実施できる体制を整えました。チームは「3カ月に1回の訪問を2年間、といった試験であれば、疾患の領域にもよるが、100人の被験者を担当できる」(同氏)ほどの規模で、昨年、非常勤スタッフのコロナ感染によってクリニックの一時閉鎖を余儀なくされる中、治験をやり切った経験がもとになっています。その際は、電話診療やCRCによる治験薬の配送で対応したといい、長嶋氏は「コロナ禍で強制的にDCTに組み込まれたことで、他の医師やCRCの意識も変わった」と話します。
チームを作るため、同院では据え置き型の電子カルテをクラウドシステムに変更し、非常勤の分担医師や訪問看護師、クリニック独自のCRCと契約。5人の糖尿病患者を対象に、来院と訪問看護、オンライン診療を組み合わせた非介入臨床研究を行い、ハイブリッドDCTでチームが機能することを確かめました。実施医療機関側の手間やコストは増しますが、患者の利便性やアクセス、安全性の確保につながることは間違いなく、治験期間の短縮につながることが期待されます。
訪問看護師のトレーニングが必要
DCTでは、採血や心電図といった簡単な検査を実施するにあたり、実施医療機関による訪問診療や、訪問看護のほか、近隣医療機関(サテライト医療機関)が活用されます。デジタルデバイスを活用すれば、オンラインでの訪問も可能です。
課題となるのが、訪問看護師に対する教育や啓発です。3Hメディソリューションは今月、訪問看護事業を手掛けるケアプロと連携し、在宅治験に携わる訪問看護師のトレーニングやマッチングの支援を開始。将来的に全国の訪問看護ステーションが在宅治験を行える仕組みの構築を目指しています。
2030年には治験の30%をハイブリッドDCTでカバー可能
日本製薬工業協会の医薬品評価委員会が今年まとめた「日本での導入の手引き」では、「DCTは従来の臨床試験と二律背反の関係ではない」「DCT導入は目的でなく手段である」とされており、長嶋氏も、DCTと従来の治験を組み合わせたハイブリッド型が合理的だと話します。医療機関のDCT専門チームや訪問看護、訪問CRCといったインフラの整備が進めば、2025年には国内で行われる治験の10%を、30年には30%をハイブリッドDCTでカバーすることも可能ではないかと長嶋氏はみています。
DCTではデジタルデバイスやウェアラブルデバイスの活用も肝になりますが、長嶋氏が行った糖尿病患者を対象とした臨床研究では、一部の高齢患者でデジタル検査をうまく実施できなかったといいます。一方、「フィットビット」や「アクチグラフ」といったウェアラブルデバイスは全ての患者で問題なく使用できたといい、活用が期待されます。
このほか、研究機関側からの検討も進んでおり、たとえば今年8月には、聖マリアンナ医科大とMICINが戦略的包括協定を締結。すでに聖マリでMICINのDCT支援システムの活用が進んでいます。治験のコストを押し上げているデータの入力・点検業務についても、国立がん研究センター東病院がファイザー、NTTデータと共同研究を開始。NTTのソフトウェアを使い、電子カルテのデータを治験報告用データとしてファイザーのEDC(臨床データ収集システム)に登録する手法を開発し、年末をめどに運用の課題を抽出する研究を進めています。
「2021年はDCT元年になるのではないかと思っています」。3Hクリニカルトライアルの滝澤代表は、ITドリブンではない、患者体験を基本としたDCTがこれからさらに進むのではないかと見通します。多様なプレイヤーが一体となり、日本の環境に合ったDCTを作っていくこととなりそうです。
あわせて読みたい
オススメの記事
-

キッセイ、米社から甲状腺眼症治療薬を導入/参天、緑内障・高眼圧症薬ネタルスジルメシル酸塩を申請 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年7月30日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り