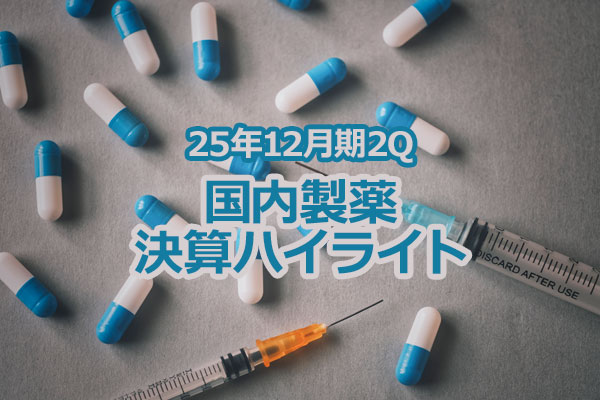製薬業界のプレイヤーとして存在感を高めるベンチャー。注目ベンチャーの経営者を訪ね、創業のきっかけや事業にかける想い、今後の展望などを語ってもらいます。
| 原田雅充(はらた・まさみつ)1972年生まれ。98年、岐阜大大学院生物資源利用学(遺伝子工学専攻)卒。旧通産省工業技術院生命工学工業技術研究所に出向し、血管の老化研究で農学修士を取得。日本化薬、アムジェンを経て、2007年にセルジーン(現ブリストル・マイヤーズスクイブ)入社。臨床開発統括部長を務めた。14年にMBAを取得し、翌年からシンバイオ製薬で営業・マーケティング本部長を担当。17年、ヒューマンライフコードを設立した。 |
廃棄されるへその緒を活用
――へその緒(臍帯)由来の間葉系幹細胞(MSC)を使った細胞医薬の開発を進めています。臍帯由来の細胞の特徴を教えて下さい。
特徴としてはまず、胎児の細胞であるため、増殖能が高い。骨髄や脂肪由来のMSCに比べても若く、より短期間でスケールアップできます。それから、MSCは炎症部位に集積し、サイトカインストームを沈静化する性質を持っていますが、臍帯由来MSCは集積性が極めて高いのも特徴です。
3つ目の特徴は、免疫原性が低いこと。免疫原性の低さはMSCに共通した特徴ではありますが、骨髄由来MSCだと炎症環境下で免疫原性が少し上がってしまう一方、臍帯由来MSCはそうした環境でも免疫原性を抑えることができ、拒絶反応のリスクが低いと期待されています。
4つ目は、完全無血清で培養可能であること。これにより、細胞が未知の細菌やウイルスに感染するリスクを最小限に抑えることができます。
一方、臍帯そのものにフォーカスすると、▽ドナー(母子)に対して無侵襲で採取できる▽廃棄物を医療資源として有効活用できる▽凍結保存で臍帯ごとに半永久的に備蓄できる――という特徴があります。産業として考えれば、国内で原材料を確保できることと、必要な時に必要な量を製造できることは非常に大きな利点です。
――コスト面はどうでしょうか。
具体的にいくらになるかは、今後のスケールアップを含めて考えなければならないのでお伝えできません。ただ、廃棄物を利用するため、製造原価を低く抑えることは可能です。
現在販売されている骨髄由来の細胞医薬は原価が7割と公表されていますが、業界として「原価4割を超えたら手を出すな」と言われる状況で製造を続けていくのは厳しい。臍帯は原価率でいうと半分以下に抑えられますし、今後供給量が増えれば単価は下がっていきます。ほかの細胞医薬より持続可能なビジネスとして展開していけるのではないかと考えています。
さらに言うと骨髄は100%輸入に頼っていますが、パンデミックで骨髄そのものの単価も上がっている。一方、臍帯は東京大医科学研究所との連携により、国内で安定的に調達できています。新型コロナウイルスワクチンを各国で取り合っている現状を鑑みても、国産のものを作らなければ必要な人にタイムリーに届けることはできない。それは細胞医療も同じです。
「第3のパイプライン」で24年の実用化目指す
――へその緒由来のMSCについて、現在、急性移植片対宿主病(GVHD)と新型コロナウイルス感染症の急性呼吸窮迫症候群(ARDS)で開発を行っています。
白血病患者を主体とする急性GVHDでは、すでに臨床第1相(P1)試験が完了しており、ピボタル試験を計画中です。ARDSはP1試験が進行中で、そろそろ終わりが見えてきているところです。安全性の問題は今のところ認められていませんので、次の試験デザインについて当局と話し合いを進めています。
――ARDSに対する次の試験の目標時期は。
進行中の P1試験では有効性のシグナルを確認していますが、まずは、それが本当にMSCの効果かどうかを客観的に判断できるバイオマーカーの特定が必要だと考えています。そのため、探索的な評価項目として免疫細胞や血中のサイトカイン濃度などを調べていて、そのデータをしっかり解析した上で次の試験に進むつもりです。
新たな治療選択肢が望まれているところではありますが、拙速に進めることはせず、P1試験の症例ひとつひとつをしっかり吟味したい。MSCの免疫抑制効果や炎症抑制効果を評価できる項目が特定できれば、比較試験を行う必要もなくなるかもしれませんしね。
仮にパンデミックが収束したとしても、ARDSを対象とした開発は継続するつもりです。新たな感染症が発生すれば、それに伴う過剰炎症や臓器障害が起こりうる。今回のデータは、将来のリスクマネジメントの観点からも重要だろうと考えています。
――これらのパイプラインに続く展開としては、どのようなものを考えていますか。
現在、ある難病の患者さんを対象に、3つ目の開発プロジェクトを計画しています。GVHDでのエビデンスと、ARDSで認められた急性炎症下での修復効果をかけ合わせ、年末から来年初頭にかけて実行に移していきたい。実は、医薬品として最初に承認を受けるのはこのパイプラインだろうと考えていて、2024年の中ごろの承認を目指しています。
われわれがまず考えているのは、現在ステロイドが中心的に使われている炎症性疾患。ステロイドは安価で、医師も使い慣れているので、これからも標準治療として使われ続けると思いますが、骨格筋障害や腎機能障害などの副作用があります。一方で、われわれのMSCは、そうした副作用は限りなくゼロに近い。ステロイドだけでコントロールできない疾患を対象に開発しており、GVHDの適応でもステロイド難治の患者にフォーカスしています。
特定の難病患者さんで実用化したあとは、難病での垂直展開と慢性炎症への水平展開を考えています。慢性炎症が継続して筋肉が年齢以上に衰えるサルコペニアや、遺伝的な要因で老化が異常に速く進む早老症などが対象です。
直面した法と技術の壁
――へその緒からどうやって製品を作るのですか。
まず、帝王切開で生まれた赤ちゃんからもらった臍帯を、東大医科研が開発した特殊な凍結保護液に浸し、同研究所で保管します。帝王切開に限定しているのは、自然分娩では産道を通るときに細菌やウイルスに暴露するリスクがあるからです。臍帯の収集先としては、現在、東大医科研を通じて都内の2つの産科病院と提携しています。
保管している臍帯は、使用前のスクリーニングをパスしたものを臨床用として活用します。臍帯10本あれば、合格するのはだいたい9本。合格した臍帯から、製品のタネとなる「マスター細胞」を作り、継代培養で3000~5000倍に増やして最終的なプロダクトセルを作製します。治験では、完成した細胞を輸血バッグに詰め、点滴静注で患者に投与しています。
――この方法を確立するまでに、どんな課題がありましたか。
1つが法的な壁です。臍帯はかつて、都の「胞衣条例」で産業利用が禁止されていました。臍帯由来MSCの実用化には、条例を変えることが不可欠でした。
2017年の創業当時、ヒューマンライフコードには私しかいませんでしたから、私と東大医科研で都政に働きかけ、ロビー活動を繰り返し、2年半後の19年9月にようやく条例の規制を緩和するとの通知を勝ち取りました。これにより、廃棄物だった臍帯を医療資源として活用できる枠組みが整い、産業化に向けた大きな一歩を踏み出しました。
技術面では、ほかの多くの細胞医薬と同様に、スケールアップの壁がありました。われわれの場合、東大医科研の長村登紀子准教授が18年5月に製造法を確立し、それをライセンスインすることで壁を突破することができました。現在は1本のへその緒から1000回投与分の製剤を作ることができるようになっています。
ただ、今後の適応拡大に耐えうる製造キャパシティを確保するには、さらに2倍、3倍、10倍と増やしていく必要がありますので、その技術革新も並行して進めています。
――商業生産に向けての課題は。
まず、臍帯を必要なだけ集められる体制を構築するために、提携する産科病院の数を増やしていかなければならないと考えています。医薬品化に向けて、来年にはそうしたインフラ整備を始めたいです。
これから症例数を増やしていくことを考えると、製造所のキャパシティを増やし、トレーニングされたスタッフを確保していくことも課題です。そのために、東大医科研内に製造業の許可が取得可能な細胞製造所の整備を進めています。医科研と連携し、マスター細胞を供給する製造体制の構築を目指します。
われわれは、実用化を見込む2024年までの7年間を創業期と考えています。今はちょうどその折り返し地点。ここからは第二の創業期ととらえ、▽研究開発▽サプライチェーンマネジメント▽信頼性保証▽事業開発▽コーポレート――という新体制の構築を急いでいます。三役の配置を含め、商業生産に向けた人材の獲得も課題です。
きっかけは米国で出会った小児患者
――細胞治療を事業にしたいと考えたきっかけを教えてください。
もともと学生の頃から細胞を扱っていて、研究のキャリアがありました。明確に細胞治療を意識したのは3社目のセルジーンにいたころです。臨床開発統括部長として日本と米国を頻繁に行き来する中で、米国の本社で胎盤を使った細胞療法に出会いました。
そのとき、治療を受けた患者さんは当時5歳。先天性の遺伝性疾患だったんですが、体力がかなり落ちていて、強力な化学療法に耐えられず、唯一の治療法である骨髄移植を行うことができなかった。ところが、その患者さんに胎盤由来のMSCを投与したところ、体力が回復して骨髄移植を実施できたんです。その後、患者さんは完全寛解に至り、巨頭症でかぶれなくなっていた大好きな野球帽をかぶれるまでになりました。
それまでも、抗がん剤の開発に関わる中で、体が弱くて薬剤の使用に耐えられない小児・高齢者や、使用したとしても副作用に苦しむ患者さんを目の当たりにしていましたから、副作用の少ない細胞治療は新たな選択肢になると考えました。さらに、廃棄物を活用するのでビジネスの入り口で勝っていると直感した。そこで、セルジーンで社内ベンチャーの立ち上げを提案したのですが、統括部長という立場もあり却下されてしまいました。
ただ、その思いをどうしても忘れることができなかったんです。「だったら独立して、ビジネスにしよう」と思い立ち、会社を辞めてニューヨークに渡って1年間ビジネスを学びました。頭の中には常に事業計画のことがありましたから、学びながら計画を練っていたといった方がよいかもしれません。そうして、ヒューマンライフコードを設立しました。
――開発から製造まで連携する東大医科研とも以前からの縁だとか。
東大医科研には、第二新卒として入ったアムジェンにいた頃、2000年から4年間お世話になりました。当時は血液がん領域のパイプラインが主軸だったので、血液腫瘍の教室に飛び込み、難治性白血病の研究を行いました。
4年間で血液腫瘍のドクターと対等に話せるくらいに専門性を高めることができたのは非常に大きかったですね。医科研として10年ぶりに米国血液学会の口頭発表に採択されて、「サラリーマン研究員が通っちゃったよ!」と(笑)。いろんな先生方に支えられて大きな成果を得ることができました。このときの実績と信頼があったからこそ、11年ぶりに門を叩いて「臍帯由来の細胞を開発させてください」とお願いした時、「原田が言うなら」と認めていただけた。当時はそんなことは考えてもいませんでしたが、今思えば不思議な縁ですね。
「日本で生まれたノウハウを世界に」
――東京を中心に“地産地消”のモデルを構築していますが、東京以外でのインフラ整備やグローバル展開は考えていますか。
日本では、東京を拠点にします。日本でわれわれが対象とする疾患に対しては、東京で提携する産科病院をもう少し増やせば安定的な供給が可能になると考えています。
米国でも地産地消のインフラ構築を目指しています。すでにある企業と基本合意し、契約に向けて話を進めているところです。実現すれば、米国でも東大医科研で構築した製造ノウハウを使って、同一の品質で作れることになります。
このとき、日米連携のキーワードとなるのが「標準化」です。細胞医薬では、製造方法に規格がなく、医薬品では当たり前の「日米欧の共同治験」がなかなかできません。だからこそ、米FDA(食品医薬品局)と日本のPMDA(医薬品医療機器総合機構)の両方が認める標準化プロセスを確立できれば、共同治験も可能となり、その後のグローバル展開がぐんと楽になる。なので、まずは日本と米国に焦点を当てています。日米で足元を固めたあとは、主にアジアでの展開を考えています。
――上場の見通しを含め、今後の展望は。
IPOは、安定的な資金を獲得する手段の1つとしてもちろん視野に入れています。ただ、やみくもに上場を急ぐことは考えていません。上場のタイミングは、実用化のタイミングとほぼイコールになるのではないかと思っています。
われわれの1番のミッションは、一日でも早く臍帯由来の細胞医薬を実用化すること。それを成し遂げた暁には、パブリックに認められる会社になると思いますので、まずは医薬品化にすべての思いとエネルギーを注いでいきたいです。
日本で生まれたノウハウが世界標準となり、捨てられていたへその緒が世界中で有効活用される世界は、実現不可能ではありません。やれるチャンスがあるなら、やるしかないと思っています。米国のパートナーも含め、賛同してくれる方がいますから、臍帯由来細胞医療のパイオニアとしてリスクをとって先導していきたいです。
(聞き手・亀田真由、写真はヒューマンライフコード提供)