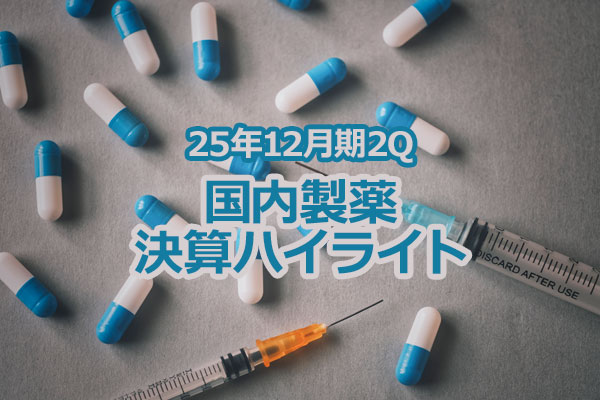新型コロナウイルスの拡大で一気に加速すると言われているデジタルトランスフォーメーション(DX)。テレワークが進み、デジタルチャネルを通じた営業活動が広がるなど、デジタル化が遅れていると言われる製薬業界にも変化が見え始めました。製薬業界では今、DXに対してどのような動きがあり、その先にはどんな世界が待っているのか。デロイト トーマツ コンサルティングのコンサルタントと議論します。(連載の全記事はこちら)
急速に低下する研究開発生産性
前田雄樹(AnswersNews編集長):研究の分野でホットなDXのトピックスといえば、やはりAI創薬でしょうか。
松原大佑(デロイト トーマツ コンサルティング・マネジャー):昨今、非常に熱が高まっていますね。その背景にあるのは、製薬企業の研究開発の生産性の低下です。弊社グローバルチームの調査によれば、グローバル大手製薬企業の研究開発生産性は2010年から右肩下がりに落ちていて、この10年ほどで5分の1の水準まで低下しています。
世間的には、「ムーアの法則(Moore’s law)」を逆から読んで「イールームの法則(Eroom’s law)」と言われたりもしますが、創薬にかかるコストはこの20年間で非常に高騰している。製薬企業にとっては、コストをいかに下げ、着想から上市までの期間を短縮できるかが重要で、AIを使った創薬アプローチに各社が期待を寄せているのもこのためです。

増井慶太(デロイト トーマツ コンサルティング・執行役員):医薬品以外のビジネスも広がりつつありますが、やはり製薬企業なので、本丸である医薬品開発の生産性を改善することは非常に重要です。データやデジタルを使って開発の成功確率を高め、コストを下げていくことは、どの会社も希望しているところかと思います。
松原:実際に取り組んでいるかは別として、AI創薬を検討していない製薬企業は皆無なのではないかと思います。やはり外資系企業の動きが早いですが、内資でも大手だけでなく、中規模の企業もAIスタートアップと協業しているという話を耳にすることが多くなっています。
データの増加が後押し
前田:使えるデータが増えてきていることも、AI創薬の実現性を高めていますね。
松原:次世代シーケンサーが普及したことによって、遺伝子情報の取得コストはこの10年ほどの間で著しく低下しました。また、タンパク質の構造解析の分野では、クライオ電子顕微鏡による解析の精度も格段に上がっており、非常に早いペースで構造データの蓄積が進んでいます。いずれも、創薬を行う上で非常に重要なカギとなる情報ですので、これらのデータベースが拡充されてきていることが、AIやインシリコでの創薬を後押ししています。
こうしたミクロな対象のデータだけではなく、生体データのようなマクロな対象のデータも、いずれは創薬に還元されるのではないかと思っています。どう取り入れるのかというのはまだ未来形ですが、将来的には生体データをフェノタイプとして使いながら、遺伝子やタンパク質といった分子データと組み合わせて解析してくことが可能になってくるのではないでしょうか。
見えてきた成果
前田:AI創薬と一口に言っても、アプローチはさまざまです。
松原:やはり、本丸である創薬標的の探索や化合物・抗体等の設計・最適化、活性や毒性の予測・評価というところが最も注目されるテーマで、事例も蓄積されてきています。それ以外では、合成経路探索の精度も上がっていますし、画像や動画などアッセイデータの解析はすでに一般的になっていると思います。患者の層別化やバイオマーカーの探索に使われるケースもありますし、臨床試験の成功確率を予測する試みも出てきています。周辺領域では、アンメットニーズや関連特許の調査をAIで効率化するというものもあります。

増井:層別化やバイオマーカーの探索は、オンコロジー領域で進んでいますが、ほかの疾患でもドラッグ・リポジショニングと組み合わせて進んでいくのではないかと思っています。
90分で探索完了→9カ月で使用許可
前田:昨年1月、大日本住友製薬が英Exscientiaと共同でAIを使って創製した化合物の臨床試験を始めたと発表し、話題となりました。成果が出始めていますね。
松原:AIにより創出された新薬が承認・発売に至るのはまだ先だと思いますが、臨床試験に入るものは少しずつ出てきています。
大日本住友とExscientiaのケースは、通常4~5年かかると言われている探索研究を1年未満で終わらせたという点で、非常に画期的なことだと思っています。リード化合物を得るためには多くの候補化合物を合成して評価しますが、大日本住友とExscientiaの場合は、AIを用いることで、実際に合成・評価する候補の数を通常の7分の1程度に絞り込めたことが、大幅に期間を短縮できた要因です。
もう1つご紹介したい事例が、英BenevolentAIのドラッグ・リポジショニングによる新型コロナウイルス感染症治療薬の探索です。同社がAIを用いて論文などの情報から構築したナレッジグラフをもとに探索を行ったところ、わずか90分の計算時間でバリシチニブを潜在的なコロナ治療薬候補として特定し、昨年2月4日のランセット誌で報告しています。その後、臨床試験でレムデシビルとの併用による効果が確かめられ、11月19日付で米FDA(食品医薬品局)から緊急使用許可を得ています。探索開始から9カ月という前例のないスピードで当局から使用を認められました。
増井:9カ月というのはアイオープニングですよね。AI創薬はリポジショニングから進んでいくのかもしれません。適応拡大の一種と捉えられてしまうとあまり旨みがないとか、他社の化合物だと販売しづらいといった難しさがかつては言われていましたが、新型コロナウイルスの影響でスピーディーな医薬品開発の必要性が高まる中、あらためて着目されています。
松原:アメリカのLantern Pharmaのビジネスモデルも面白いですよ。他社が臨床試験に失敗したオンコロジー領域のパイプラインを買ってきて、AIで同定したバイオマーカーで患者を絞り込み、成功確率を高めようということをやっています。自分たちでは最後まで開発を行わずに、POCが取れたらまた他社に売ってしまう。詳しくは明らかになっていないですが、実際にイグジットに成功した実績もあるようです。これをわずか数人の体制でやっているということなので、非常に効率がいい。
ここまでは低分子化合物の話が中心でしたが、抗体医薬やペプチド医薬品でも配列を最適化するためにAIを使おうというアプローチが出てきています。国内だとMolcureがすごく先進的なアプローチを実践しており、注目しています。
増井:彼らはウェット・イン・ザ・ループと呼んでいますが、アルゴリズムを提供するだけでなく、実際にラボ環境を持っていて、プロセスをどんどん回していくことでアルゴリズムもバージョンアップしていくんですよね。技術進化モデルとしても面白いなと思って見ています。
AIが起こすイノベーション
松原:ウェット・イン・ザ・ループのような創薬アプローチは、将来、破壊的なイノベーションを起こすのではないかと見ています。
研究のプロセスでは、実験をしてデータを取り、そこから示唆を抽出して、分子エンジニアリングの改良や次の実験のデザインをする、ということを回していくわけですが、AIを中心に置いて一連の流れを全部機械化できると、勝手に実験が行われ、どんどんデータが蓄積されて学習が進み、より精度の高いAIができていく。
それにより、これまでのウェット実験では見つけられなかったものが見つかったり、ものすごく時間がかかっていたものが一瞬で答えにたどり着けたりするようになります。AIを中心に研究プロセスを設計する企業が、製薬企業や従来のバイオテック企業に取って代わり、医薬品の創出源になることもあり得るなと思っています。
製薬企業もこうした世界観を見ていないわけではないと思いますが、既存の研究プロセスが大きすぎるため、どこからデジタル化に手をつけるべきかの検討が煩雑になりやすく、大規模なデジタル化となれば実装にも時間がかかります。その間に、コアなところだけスモールスケールで最適化した新しいプレイヤーがどんどん結果を出していくようなことになれば、いよいよ破壊的イノベーションが現実味を帯びてきます。AI創薬のような革新的なプロセスをどのように取り込んでいくかというのは、新しい経営テーマだと思います。

増井:研究は、デジタル投資がなかなか及びづらい分野だと感じています。それは、短期的に成果が見えづらいというのもあるんですが、デジタル投資を控え目にやっていると、スタートアップにさらわれる可能性がありますね。
松原:パイプラインが出ずに苦しんでいる国内の中小製薬は、新しいプレイヤーに打ち負かされてしまうのではないかという危惧はあります。
最もDXを考えなければならない領域
前田:そうすると、中小こそこういうアプローチをとるべきだということでしょうか。
増井:モノが出にくいのは明らかなので、こちらにシフトしてもいいのではないでしょうか。グローバルファーマと同じような戦い方をしても勝てないので、アプローチ自体を抜本的に変えてしまうという考え方もあると思います。ただ、そうなると、これまでとはまったく違う組織ケイパビリティが必要になってくるので、組織自体のトランスフォーメーションが求められるし、それだけの意思決定ができる経営者が必要になります。
松原:トップレベルの意思決定は絶対に必要です。研究現場は、AIで自分たちの研究をどう補うかという視点にとどまり、既存のプロセスを白紙にして考えるのは難しい印象です。より高い視点から、今後の競争力の源泉をどこに設定するのか、という見方がなければ難しいと思いますね。
増井:製薬企業の一番の価値の創出源は研究なので、研究に最も投資をしなければならないと思うんです。最もDXを考えなければならない領域だし、最も経営判断の思考を割くべき領域で、最もノベーションを模索しなければいけない領域だと考えています。
松原:従来の戦略やプロセスに縛られない特区のようなものをつくって、「こういう発想でAIを起点に創薬プロセスを組んだらどうなるんだろう」といった投資が必要なんだと思います。「第二R&D」と言ってもいいかもしれません。AIスタートアップと提携して、アルゴリズムで何かを見つけてきてもらうといった共同研究をやっていても、すべてを機械化してしまうような、本当の意味でのトランスフォーメーションを実現することは永遠に無理なのではないでしょうか。

増井 慶太(ますい・けいた)=写真左。デロイト トーマツ コンサルティング合同会社執行役員/パートナー。米系戦略コンサルティングファーム、独系製薬企業(経営企画)を経て現職。「イノベーション」をキーワードに、事業ポートフォリオ/新規事業開発/研究開発/製造/M&A/営業/マーケティングなど、バリューチェーンを通貫して戦略立案から実行まで支援。東京大教養学部基礎科学科卒業。 松原 大佑(まつばら・だいすけ)=写真右。デロイト トーマツ コンサルティング合同会社マネジャー。京都大理学部卒業後、同大大学院生命科学研究科で博士号を取得し、アカデミアで研究に従事。現職ではR&D領域のテーマに数多く携わり、AI/ML/DLの活用を含むデジタルトランスフォーメーションに関する取り組みにも幅広い知見を有する。 |
【AnswersNews編集部が製薬企業をレポート】
・大日本住友製薬