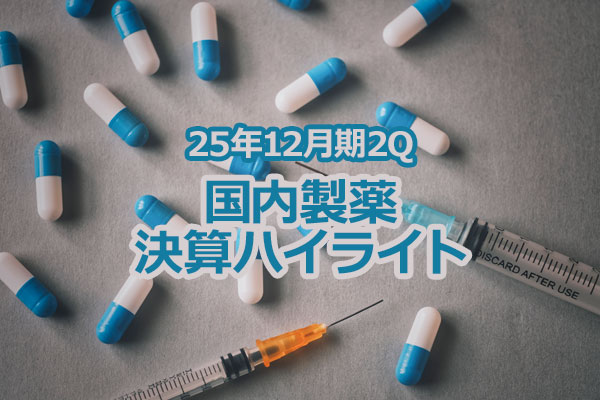新型コロナウイルス感染症で関心が高まっている「バーチャル臨床試験」。国内では、訪問診療や訪問看護などを活用して遠隔で臨床試験を実施した例はあるものの、バーチャル化のハードルは依然として高いのが実情です。そうした中、日本製薬工業協会が今年9月、実現に向けた課題などをまとめた報告書を公表。オンライン診療ベンダーがCROと組んでシステムを開発するなど、動きが活発化しています。
アンケートで見えた課題
日本製薬工業協会(製薬協)の医薬品評価委員会臨床評価部会は今年9月、製薬企業や受託企業などに昨年行ったアンケート調査などをもとに、バーチャル治験などを含む来院に依存しない「分散型臨床試験(DCT)」の導入に向けた課題などを検討した報告書を公表しました。
ひとくちに「来院に依存しない」といっても、被験者がまったく来院しない「フルバーチャル」から、バーチャルとの組み合わせによって来院回数を減らす「ハイブリッド型」まで、そのあり方は様々。実施する上では、オンライン診療やデジタルデバイスの利用に加え、GCPなどの規制の順守、被験者の安全確保、データの質の担保など重要となるポイントも多岐にわたります。

DCTによって期待されることの1つに、医療機関との距離や身体の状態によって通院の負担が重い患者にも治験へのアクセスを拡大できることがあります。オンライン診療や訪問看護を活用し、自宅に治験薬を配送することができれば、患者は通院せずとも治験に参加できるようになります。
「診療」「臨床検査」「治験薬配送」などの課題
製薬協の報告書によると、神経疾患や皮膚疾患の治験で訪問診療が活用された例や、神経疾患や希少疾患の治験で訪問看護による臨床検査が行われた例がある一方、アンケート調査の時点ではオンライン診療の活用例はありませんでした。法規制やインフラ整備への投資など、製薬企業側の事情が導入へのハードルとなっています。

訪問看護の活用にも、育成という壁があります。訪問看護は、被験者の安心感やエンゲージメント向上への好影響が期待され、サービスプロバイダーに業務を委託するモデルが検討されていますが、看護師へのGCPに関するトレーニングが必須。一方で、看護師資格を持つ治験コーディネーター(CRC)がすぐに訪問看護を始めることも規制上できないため、いずれにせよプロバイダーでの育成が必要です。そのため、初期投資が高額となることが予想されます。
治験薬や関連資材の配送については、現行の規制では実施医療機関の責任下で行うのが原則。海外では製薬企業(治験依頼者)から直接配送を行ったケースがあり、国内でも医療機関スタッフの同席のもとメーカーからの直接配送が行われた例もあります。報告書では、完全なDCT導入に向けては、医療機関を介さない配送の検討も必要になると指摘しています。

一方、治験実施中のデータ収集については、治験の原データとしてePRO(電子患者報告)やウェアラブルデバイスがすでに使われています。現在は補助的な使用に限定されていますが、海外を中心に既存の主要評価項目、副次評価項目を遠隔で測定する試みが増加。こうした指標の実現には、指標の信頼性・妥当性を疾患領域の専門家やツールの開発企業と検討することが欠かせません。報告書では、医薬品の開発の早期段階から検討を開始するべきだと提案されています。
オンライン診療ベンダーやCROが取り組み
課題が多く分散化への動きが鈍かった日本でも、徐々にではありますが、取り組みが進んできている部分もあります。2019年には、国内最大のオンライン観察研究「トライアルレディコホート構築研究」が開始。認知機能検査を使って登録者の認知機能の経過を観察し、必要であればアルツハイマー病予防薬の臨床試験への参加を促す研究で、東京大などが進めています。
オンライン診療システム「curon(クロン)」を手掛けるMICIN(マイシン)は、シミックと共同でバーチャル臨床試験システム「MiROHA(ミロハ)オンライン診療」を開発。同システムはMICINのオンライン診療サービスに、臨床試験でのデータ収集を行うeSource機能を搭載したもの。医師はビデオ通話で患者を診察しながらデータをシステムに直接記入でき、EDC(治験データを電子的に収集・管理するシステム)と自動で連携します。データ転記作業やCRAの訪問回数の削減などが見込めるとして今年4月から提供が始まりました。

7月には、MICINと3Hグループ、東京センタークリニックの3者で、対面と遠隔の診療を組み合わせたハイブリッド型バーチャル臨床研究を開始。2型糖尿病患者の体調や状態変化を観察する臨床研究で、治験でのデジタルツールの利活用について、有用性や実施可能性、導入の課題を明らかにするのが目的です。ウェアラブルデバイスのほか、MICINはMiROHA、3HグループはePRO「3H P ガーディアン」を提供。3Hは、被験者のリクルートメントやCRCの派遣も行います。
9月にも、イーピーエス(EPS)とMICINがバーチャル治験の普及に向け業務提携。EPSは被験者とCRAの両方が施設を訪問しなくてよい臨床試験を念頭に、eCOA(電子臨床アウトカム評価)やeConsent(電子的同意取得)、訪問介護などトータルスキームをデザインする「Virtual GO」構想を推進しています。両社は今後、管理システムの開発を検討するほか、運用・レギュレーション上の課題解決に向けた提案などを行うとしています。
導入事例の積み重ねが必要
海外では、遠隔臨床試験を専門とする米サイエンス37や英eClinicalHealth、包括的ヘルスケアサービスを手掛ける米メディデータや同ベリリー・ライフサイエンスなどがDCTサービスを展開。最近では、開発受託機関の同IQVIAや同パレクセルも参入しており、たとえば、英アストラゼネカの新型コロナウイルスワクチンの開発は、IQVIAの協力のもとDCTが活用されているといいます。
米国では医薬品やサプリメントなどで2019年9月までに14のDCTが行われていて、被験者からの反応も概ね肯定的。産官学での議論も活発化しており、16年10月~17年1月には、米デューク大と米FDA(食品医薬品局)主導で、製薬企業やバイオテクノロジー企業にインタビューが行われました。
欧州でも、昨年にDCT実現に向けた官民連携組織「Trial@Home」が立ち上がり、仏サノフィとユトレヒト大学医療センター(オランダ)を調整役として議論が進行中。製薬企業からは、武田薬品工業やスイス・ノバルティス、アストラゼネカなどが参画しています。
製薬協の報告書では、「DCT手法の導入事例を増やし、製薬企業だけでなく、臨床試験に関わる各ステークホルダーの経験を蓄積すること」を提案。事例を積み重ねることで、DCTとの親和性の高い領域や課題が明確になると記しています。一部の企業では、治験計画を患者にレビューしてもらうケースもあり、ePROの入力方法など課題を洗い出すことができたといいます。PMDAやヘルスケア産業など、様々なステークホルダーを巻き込んだ議論が進めば、実現に近づくでしょう。
(亀田真由)
AnswersNews編集部が製薬企業をレポート