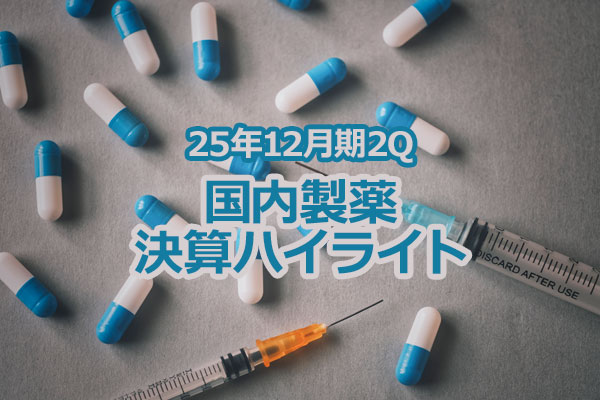ゲームの要素をゲーム以外のサービスやシステムに応用する「ゲーミフィケーション」。これを活用して新たなデジタルヘルスケアソリューションを生み出そうと、アステラス製薬が横浜市立大、東京芸術大と産学連携の枠組み「Health Mock Lab.」を発足させました。ゲーミフィケーションによってヘルスケアはどう変わるのでしょうか。
ゲーミフィケーションとは何か
「ヘルスケアには『頭ではわかっているのに始められない』『思い切って始めてみたものの続かない』といった障壁がある。ゲームの要素を織り込むことで、行動変容や継続といった障壁を乗り越えられるのではないか」
10月2日、アステラス製薬と横浜市立大、東京芸術大が東京・六本木で開いた「Healthcare×Gamification Forum~ゲームによるヘルスケアの進化~」と題するイベント。その冒頭、アステラスの岡村直樹副社長(経営戦略担当)は、同社がゲーミフィケーションの活用に注目する理由をこう語りました。
ゲーミフィケーションとは、ゲームの要素をゲーム以外のサービスやシステムに応用し、利用者のモチベーションや満足度を向上させる手法のこと。アステラスと横浜市大、東京芸大は今年8月、バーチャルな産学連携の枠組み「Health Mock Lab.」を発足。ビジネス、医学、ゲーミフィケーションの視点を持ち寄り、新たなデジタルヘルスケアソリューションの創出・実用化に取り組んでいます。
熱中できる場を作り出すことに意味
ゲーミフィケーションの活用事例としては、ゲームをクリアする感覚で学習を進められる子ども向け教材などが挙げられますが、ヘルスケア分野でも近年、ゲームの要素を取り入れて社会的課題を解決するサービスが注目を集めています。
例えば、米アキリ・インタラクティブ・ラブズはADHD(注意欠陥・多動性障害)を治療するゲームアプリを開発。臨床試験で有効性が示され、現在、米FDA(食品医薬品局)に承認申請中です。日本では、今年3月に同社とライセンス契約を結んだ塩野義製薬が開発を進めています。
ゲーミフィケーションはあくまで、ゲームの要素を取り込むことであり、ゲーム化を意味するものではありません。東京芸大大学院映像研究科の桐山孝司教授は「点数を競うとか、ゴールが明確にあるとかではなく、ハードルを越えるためのデバイスを持つことで、やることが楽しくなるとか、もっとやりたくなるとか、そういうもので十分いい。それが継続性につながり、いつの間にか成果になる」と強調。「体験したり、熱中したりできる場を作り出すことがゲーミフィケーションの大きな意味。医療応用では、リハビリやトレーニングに出番がある」と話します。

東京芸大が制作した、声の大きさをコントロールしながらリンゴを転がしていくゲーム
ゲーミフィケーションで何をするか
アステラスは2018~20年の中期経営計画で、3つの戦略目標のうちの1つに「Rx+プログラムへの挑戦」を掲げています。医療用医薬品ビジネスの経験に異分野の技術を融合させることで、新たな製品・サービスを生み出すことを目指しており、横浜市大、東京芸大との連携もこの取り組みの一貫です。

ここ数年、デジタルヘルスがバズワード化し、多くのヘルスケアアプリが登場していますが、アステラス製薬Rx+創成部の金山基浩ビジネスプロデューサーは「ヘルスケアアプリは継続性が課題だ」と指摘。「継続性を高めることに非常に大きなアンメットニーズがあるし、私たちにとってはそこがバリューを上げることにつながる」と言います。
心理的な壁をゲーミフィケーションで解決
アステラスはRx+の取り組みの1つとして、バンダイナムコエンターテインメントと共同で運動支援アプリを開発中。生活習慣病予備軍など継続的な運動が必要な人を対象に、科学的根拠のある運動プログラムを、ゲーム性を取り入れることで継続しやすい形で提供することを目指しています。金山氏は、運動継続には「心理的な壁」(モチベーション/抵抗感/煩わしさ/諦め)と「実行の壁」(身体機能/知識不足/準備不足/周辺環境)があると言い、「ゲーミフィケーションによって心理的な壁を、エクササイズの進化によって実行の壁を解決したい」と話します。
もう1つ、ゲーミフィケーションの活用で期待されるのが無関心層の取り込みです。金山氏は、大ヒットゲーム「ポケモンGO」を例に挙げ、「ゲーミフィケーションであればヘルスケアに無関心な層にもリーチが可能になるのではないか。しかも、そこで使われる製品が科学的根拠に立脚したものであれば、健康リテラシーの向上につながる」と期待。製薬会社、ゲーム/エンターテインメント会社、医療従事者の3者がゲーミフィケーションを通じて連携し、新たなヘルスケアソリューションを生み出すことで「健康行動が促される社会を作っていきたい」と語りました。

ヘルスケアの未来は
デジタルヘルスが隆盛する背景には、進化するテクノロジーによって従来の医療の限界を突破できるのではないかという大きな期待があるからです。
横浜市大先端医科学研究センターコミュニケーション・デザイン・センターの武部貴則センター長は「これまでの医学は、薬や外科的治療、リハビリなど、複数の方法論を使って治療を施すということをしてきたが、これには限界がある」と指摘。「メタボの人に『リスクがあるから痩せてください』と医師が言っても、痩せたくないという人が多い。しかし、体の形に関わることが入り口になると、多くの人が痩せたくなる。形を可視化するという方法の方が、もしかしたら有効なのかもしれない」と言います。
 東京芸大が制作した、腹筋の回数が増えるにつれてイラストが変化していくゲーム
東京芸大が制作した、腹筋の回数が増えるにつれてイラストが変化していくゲーム
人生のあらゆるタッチポイントで介入
その上で武部氏は、医療の定義を「Medicine for Disease」から「Medicine for Humanity」へと変えていくことが必要だと強調。「病気を持った人の生活をみて、人生のあらゆるタッチポイントで介入をしていくことが大切で、しかもそれは多くの人にできることがあるのではないか」と説き、「空間」「アート」「音楽」「ファッション」といったものも介入の実践になり得ると話します。
武部氏によると、日本のゲーム人口は4500万人。ゲームは薬に比べて安くつくることができる上、世界トップ10にソニー、任天堂、バンダイナムコという3つの会社がランクインするなど、世界的に見ても日本が強い分野でもあります。
「目的の場所に行くことが難しくなる」という認知症の早期のサインを利用し、探検ゲームを使って認知症を早期診断する研究が欧州で行われるなど、ヘルスケア領域でのゲームの活用は海外を中心に進んできています。武部氏は「われわれはゲームに非常に大きな可能性が見込めると考えている。ゲーミフィケーションを活用したヘルスケアソリューションが増えて、当たり前に処方されるような形が、将来の医療をつくるかもしれない」と語りました。
(前田雄樹)