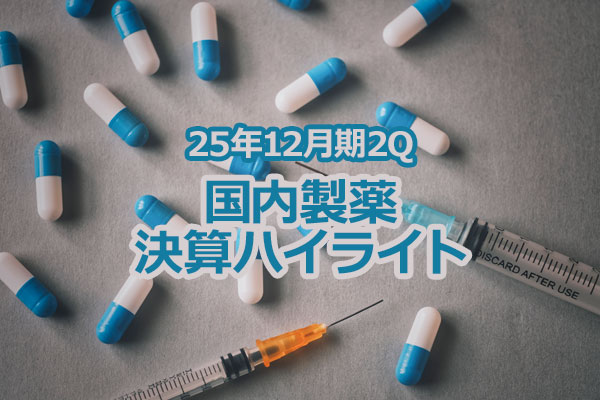医薬品の費用対効果を分析し、薬価に反映させる「費用対効果評価」。4月の本格導入に向け、制度の骨子が決まりました。ポイントを整理します。
INDEX
【ポイント1】保険適用するかどうかの判断には使わない
費用対効果評価は文字通り、医薬品や医療機器の費用対効果を評価し、それに基づいて保険償還価格(医薬品の場合は薬価)を調整する制度です。
国内では2010年ごろから中央社会保険医療協議会(中医協)で議論がはじまり、12年5月には中医協に「費用対効果評価専門部会」が設置され検討が本格化。16年4月には医薬品7品目・医療機器6品目を対象に試行がはじまり、その経験も踏まえて今年2月20日の中医協で制度の骨子が決まりました。今年4月から本格導入されます。
制度の大前提として、費用対効果評価は保険適用するかどうかの判断には用いられません。海外には、保険適用を決める際の判断材料として評価結果を活用している国(英国やオーストラリアなど)もありますが、日本の場合、評価結果は保険適用された医薬品・医療機器の価格調整にだけ使われます。新規の医薬品・医療機器については、いったん保険適用した上で費用対効果の分析を行い、結果に基づいてあとから価格の調整を行います。
【ポイント2】「完全健康状態で1年生存」にいくらかかるかで評価
医薬品・医療機器の費用対効果は「ICER」(増分費用効果比)という値で評価します。
ICERは、ある治療を別の治療と比べた場合に、「効果」を1単位獲得するのにいくらかかるかを表す指標。この値が小さいほど費用対効果は良いということになります。
ICERを算出するにあたり、「効果」を評価する指標となるのが「QALY」(質調整生存年)です。QALYは、生存年とQOL(生活の質)をあわせて評価するための指標。完全な健康状態を「1」、死亡を「0」としてQOLを数値化し、それに生存年を掛けて計算します。
QALYは概念としては非常に単純で、例えば「完全な健康状態で20年、その後病気で寝たきりとなりQOL0.3の状態で10年生きた患者X(QALYは23)」と「病気によりQOL0.5の状態で30年生きた患者Y(QALYは15)」を比べてみると、生存年は同じ30年でもQALYは患者Aのほうが高くなります。

ICERは、ある治療を別の治療と比べた場合に、このQALYを「1」獲得するのにいくらかかるかを表します。今回導入される制度では、費用対効果を「完全な健康状態で寿命を1年延ばすのに、追加でどれくらいの費用がかかるのか」で評価するということです。
例えば、ある疾患に標準的に使われる既存薬Bが10QALY獲得するのに1000万円、同じ疾患に対する新薬Aが15QALY獲得するのに3000万円かかるとします。この場合、新薬AのICERは400万円/QALYとなり、新薬Aは既存薬Bに比べて完全な健康状態で1年生存するのに追加で400万円のコストがかかるということになります。

【ポイント3】ICERが500万円/QALY以上で薬価引き下げ
今回導入される費用対効果評価では、ICERが500万円/QALYを超えた医薬品は薬価が引き下げられます。
引き下げの範囲は薬価全体ではなく、原則として、薬価全体のうち「有用性系加算(画期性加算、有用性加算)部分」が対象。原価計算方式により薬価算定された品目で、原価の情報開示が少ないものは、営業利益部分も引き下げの範囲に含まれます。

薬価の引き下げは、ICERが▽500万円/QALY以上750万円/QALY未満▽750万円/QALY以上1000万円/QALY未満▽1000万円/QALY以上――の3段階で実施。適応症の一部に希少な疾患を含むなど「配慮が必要とされた品目」については、▽750万円/QALY以上1125万円/QALY未満▽1125万円/QALY以上1500万円/QALY未満▽1500万円/QALY以上――に緩和されます。
薬価の引き下げ率は有用性系加算部分と営業利益で別々に設定されており、加算部分は「30%」「60%」「90%」、営業利益部分は「17%」「33%」「50%」。ICERが500万円/QALY未満の場合、薬価の引き下げは行われません。

また、安定供給を確保する観点から、価格調整には「下げ止め」という仕組みも設けられました。有用性系加算の加算率が25%以下の品目は調整前の薬価全体の10%、加算率100%以上の品目は15%、加算率が25%以上100%未満の品目は10~15%の範囲で加算率に応じた率が、それぞれ薬価引き下げの上限となります。
一方、比較対象となる治療に比べて効果が大きいか同等で費用が減る品目(ICERが算出不能な品目)や、ICERが200万円/QALY未満の品目は、一定の条件を満たせば薬価が引き上げられます。
【ポイント4】ピーク時の市場規模予測が100億円以上の医薬品などが対象
費用対効果評価の対象は、新規収載品(制度の本格導入以降に保険適用される品目)の場合、薬価算定時に有用性系加算(医薬品の場合は画期性加算や有用性加算)がついた品目や、原価計算方式で原価の情報開示度が50%未満の品目で、▽ピーク時の市場規模予測が年100億円以上(H1)▽同50億円以上100億円未満(H2)――のものなど。

H1に該当する品目は速やかに費用対効果の分析を始める一方、H2は「評価候補品目」と位置付け、年間の評価可能品目数も勘案しながら、市場規模予測の高いものから分析を実施。また、H1、H2の条件に該当しない品目でも、単価が著しく高い場合などは中医協の判断で対象にすることができます。
一方、既収載品(本格導入以前に保険適用された品目)の場合は、有用性系加算が算定された品目で、市場規模が年間1000億円以上の品目が対象。新規収載品と同様、単価が高いなどの理由で費用対効果評価が必要と中医協で判断された品目も対象となります。
難病だけに使われる医薬品などは対象から除外
対象品目の選定にあたっては、新薬開発や患者アクセスの観点から除外基準も設けられています。

具体的には、▽治療法が十分に存在しない希少な疾患(指定難病や血友病、HIV)だけに使われる品目▽小児だけに使われる品目――は、費用対効果評価の対象から除外。適応症の一部にこれらを含む品目や抗がん剤は評価の対象となりますが、薬価引き下げの基準が緩和されます(ポイント3を参照)。
【ポイント5】分析開始から15カ月程度で新薬価が決定
選定基準に沿って中医協で費用対効果評価の対象品目が決まると、その後、分析前協議→企業分析→公的分析→総合的評価、の流れで評価が行われます。

企業分析とは文字通り、対象品目を持つ製薬企業が自ら行う分析のこと。公的分析では、大学などの第三者(公的分析班)が企業分析の妥当性を検証し、必要に応じて独自の分析(再分析)を行います。
企業分析の前には、企業と公的分析班の間で▽どういった患者集団を対象にするか▽どの治療(医薬品)と比較するか▽どういったデータ(臨床試験)を分析に使うか――といった分析の枠組みをすり合わせる分析前協議を実施。このとき、企業と公的分析班は直接接触しないこととされており、国立保健医療科学院が間に入って行われます。
企業分析と公的分析が終了すると、その結果を中医協の「費用対効果評価専門組織」が総合的に評価。最後は、中医協で最終的な評価と新たな薬価が決まります。
総合的評価を担当する費用対効果評価専門組織は、医療経済や医療統計の専門家らで構成。品目に応じて、あらかじめ分野ごとに指名された臨床の専門家も参加し、分析や評価の妥当性を確認します。
![費用対効果評価専門組織の構成の表。【本委員】<費用対効果評価専門組織>・医療経済の専門家4人程度・臨床の専門家2人程度・医療統計の専門家2人程度・医療倫理の専門家1人程度。([参考]:薬価算定組織、・医師7人・歯科医師1人・薬剤師2人・医療経済学者1人)。【分野ごとの専門家】<費用対効果評価専門組織>分野ごとの臨床の専門家をあらかじめ指定(30人程度)。([参考]:・医師27人・歯科医師1人・薬剤師10人・医療経済学者4人)。](https://ten-navi-prd-cms-img-481565300627.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/answers/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/HTA8.png)
費用対効果の分析・評価にかかる期間は、分析前協議から中医協での評価・新薬価決定までで15カ月(公的分析で再分析を行う場合は18カ月)。評価に基づく薬価の調整は年4回ある新薬の薬価収載のタイミングで行われますが、医療機関・薬局の在庫への影響なども考慮し、新薬価の公表から実際の調整までは一定の期間を設けることになっています。
製薬業界の受け止めは
費用対効果評価の制度の概要が固まったことを受け、日本製薬工業協会(製薬協)の中山譲治会長は2月20日、「医薬品の研究開発・安定供給を継続していく上で厳しい内容と言わざるを得ない」との見解を発表しました。
製薬協は見解の中で、▽原価計算方式で薬価算定された品目では、有用性系加算が適用されていない一部品目も費用対効果評価の対象になっている▽評価に基づく薬価の引き下げ幅が大きすぎる▽総合的評価がICERに偏っており、公的介護費や生産性損失など考慮されるべき要素が十分に反映されていない――の3点を問題点として指摘。運用での改善と求めていくとともに、薬価制度全体として医薬品の多面的な価値を評価できる仕組みへの見直しを働きかけていく方針です。
(前田雄樹)