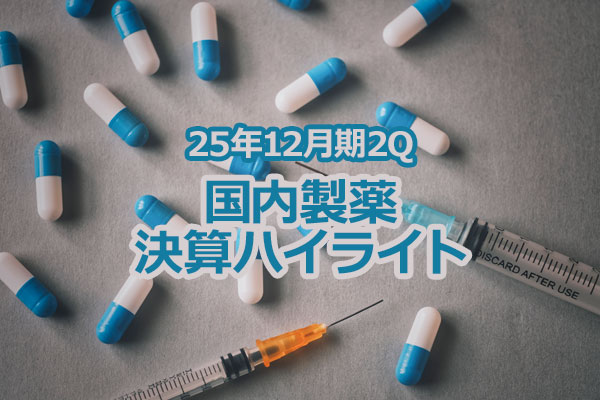自宅にいながらにして臨床試験に参加できる「バーチャル臨床試験」。今年に入り、スイス・ノバルティスや仏サノフィが相次いでIT会社との提携を発表するなど、欧米の大手製薬企業が活用に本腰を入れています。
バーチャル臨床試験によって何ができるようになり、どんなメリットがあるのか。バーチャル臨床試験システムを提供する米メディデータの日本法人メディデータ・ソリューションズの山本武・代表取締役に話を聞きました。
患者負担を軽減 臨床試験へのアクセスを上げる
「バーチャル臨床試験」の活用に、欧米の製薬大手が本腰を入れています。今年3月には、スイス・ノバルティスと仏サノフィがそれぞれ、分散型治験システムを提供する米IT会社「サイエンス37」との提携を発表。ノバルティスは今後3年間で10件のバーチャル臨床試験を開始するとしています。
今回、話を聞いた米メディデータも今年2月、バーチャル臨床試験のためのプラットフォーム「Engage」の提供を開始したと発表しました。そもそも、バーチャル臨床試験とはどのようなものなのでしょうか。
「従来の臨床試験では、患者は病院で診察・診療を受けて、そこで得られたデータが試験の結果として評価されてきました。ところが昨今、モバイルテクノロジーの進化とか、遠隔医療とか、さらにはさまざまなセンサーの進歩によって、いろいろなデータを遠くからリモートで取れるような世界ができあがってきた。そこで、ある程度は遠隔で治験を実施できるのではないかというのが、バーチャルトライアルの取り組みです。
例えば、遠くの病院に行かないと治験が受けられない場合、その患者はどんなに治験を望んでも、通院の負担によって参加できないというケースもある。患者の負担軽減は、臨床試験における非常に重要なファクター。患者の負担を軽減し、臨床試験へのアクセスを上げていこうというのが最大の狙いです」

リクルーティングの期間とコストを削減
製薬企業がプライマリー領域からスペシャリティー領域に新薬開発の軸足を移す中、課題となっているのが被験者の確保です。
米国のNPO「Center for Information & Study on Clinical Research Participation」(CISCRP)によると、米国では参加条件に該当する患者の2%しか臨床試験に参加しておらず、米国で実施される臨床試験の80%が被験者の募集を理由に遅れているといいます。試験の遅れは、そのまま開発コストに跳ね返ってきます。
「バーチャルによって臨床試験へのアクセスを上げることは、患者のリクルーティングの助けになると考えられます。
分子標的薬や個別化医療、希少疾患、こういったところに新薬を投入していこうというのが、今の製薬業界のトレンドです。しかし、こうしたところで薬を開発しようとすると、当然ながらプロトコルは複雑化していきます。
対象患者が絞られる中で有効性と安全性を評価するのに十分なデータを集めようとすれば、それだけリクルーティングに時間とコストがかかるようになる。そこに対するソリューションとして、さまざまな製薬会社がバーチャル臨床試験に取り組み始めているということなんだと思います。
リクルーティングの期間短縮はコスト削減効果も大きいし、開発期間が短縮できると販売期間も長くなる。経済的にも大きな効果をもたらします。バーチャル臨床試験は患者だけでなく、製薬企業の事業にとっても非常にポジティブな影響があると考えられます」
バーチャルだから取れるリアルなデータ
バーチャル臨床試験は、臨床試験で最も重要なデータそのものを変えてしまう可能性も秘めています。モバイルテクノロジーを活用することで、通常の臨床試験では得るのが難しいリアルなデータを集めることができるようになるといいます。
「バーチャル臨床試験では、データの質も変わってくると思っています。今やられているほとんどの臨床試験では、データポイントは来院時で、来院時にとったデータがすべて。場合によってはこれにプラスして、被験者日誌を確認しながら有効性と安全性を評価していくことになっています。
これがバーチャル臨床試験になると、さまざまなテクノロジーを駆使して患者さんを観察していくことになります。ウェアラブルセンサーで脈拍や血圧を計り続ければ、通常の臨床試験のデータよりもっと細かいポイントでデータを拾っていくことができる。
被験者日誌についても同様で、例えば『いつ痛みが出たか』ということも、モバイル端末を使うことによってかなりの精度でその瞬間を捉えることができるようになります。
こうしたことでデータの質が上がれば、誤差も小さくなって試験のn数を減らすことができるかもしれない。さらに、これまで有効性がなかなか説明できなかった薬も、患者の生活をトラックして細かいデータをとることで説明できるようになるかもしれない。そうすると、今まで世の中に出てこなかった薬が出てくるようになるかもしれません。
もう1つ例を挙げると、痛みの評価には決められた指標がありますが、痛みが収まると活動が増えるというふうに考え方を少し変えると、GPSを使って行動範囲が広がったかどうかを評価するということもできるのではないでしょうか。
こうしたデータは、今までの臨床試験では取れなかったデータです。そういった新しいデータが今後、エンドポイントとして活用できるようになれば、真のアウトカム志向というか、患者のQOLにどう貢献したのかというデータの見方もできるようになるのではないでしょうか」

メディデータ・ソリューションズの山本武・代表取締役
米国では100%バーチャルの大規模臨床研究も
メディデータによると、世界初のバーチャル臨床試験は米ファイザーが行った過活動膀胱治療薬「Detrol LA」(一般名・酒石酸トルテロジン、日本製品名・デトルシトール)の製造販売後臨床試験「REMOTE」。
メディデータは、この試験に使われたアプリケーションEngageを買収によって獲得しました。米国では、同社のテクノロジーを使ったバーチャル試験がすでに12本実施。サイエンス37と提携するノバルティスも、すでに米国で群発頭痛やにきび、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の治療薬のバーチャル臨床試験を始めたことを明らかにしています。
「米国では現在『ADAPTABLE』という史上最大規模のバーチャルによる臨床研究が行われています。
これは、米国のNPO法人『Patient Centered Outcomes Research Institute(PCORI)』が行っているもので、心疾患患者1万5000人の登録を目標に、アスピリンの低用量投与群と高用量投与群を比較する研究です。この研究にはメディデータのプラットフォームが使われており、100%バーチャルで研究への参加から経過観察まで行っています。
100%バーチャルというのは、臨床試験(研究)のためだけの来院が必要ないということ。ただ、今私たちが考えているのは、バーチャル臨床試験は100%バーチャルでなければならないのかということ。
例えば、検査項目が100あるとすると、そのうち50はバーチャルで、あとの50は来院してもらってもいいのではないかと。それでもバーチャル化の効果は出ると思います。場合によってはこれを患者ごとに変えられないのかといった取り組みは必要だろうと考えています」
日本での広がりは
日本では先日、慶応大が、ペンドレッド症候群の難聴・めまいに対して低用量のシロリムスを投与する医師主導治験で、患者に検査機器やタブレット端末を貸し出し、検査結果を自宅からリモートアクセスでデータセンターに送る取り組みを行うと発表しました。バーチャル臨床試験は今後、日本でも広がっていくのでしょうか。
「日本でできるようになるのかということを私の立場で言うのはおこがましいと思いますが、できるようになるべきなんだと思います。
臨床試験へのアクセスを向上させることに対して否定的な考えをする人はいないと思います。その中でテクノロジーが進化し、それを活用して臨床試験へのアクセスを上げて患者に貢献するのは非常に重要。コストダウンの効果もあるとなると、医療費など今の日本の重要なテーマにも沿う取り組みにもなるでしょう。バーチャルだからこそ取れるリアルなデータが、薬の本当の価値を評価する指標になってくるかもしれません。
日本でバーチャル試験を行うハードルが低いとは思いません。今は海外が中心ですが、事例が増えてくることによって導入しやすい環境ができてくるのではないかと思います」
あわせて読みたい
オススメの記事
-

キッセイ、米社から甲状腺眼症治療薬を導入/参天、緑内障・高眼圧症薬ネタルスジルメシル酸塩を申請 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年7月30日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り