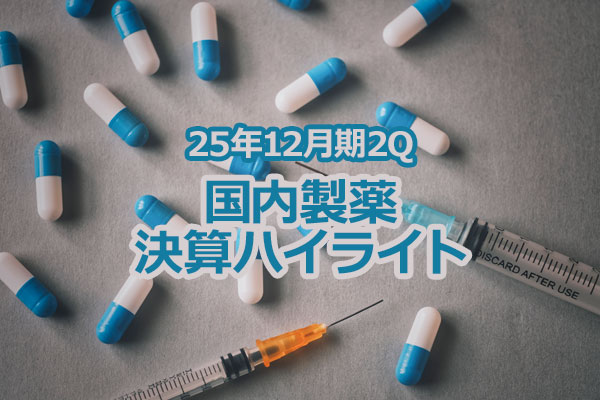がん治療で急速に普及する分子標的薬。その投与の適否を判断する「コンパニオン診断薬」のあり方が大きく変わろうとしています。
免疫チェックポイント阻害薬の登場で「薬剤と診断薬の1対1の関係が崩れてきている」と指摘するのは、愛知県がんセンター中央病院遺伝子病理診断部長・臨床検査部長の谷田部恭氏。PD-L1という一つのバイオマーカーに多くの薬剤が診断薬を伴って登場することで「従来のコンパニオン診断薬の枠組みは破綻をきたす」といいます。
重要性増すバイオマーカー
日本語で「精密医療」と訳される「プレシジョン・メディシン」。がん細胞の遺伝子変異を調べ、患者一人ひとりに最適な治療薬を選ぶこの医療のあり方は、2015年に米国のオバマ大統領が一般教書演説で「プレシジョン・メディシン・イニシアチブ」を発表したことで世界的に大きな注目を集めました。日本でも国立がん研究センターを中心とする全国約200の医療機関と製薬企業十数社が参加する「SCRUM-Japan」と呼ばれるプレシジョン・メディシンのプロジェクトが進行中です。
がん細胞の特定の遺伝子変異をターゲットとした分子標的薬は、すでに国内でも多くの製品が販売されています。乳がんや胃がんで発現するHER2を標的とした「ハーセプチン」、ALK融合遺伝子(肺がん)の「ザーコリ」「アレセンサ」、EGFR(同)の「イレッサ」「タグリッソ」、BRAF(悪性黒色腫)の「ゼルボラフ」「タフィンラー」など。バイオマーカーの重要性は増しています。
こうした分子標的薬の投与の適否を判断するのに欠かせないのがコンパニオン診断薬。厚生労働省の定義によれば、
▽特定の医薬品の有効性または安全性の向上などの目的で使用
▽当該医薬品の使用に不可欠な体外診断用医薬品または医療機器
▽単に疾病の診断などを目的とするものを除く
とされ、具体的には
▽効果がより期待される患者を特定する
▽特定の副作用が発現するおそれの高い患者を特定する
▽用法・用量の最適化または投与中止の判断を適切に実施する
といった目的で使用されるものとされています。
免疫CP阻害薬 各薬剤で診断薬も開発
コンパニオン診断薬はその名の通り、特定の治療薬専用の診断薬として、医薬品とセットで開発されるもので、医薬品と同時に承認されるのが一般的です。
いわば治療薬と診断薬が「1対1」の関係にあるわけですが、この概念が最近、崩れつつあると、愛知県がんセンター中央病院遺伝子病理診断部長・臨床検査部長の谷田部恭氏は指摘します。7月21日、MSDが開いたがんのバイオマーカーに関するメディア向けのセミナーで「従来のコンパニオン診断薬の概念は破綻をきたしている」と述べました。
その背景には、1つのバイオマーカーに対して数多くの薬剤が開発されている現状があるといいます。谷田部氏がその例として挙げたのが免疫チェックポイント阻害薬です。
免疫チェックポイント阻害薬は現在、小野薬品工業の抗PD-1抗体「オプジーボ」(ニボルマブ)とMSDの同「キイトルーダ」(ペムブロリズマブ)が日本で承認済み。中外製薬の抗PD-L1抗体アテゾリズマブとファイザーの同アベルマブが申請中で、アストラゼネカの同デュルバルマブも臨床第3相試験の段階にあります。
オプジーボとキイトルーダにはそれぞれ、非小細胞肺がんへの投与の可否を判断するにあたり、がん細胞のPD-L1発現率を調べる診断薬が承認されています。キイトルーダは「PD-L1 IHC 22C3 pharmDx『ダコ』」、オプジーボは「PD-L1 IHC 28-8 pharmDx『ダコ』」。開発中の免疫チェックポイント阻害薬でも、それぞれの薬剤に対応した診断薬の開発が進められています。
オプジーボはキイトルーダの診断薬でも条件付きでOK
ただし、オプジーボではPD-L1の検査は必須ではなく、厚生労働省が作成したオプジーボの最適使用推進ガイドラインでは、非扁平上皮がんの患者に限り「PD-L1発現率が1%未満の場合は原則、ドセタキセルなど本剤以外の抗悪性腫瘍剤の投与を優先する」と規定しています。
しかも、キイトルーダのコンパニオン診断薬でPD-L1の発現率を確認した患者で、オプジーボの診断薬による再検査が困難な患者には、キイトルーダのコンパニオン診断薬による診断でも投与の可否を判断することを認めています。
1つのバイオマーカーに対して複数の薬剤が開発されており、現実に免疫チェックポイント阻害薬では他剤のコンパニオン診断薬での診断が認められている状況から、谷田部氏は「薬剤と診断薬が1対1の関係だったのが、薬剤がたくさん出てきたためにその関係が保てなくなっている。従来の枠組みが合わなくなってきている」と指摘します。
免疫チェックポイント阻害薬は診断薬とあわせて今後も続々と臨床の現場に登場する見通しです。ただ、「これまでのコンパニオン診断薬の概念にのっとれば、それぞれ検査を行い、それをもって薬を決めなければならないが、肺がんの検体は非常に小さい。EGFRやALKを含め、たくさんのバイオマーカー検査をするのが可能かというと、なかなか難しい」(谷田部氏)。実際、どれか一つの診断薬で検査を済ませられるかどうかを検証する研究も行われているといいます。
「診断薬に縛られる必要はない」
こうした状況の中、免疫チェックポイント阻害薬をどう選択すべきなのか。谷田部氏は「個人としては、精度管理ができて診断されるのであれば、コンパニオン診断薬にそれほど縛られる必要はないのではないかと思う」と述べました。
一方、免疫チェックポイント阻害薬のPD-L1検査には別の課題もあります。1つは投与の基準となるPD-L1の発現率が薬剤によって異なること。キイトルーダの場合は、非小細胞肺がんの1次治療はPD-L1の発現率が50%以上、2次治療では1%以上が投与の対象となるのに対し、開発中の薬剤の中には25%以上としているものもあり、「クライテリアが違い、診断する側としては紛らわしい」(谷田部氏)。発現率を定量的に判断しなければならず、同じ腫瘍の中でも場所によって発現率が異なるという難しさもあります。
免疫チェックポイント阻害薬は一部の患者に高い効果を示す一方、高額なだけに、投与すべき患者の選別は重要なポイントです。プレシジョン・メディシンががん治療の主流となっていく中、コンパニオン診断薬のあり方も変わっていくのかもしれません。