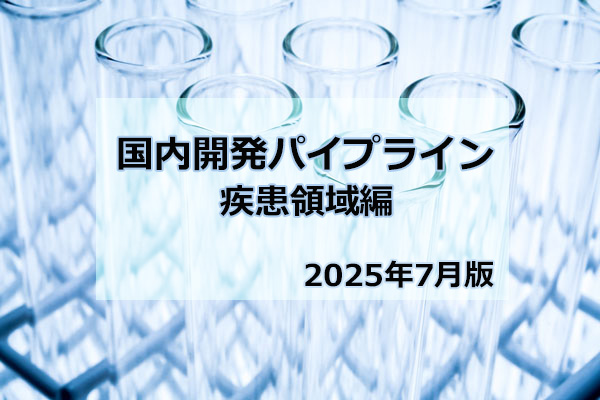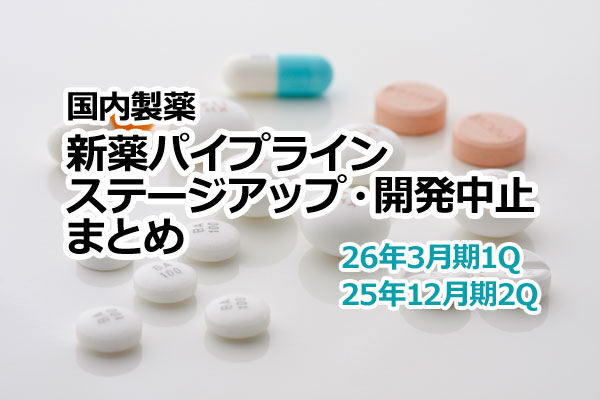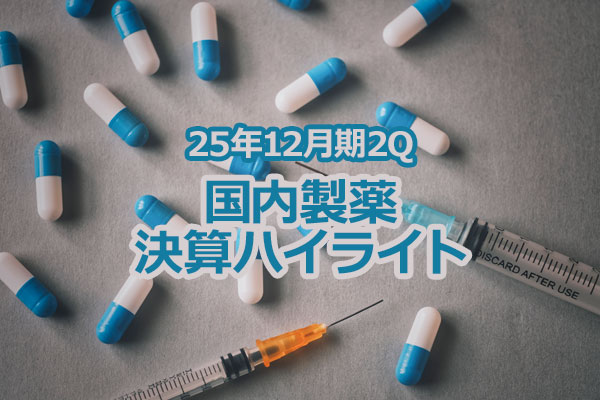ビーワン・メディシンズの安達進社長
BeiGene Japanから社名を変更したビーワン・メディシンズが、国内2製品目となる抗PD-1抗体「テビムブラ」を発売し、日本市場への攻勢を一段と本格化させています。3月に発売したBTK阻害薬「ブルキンザ」の販売は好調といい、テビムブラも対象とする食道がんで高シェア獲得を狙う構え。「グローバルの豊富なパイプラインをいち早く日本の患者さんに届けるのが、われわれの使命であり責任だ」と話す安達進社長に、日本事業の現状と展望を聞きました。
テビムブラ「既存薬との違い、短期間で浸透」
――7月1日付で日本法人の社名をBeiGene Japanからビーワン・メディシンズに変更しました。
ビーワン(BeOne)という社名には、製薬企業、患者さん、支援団体、さらには当局といったステークホルダーが1つのチームとなって、自分らしく生きる患者さんを支えるというメッセージを込めています。新たなロゴでは、Oneのeの横線だけ色を変え、オンコロジーをイメージできるものにしました。今年1月には米ナスダックのティッカーシンボルも「ONC」に変更しており、オンコロジーへのコミットメントを示しています。個人的には、その名の通り、いろんな意味で1番の会社になりたいと思っています。

ビーワン・メディシンズのロゴ(同社提供)
――社名変更と同じ日に、国内2製品目となる抗PD-1抗体「テビムブラ」(一般名・チスレリズマブ)を発売しました。対象とする食道がんでは先行している免疫チェックポイント阻害薬もありますが、テビムブラはこれらとどんな違いがあるのでしょうか。
テビムブラは、抗体に改変を施すことで主に3つの既存のPD-1抗体との違いを持たせています。1つ目は、PD-1に対するカバー率がほかの薬剤と比べて高いこと。2つ目は、PD-1への結合率が他剤と比べて高いこと。3つ目が、マクロファージによるT細胞の貪食を他剤より抑えられることです。
化学療法歴のない根治切除不能な進行・再発食道扁平上皮がんの患者さんを対象に行った国際共同臨床第3相(P3)試験では、テビムブラと化学療法の併用療法の全生存期間(中央値)は17.2カ月で、プラセボと化学療法の併用(10.6カ月)と比べて統計学的に有意な延長を示しました。先ほど説明した特徴がこうしたデータにつながっていると考えています。
今年3月末の承認以降、既存の抗PD-1抗体との違いについて短期間で専門医に浸透してきており、手応えを感じているところです。市場でも高いシェアを獲得できるのではないかと思っています。
――3月に国内第1号製品として発売したBTK阻害薬「ブルキンザ」(ザヌブルチニブ)の販売状況はどうですか。
想定を上回るスピードで先生方に使用していただいています。他のBTK阻害薬との直接比較試験のデータがあること、心毒性をはじめとする安全性のプロファイルも比較対照としたBTK阻害薬と大きく異なることが評価されていると考えています。
ブルキンザはBTKに対する選択性が高く、安定して高い血中濃度を維持できるのが特徴で、第2世代のBTK阻害薬として血液がん専門医の間では以前から知られていました。日本での承認は昨年12月でしたが、化合物の特徴や臨床での優位性が医師にきちんと伝わっていると感じています。

――営業の体制や戦略を教えてください。
コール数という観点でMR体制はつくっていません。私もがんを専門に治療する医師でしたが、がんという疾患の特性上、しっかり話し込めることが大事だと思うので、他社よりもかなり少ないMRの人数で営業体制を構築しています。
その分、一人ひとりのMRが活動しやすい環境は用意しています。たとえば、1人あたりのカバーする範囲が広くなるので、全MRに4WDのハイブリッド車を営業車両として渡しています。
MRには医師と患者さんの話をしてほしいと思っています。どんな患者さんがいるのか聞いた上で、適切な患者さんに使っていただくことが大切で、明らかにわれわれの製品を使うべきでない患者さんについては断るようにと常に言っています。そういった活動ができるスキルの高いMRをたくさんそろえるのも難しいですから、少ない人数の中でそうした販売活動をやっていきたいと思っています。
新薬開発「海外から遅れることないよう体制整備」
――今後の日本での製品開発・市場投入の計画を教えてください。
テビムブラについては、胃がんへの適応拡大に向けたP3試験が終了し、国内で申請の準備を進めています。それ以外の疾患についても開発を検討中です。ブルキンザは現在、マントル細胞リンパ腫と濾胞性リンパ腫を対象としたP3試験に日本も参加しています。もう1つの適応でも日本独自の試験を計画中です。
24年には13の新薬候補を臨床段階に進めており、これはオンコロジー領域で世界一です。その前の年を含む2年間で見ても、英アストラゼネカに次いで2番目に多くなっています。モダリティも幅広く、低分子はもちろん、二重特異性抗体、三重特異性抗体、細胞療法、「CDAC」と呼ぶ標的タンパク質分解誘導薬などを手掛けています。特に標的タンパク質分解誘導薬は業界トップレベルの開発品を持っていると思っています。
近い将来に承認取得を見込むのは、BCL2阻害薬とBTK CDACです。BCL2阻害薬は、日本は少し遅れるものの海外では順調にいけば今年から来年の申請を予定していますし、BTK CDACは日本もP3試験に入っています。
乳がんを対象に開発しているCDK4阻害薬も今後、P3試験に入ってくると思われ、大きな期待を持っています。開発は米ファイザーが先行していますが、ポテンシャルとしては十分に戦えると思っています。
――グローバルのパイプラインはすべて日本でも開発していく方針ですか。
はい。日本法人のキャパシティの問題もあり、現状ではまだすべてのパイプラインを開発できていませんが、来年以降に始まる試験については、少なくともP3試験には乗り遅れることのないようにしたいと考えています。
ビーワンはグローバルで臨床開発業務の内製化を進めています。内製化したほうが開発期間を短縮でき、コストも削減できるからです。日本法人では、昨年はすべての試験をCROに委託していましたが、今年はそれを50%にし、来年にはほぼ自前で行えるようにします。そうすることで海外に遅れることなく試験に入り、申請まで持っていけると考えています。
パイプラインが豊富にあるということは、それを患者さんに届ける責任があるということです。海外に遅れることなく良い薬、良いオプションを届けることがわれわれの1番の使命だと思っています。
日本法人「26年に200人規模に」
――事業拡大に向け、日本法人の体制をどう整備していきますか。
現在、日本法人の従業員数は130人。これを25年中に150人以上、26年に200人程度まで増やす計画です。
――2021年の日本法人設立から5年間で2製品を発売しました。これまでの日本市場での活動をどう評価しますか。
私がビーワンに入社したのは22年8月で、日本法人では3番目の社員です。その年の終わりの社員数は6人、翌23年末が19人でしたので、実質2年半から3年の会社としてはよくやってきたと思っています。
製品の開発・販売以外にも、実はいろいろな取り組みをしています。
たとえば、ブルキンザは2週間のパッケージで販売していますが、発売直後、ある医師から「初めて処方する患者さんは、どんな副作用が出るかわからないので1週間で処方するようにしているが、病院や薬局からは『残ったら不安だ』と言われる」との声をいただきました。そこで、関係機関に掛け合い、一定の条件を満たせば返品を受け付けることにしました。この取り組みは多くの医療機関の薬剤部から評価していただいています。
もう1つ例を挙げると、学会のブースや会社が行う講演会で先生方に書いていただくアンケート1件につき2000円を、小児がんや希少がんに関連する団体や学会に寄付する取り組みを24年から行っています。
製品の開発や販売はもちろん、こうした取り組みや企業としての姿勢についても今後、さらに認知を広げていけたらと思っています。
あわせて読みたい
オススメの記事
-

キッセイ、米社から甲状腺眼症治療薬を導入/参天、緑内障・高眼圧症薬ネタルスジルメシル酸塩を申請 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年7月30日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り