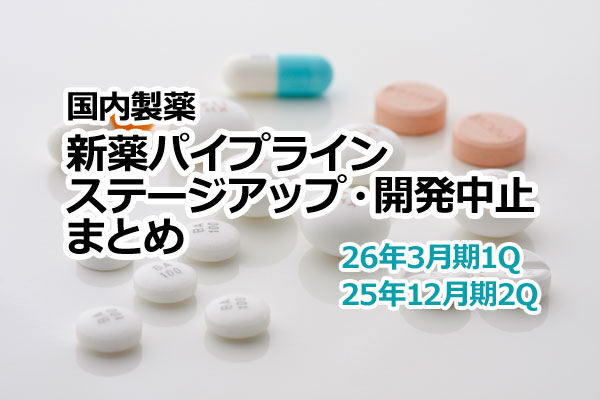国内推定患者数2500人の希少疾患、遺伝性血管性浮腫に新薬が続々と登場しています。2018年に国内では28年ぶりとなる治療薬が発売されたのを皮切りに、継続的な投与で急性発作の発症を抑制する治療薬が相次いで発売。選択肢は広がる一方、治療を受けている患者は推定患者数の5分の1以下とされ、啓発が課題となっています。
血漿カリクレイン阻害薬など相次ぎ承認
遺伝性血管性浮腫(HAE)は、C1インヒビター(C1インアクチベーター)と呼ばれるタンパク質をつくる遺伝子の異常によって起こる疾患です。主な症状は突発的かつ繰り返し起こる浮腫の発作。発作は数日で自然に消失しますが、体のさまざまな部位に現れます。浮腫が咽頭に起こると気道が閉塞し、呼吸困難となって生命を脅かすことがあるほか、消化管に現れると激しい腹痛や嘔吐、下痢を伴います。HAEは「原発性免疫不全症候群」の1つとして指定難病に指定されています。
HAE患者では、遺伝子異常によってC1インヒビターの量が不足または機能が低下しています。C1インヒビターは血液中に存在してさまざまな機能を担っていますが、その1つが浮腫の直接的な原因となるブラジキニンの過剰な産生を抑える働きです。C1インヒビターの不足または機能低下によって過剰になったブラジキニンは、ブラジキニンB2受容体に結合して血管拡張や血管浸透性の亢進を引き起こし、その結果、血管から水分が漏れ出して浮腫を生じさせると考えられています。
HAEの治療は、▽急性発作が起こったときに行うオンデマンド治療▽手術や抜歯、内視鏡検査など発作を起こすリスクがあるイベントの前に行い、発作を抑制する短期発作抑制治療▽発作を抑止するために定期的に薬を投与する長期発作抑制治療――に分けられます。

国内では1990年に、オンデマンド治療としてC1インヒビターを補う血漿分画製剤「ベリナートP静注用」(CSLベーリング)が承認。2018年には28年ぶりの新薬としてブラジキニンB2受容体ブロッカー「フィラジル皮下注」(武田薬品工業)がオンデマンド治療を対象に発売されました。ベリナートは医療機関で投与する必要がありましたが、フィラジルは患者が自宅などで自己注射することが可能です。短期発作抑制治療では、ベリナートPが17年に適応拡大の承認を取得しています。
活性化第XII因子阻害薬が登場
その後、2020年代に入ると、長期発作抑制治療を対象とした薬剤が次々と承認。21年に血漿カリクレイン阻害薬「オラデオカプセル」(オーファンパシフィック、販売は鳥居薬品)、22年に同「タクザイロ皮下注」(武田薬品)とC1-インアクチベーター製剤「ベリナート皮下注用」(CSL)が発売され、今年4月には活性化第XII因子阻害薬「アナエブリ皮下注用」(CSL)が登場しました。
血漿カリクレインはブラジキニンの産生に関わる物質で、オラデオやタクザイロはこの働きを阻害することでブラジキニンの産生を抑制します。
一方、アナエブリはHAEの急性発作の主要な開始因子である活性化第XII因子を標的とする薬剤。活性化第XII因子は血漿カリクレインを活性化し、ブラジキニンの過剰な産生を引き起こしますが、アナエブリはこの一連の反応の最上流を阻害することで効果を発揮します。承認の根拠となった国際共同臨床第3相(P3)試験では、6カ月間の治療期の月間発作回数を平均0.27回に抑え、プラセボ(平均2.01回)に比べて有意に発作が少ないことが示されました。

確定診断まで平均15.6年、未治療患者多く
アナエブリの発売にあわせてCSLが4月に開いたメディア向けセミナーで講演した広島市立病院機構の秀道広理事長は「さまざまな治療薬が使えるようになり、日本のHAE治療は新たなステージに入っている」と指摘。「発作の頻度や重症度、仕事や生活は患者一人ひとり違うし、薬の聞き方もさまざま」とし、投与のタイミングや剤形、投与頻度が異なる治療薬の中から患者の症状や生活に合わせて選択していく必要があると語りました。
治療選択肢が広がる一方で、診断には大きな課題があります。海外ではHAEの発症頻度は5万人に1人とされ、これを当てはめると日本には約2500人の患者がいると推定されています。しかし、診断・治療中の患者は約430人と報告されており、未診断・未治療の患者が多くいるとみられています。
その背景について秀氏は、「浮腫は体のさまざまな部位で起こるが、同時に起こるわけではないので一連の症状だと気付かれにくい」と説明。医療機関を受診しても別の疾患と診断されるケースも多く、発症から確定診断までに平均15.6年かかっているといいます。
「啓蒙を続けていかなければならない」
CSLの吉田いづみ社長は「HAEという病気の啓蒙を続けていかなければならい」と強調。診断率の向上に向けては、患者会と臨床医・アカデミア、HAE治療薬を販売する企業などでつくるコンソーシアムが21年に発足し、啓発活動などに取り組んでいます。コンソーシアムの代表理事も務める秀氏は「病気のことを知ってもらうとともに、患者同士あるいは患者と医師の間で情報交換し、治療の恩恵から漏れる人を少なくしたい」と話しました。
HAEに対しては、米カルビスタ・ファーマシューティカルズの日本法人がオンデマンド治療として経口血漿カリクレイン阻害薬セベトラルスタットを申請中。承認されれば初の経口オンデマンド治療となり、販売は提携先の科研製薬が行います。秀氏によると、海外では血漿カリクレインを標的とした核酸医薬や遺伝子治療の開発も行われおり、将来的に治療手段はさらに広がっていきそうです。
AnswersNews編集部が製薬企業をレポート
あわせて読みたい
オススメの記事
-

ウルトラジェニクス、LC-FAOD治療薬トリヘプタノインを申請/MSD、21価肺炎球菌ワクチン「キャップバックス」承認 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年8月8日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り