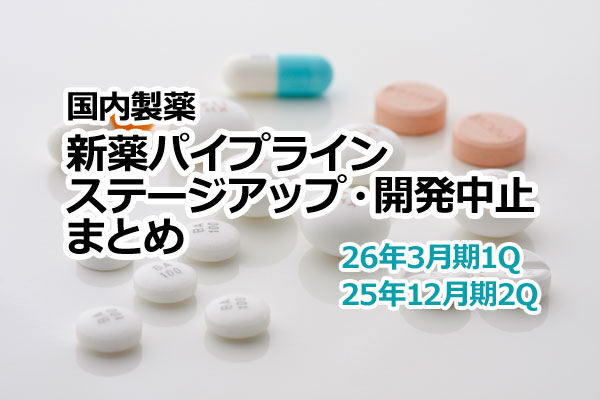最近、娘たちが映画にハマっていて、週末にはよく一緒に観に行きます。家族でいろいろな物語に触れることができるようになり、父としては嬉しいきょうこのごろです。
少し前になりますが、家族で実写映画版の「はたらく細胞」を観に行ってきました。擬人化された細胞(主に免疫系)が協力して感染症やがんといった病気と闘う物語です。マンガやアニメも大人気で、ご存知の方も多いと思います。
免疫を専攻していた私としては色々とツッコミたくなる気持ちがなかったわけではありませんが、それも吹き飛んでしまうくらい良くつくられた映画でした。マンガやアニメも子どもたちと見ていましたが、そちらは体内でのミクロな話がメインだったのに対し、映画は人間の症状や感情も描かれ(恋愛のシーンでは、DJ KOO扮する神経細胞がいろいろな神経伝達物質を出して全身の細胞をアゲアゲにしていました)、ミクロとマクロを行き来しながら物語が展開されていきました。
そんな仕掛けのおかげで病態と生体内の細胞の働きの関係がイメージしやすかったからか、観終わると子どもたちから質問や感想がいろいろと出てきました。
「どうして細胞には酸素や栄養が必要なの?」
「同じ細胞なのになんでがん細胞になるの?」
「幹細胞って何?」
「恋愛でアゲアゲになるのわかるわ~」
「外肛門括約筋の頑張りに感謝だね」
などなど。
元研究者で今も製薬企業で働く私にとって、子どもたちとこうしたコミュニケーションがとれるのは本当に嬉しいことです。体内では無数の細胞が年中無休で働いていて、その時々の環境や状況に力を合わせて対応しているからこそ、毎日健康に過ごせているということを理解してもらえたようでした。
映画の中では、不摂生の父親が娘の希望もあって健康に気を付けるようになり、健康診断で数値が改善したことを嬉しそうに娘に伝えるシーンも描かれていました。健康は家族にとっても、社会全体にとってもすごく大事なことで、私としてはそうしたことを改めて考える機会にもなりました。
はたらく細胞の映画は興行収入63億円を突破し、大ヒットとなったそうです。これを観たたくさんの人がサイエンスに興味を持ち、健康の大切さを再認識し、サイエンスや健康に関するリテラシーが少しでも高まったとすれば、すごいことだなと思います。
同時に、サイエンスの世界に身を置いていた者として、製薬企業で働く者として、さらに言うと親として、サイエンスに興味を持ち、リテラシーを高めてもらうためにできることは何だろうかとも考えました。情報の背景に思いを巡らせ、自分の頭で考え、自分で調べ、適切な評価や行動につなげていく姿勢や態度は、これからの社会でもっと大事になってくると思っています。
これからを生きる子どもたちのために、できることを大人がきちんと考えないといけないですね。
※コラムの内容は個人の見解であり、所属企業を代表するものではありません。
| 黒坂宗久(くろさか・むねひさ)Ph.D.。アステラス製薬アドボカシー部所属。免疫学の分野で博士号を取得後、約10年間研究に従事(米国立がん研究所、産業技術総合研究所、国内製薬企業)した後、 Clarivate AnalyticsとEvaluateで約10年間、主に製薬企業に対して戦略策定や事業性評価に必要なビジネス分析(マーケット情報、売上予測、NPV、成功確率、開発コストなど)を提供。2023年6月から現職でアドボカシー活動に携わる。SNSなどでも積極的に発信を行っている。 X:@munehisa_k note:https://note.com/kurosakalibrary |
あわせて読みたい
オススメの記事
-

ウルトラジェニクス、LC-FAOD治療薬トリヘプタノインを申請/MSD、21価肺炎球菌ワクチン「キャップバックス」承認 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年8月8日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り