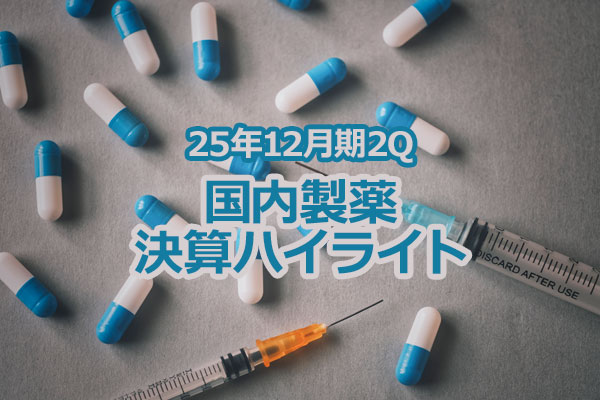早いもので今年ももう12月。1年が過ぎる早さを実感しています。今年も国内外でさまざまな新薬が登場し、話題となりました。ケミストである私の専門分野、低分子化合物に焦点を当てて、今年承認された新薬を振り返ります。
どちらも筋肉の疾患に使われる薬なのに
まず紹介したいのは、ランバート・イートン筋無力症候群治療薬アミファンブリジンリン酸塩(製品名・ファダプス)と、筋萎縮性側索硬化症治療薬メコバラミン(ロゼバラミン)です。いずれも今年日本で承認され、筋肉に関連する疾患に使われるという共通点があります。となると、化学構造も似ているのではないかと思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。

アミファンブリジンの単純な構造と比べると、メコバラミンの複雑さが際立ちます。ケミストからすると、アミファンブリジンは合成原料として使う単純な試薬のような構造ですが、メコバラミンは非常に複雑な構造を持っています。メコバラミンの人工的な合成には非常に深い歴史があるんですが、ここでは書ききれないので、興味のある人はWikipediaの記事を読んでみてください。
このように、どちらも筋肉に関係する疾患に使われる薬でありながら、その構造が大きく異なるのは、作用の対象やメカニズムが違うからです。ここまで大きな違いが現れることに、人体の複雑さが感じられるのではないでしょうか。
レアな水素が大量についた化合物
次に紹介するのは、今年米国で承認されたdeuruxolitinib(製品名・Leqselvi)という円形脱毛症の治療薬です。
構造式を見てみると、普通の薬にはめったに見られない「D」が大量に導入されています。このDの正体は「重水素」です。重水素は水素の同位体(原子番号が同じで中性子の数が異なる原子)で、天然の水素原子の中には0.015%程度しか存在しません。そうした、ある意味レアな水素が8個も含まれているのには、もちろん大事な理由があります。

重水素原子の大きな特徴として、水素原子の2倍の質量を持つことが挙げられます。質量の違いは生体内での化合物の反応性に影響を与えることがあり、代謝や分解の速度が変化したり、吸収される量が変わったりすることがあります。
実は、deuruxolitinibのもととなった、重水素を持たない化合物(ruxolitinib、製品名・ジャカビ)も骨髄線維症や真性多血症などの治療薬として承認されています。構造式を並べてみると、違いは重水素の有無だけです(deuruxolitinibの「deu」は英語で重水素を意味する「deuterium」に由来します)。
ruxolitinibのシクロペンタン(最下部左側の五角形の部分)は、体内で代謝され、薬理活性物質が体外に排出されやすくなることがわかっています。臨床試験では、投与から24時間以内に薬物由来成分の70%が排出されるとの結果が示されており、臨床で効果的な治療を行うにはもう少し体内に存在する時間を長くしたいというニーズがありました。
一方、シクロペンタン部位を8つの重水素で置換したdeuruxolitinibは、体内での代謝速度が非常に遅くなり、薬理効果の時間が延長されることがわかりました。この性質を利用し、より薬効の持続時間が長い薬剤として新たに米国で承認を得ることに成功したのです。
ちなみに、deuruxolitinibの発明者たちは、重水素による効果を確認するため、シクロペンタンのどの部分に導入するかも含めて、4個、5個、8個、9個と重水素の数が違う検体を合成し、代謝速度や半減期に与える影響を調べています。その結果、8個の重水素を導入した場合に最も代謝速度が遅くなることがわかり、開発に至りました(検討の過程が記されたdeuruxolitinibの特許はこちらで見ることができます)。重水素という自然界にはほとんど存在しないレアな水素をうまく活用した例と言えるでしょう。
ケミストがヒヤッとする構造を持つ薬
水いぼ治療薬として米国で承認されたberdazimer sodium(製品名・zelsuvmi)は、ケミスト的にはあまり扱いたくない化合物です。
主成分として含まれているのは、以下の図の1で示すberdazimerというポリマー製剤です。「ポリマーは低分子ではないのでは?」という声が聞こえてきそうですが、それはさておき、私が気になったのは一番左の分子構造。N-N-Nと3つ連続した窒素の真ん中はマイナス荷電のある酸素原子(O-)と結合しており、一番下の窒素には二重結合で接続された酸素原子があります。

ケミストなら違和感を持つ構造だと思います。この単位構造からは、段階的に2分子の一酸化窒素ガスが放出されます。つまり、気体が放出される化合物だということです(上の図の2は簡略化した式です)。
私の印象ですが、創薬研究に携わる化学者は、気体が放出される化合物に嫌悪感や恐怖感を覚える人が多いのではないでしょうか。一酸化窒素は体内でも生成され、工業的にも利用されている気体ではありますが、実験中に何らかの原因で急激に放出されると、反応容器が爆発する事故を起こしたり、窒息や毒性など実験者の健康に悪影響を与えたりといった懸念があります。正直に言うと、私は扱いたくありません。
ポリマー状にして基材と混合したゲル剤として調製されている薬剤、ということで安定性を調節しているのだと推察しますが、その検討には少なからず危険が伴ったのでは…と想像すると恐ろしくなります。気体が発生するような化学構造に恐怖心を抱くのはケミストの職業病と言えるかもしれません。
近ごろの低分子創薬について思うこと
以上、今年承認された低分子医薬品から、構造式を見て「これは!」を感じたものを紹介しました。あらためて振り返ってみると、今回紹介できなかったものも含め、普段あまり触れることのない構造を発見することができ、非常に良い勉強になりました。
さて、話は少しそれますが、低分子医薬品を見続けている人間として最近、感じていることがあります。それは「低分子」という言葉の定義が以前とはすっかり変わってしまったということです。
「低分子医薬品に適した化合物は分子量500以下」という経験則を示したリピンスキーの「Rule of five」は、かつてメディシナルケミストにとって基本中の基本で、一部の天然由来化合物や重原子を含む造影剤・放射性医薬品など特殊なものを除けば、化合物をデザインするときにまず念頭に置いておくべきルールでした。
しかし、今では状況が大きく変わっています。PROTACのような二機能分子や大環状化合物(マクロサイクル)といった比較的大きな分子量の化合物に非常にユニークな性質が見出され、臨床現場での活躍を期待して開発が進められています。
また、ADC(抗体薬物複合体)のように、低分子と別のモダリティを組み合わせる研究開発も盛んとなっており、バイオロジストが行う抗体創薬との融合も発生しています。さらには、さまざまな装置を使った実験の自動化や、そこから得られるデータの大規模活用により、いわゆる「AI創薬」を志向する活動が、実際の創薬研究の現場にも導入され始めています。
低分子化合物の概念の変化、扱うモダリティの広がり、ロボット工学やデータサイエンスとの融合など、メディシナルケミストの仕事には大きな変化が連続しています。もちろん、それぞれの製薬企業の方針や事情によってケミストの存在価値に違いはあるかもしれませんが、変化の中にあってもケミストのしごとはどこかに残り続けると確信しています。激動の時代を生きる者として、これからケミストの仕事がどうなっていくのか、興味が尽きることはありません。
| ノブ。国内某製薬企業の化学者。日々、創薬研究に取り組む傍らで、研究を効率化するための仕組みづくりにも奔走。Xやブログで研究者の生き方について考える活動を展開。 X:@chemordie ブログ:http://chemdie.net/ |