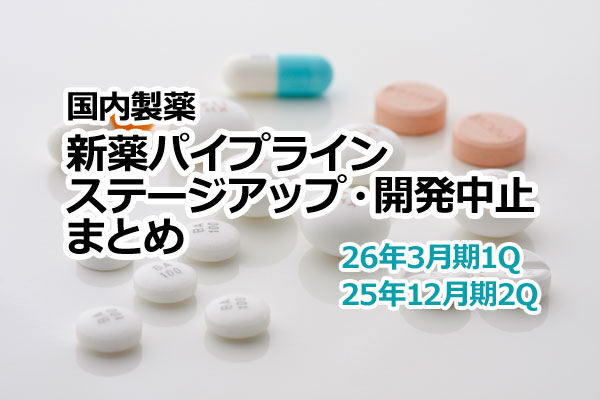今年1月に稼働した浮間工場のバイオ原薬製造棟「UK4」(同社提供)
中外製薬が、生産・製薬技術の強化に向けた設備投資を加速しています。得意とする抗体医薬や技術開発を進める中分子医薬で、2019年以降、総額1600億円超の投資に着手。臨床開発から初期商用まで内製できる体制を整え、2030年までの成長戦略で目標とする「R&Dアウトプット倍増」「グローバル品の毎年上市」を支える基盤を強化します。
バイオ原薬、内製を強化
中外の製造分野の2大戦略は、▽臨床開発から上市後初期まで内製可能な体制構築▽CDMOなども活用したデュアルサイト戦略による商用生産での安定供給の実現――。豊富な開発パイプラインとその順調な進捗を踏まえ、設備投資を通じた内製キャパシティの底上げを図っており、30年までの成長戦略をスタートさせた21年以降に限っても1000億円以上の投資を決定しています。

今年1月には、総額121億円を投じて浮間工場(東京都北区)に建設した「初期開発用治験薬・バイオ原薬製造棟《UK4》」が稼働を開始。臨床第1相(P1)試験に特化した製造棟で、ファースト・イン・ヒューマン(FIH)試験に使用する治験薬の製造を担います。従来、FIH試験向けの製造は同工場の別の製造棟「UK1」「UK2」で行ってきましたが、商用生産にも対応可能なこれら2棟にUK4を加えることで「内製戦略を確実にワークさせる」(田熊晋也・生産技術本部長)狙い。PoC取得までの期間を短縮し、開発全体のスピードアップを目指しています。

UK4には、2000リットル(L)のシングルユース(SU)培養槽2基を配置。SUを採用することで、スピードと柔軟性を確保しています。浮間事業所には製法などを研究する機能もあり、パイロットスケールの段階で研究から製造への技術移転を現場で開始できることも外製と比較した際のメリット。内製戦略には、自社に生産技術を蓄積する意図もあります。

中外は今年5月、稼働後のUK4を報道陣に初めて公開した。建築面積1220㎡、延床面積3705㎡。SUの2000L培養槽2基と精製1ラインを備える。写真はSUによる培養設備。
また、浮間工場では昨年末、P3試験から初期商用に対応したUK3の設備を増強することも発表。生産能力を3倍に拡充するとともに環境対策を講じます。同社では承認取得から5年間の商用生産に耐えうるキャパシティを確保するようにしているといい、UK3の増強によって充実するパイプラインの初期商用にも備えます。

UK3。372億円を投じて2019年に稼働した。建築面積4066㎡、延床面積26543㎡。写真は精製設備。UK3は6000Lのステンレス培養槽6基を備えており、2系列の精製ラインと自由に組み合わせることで少量多品種の生産を可能にしている。
バイオ連続生産やDXでも取り組み
バイオ原薬の製造では、宇都宮工場(栃木県宇都宮市)でも総額564億円の設備投資が進行中。中期段階以降の治験薬製造と初期商用のバイオ原薬製造を担う「バイオ原薬製造棟《UT3》」と、初期商用の無菌注射剤製造を行う「注射剤棟《UTA》」の建設を進めています。
UT3は古典的な連続培養法である「灌流培養(※)」を導入し、連続生産機能の実装を目指しています。同社独自のエンジニアリング抗体にはいわゆる「Y字型」から外れた抗体もあり、中には培養液中で分解されやすい不安定なものも存在します。田熊氏によると「連続培養なら不安定な抗体分子を高品質に生産できる可能性がある」といい、抗体の大量生産プロセスの確立に生かす考えです。
※抗体産生細胞を高密度で生育させた培養槽に、栄養分を連続で供給しながら抗体を回収する培養法。従来の培養法より生産効率の向上が見込まれる。
ただ、バイオ医薬品の連続生産は薬事規制上、不透明な部分も多く、どの程度実際の商用生産に生きてくるかは現時点では不明です。中外は「設備の小型化による低コスト化や、ロボティクス技術との相性の良さなどを評価している」とし、総合的に評価しながら検討を続けていきたいとしています。
DXによる効率化も目指す
こうしたキャパシティの増強の一方で、「スマートファクトリー」の確立を目指したDXも進みます。
中外が取り組むのは「人」に着目したデジタル化です。教育訓練の実施・管理をシステム化するとともに、生産計画に応じた要員の自動配置システムを構築し、資格情報などを双方で連携することによって育成にかかる期間やコストを大幅に削減。製造の実行時には、スマートフォンを使った作業者の遠隔支援、改ざんできない画像記録ツールも活用しています。
一連のシステムは浮間工場から導入を開始し、昨年1年かけてオペレーションの構築を進めてきたといいます。宇都宮工場にも展開済みで、今年中に藤枝工場(静岡県藤枝市)への導入が完了する見通し。DXで蓄積するデータの活用はまだ途上としていますが、将来的にはAIも活用してさらなる高度化を目指します。
中分子原薬に大胆な先行投資
抗体医薬と低分子に続く第3の柱と位置付ける中分子医薬についても、これまでに約900億円を投じて生産設備を整えてきました。中分子は、低分子や抗体ではアクセスしにくい細胞内のタフターゲットを標的にできる可能性があり、同社は未開拓の標的に対する創薬モダリティとして期待しています。
中分子医薬は、高い生理活性が求められることから対応できるCMOがほとんどないのが現状。中外は自前で技術の蓄積を進めており、25年までに製法開発から初期商用生産までを一貫して行える体制の構築を目指しています。

22年に藤枝工場で稼働した新棟「FJ2」は、高薬理活性・難物性の低・中分子化合物を安全に取り扱うことができるアイソレータ―を導入し、高度な封じ込め(化合物が外部に対して汚染されないこと)レベルを達成。555億円を投じて建設中の「FJ3」は、P3から初期商用に対応する合成原薬製造棟で、25年の稼働を目指しています。
FJ3への投資を決めた21年には、同社の中分子医薬第1号となる「LUNA18」のP1試験開始を発表。現在は同薬のほかに前臨床開発段階のプロジェクトが1つ、開発候補品選抜段階のプロジェクトが11あります。中外は、毎年1つ以上のプロジェクトを前臨床段階に進める方針で、開発のスピードアップを生産からも後押しする構え。同社にとっても、中分子医薬品への投資は「かなりの先行投資」(田熊氏)といいますが、研究との両輪でリードを確保する考えです。
AnswersNews編集部が製薬企業をレポート
あわせて読みたい
オススメの記事
-

ウルトラジェニクス、LC-FAOD治療薬トリヘプタノインを申請/MSD、21価肺炎球菌ワクチン「キャップバックス」承認 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年8月8日)
-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発
-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地
-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収
-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り