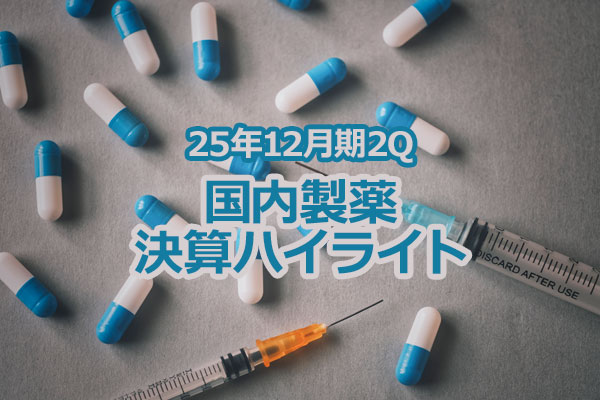新型コロナウイルスの拡大で一気に加速すると言われているデジタルトランスフォーメーション(DX)。テレワークが進み、デジタルチャネルを通じた営業活動が広がるなど、デジタル化が遅れていると言われる製薬業界にも変化が見え始めました。製薬業界では今、DXに対してどのような動きがあり、その先にはどんな世界が待っているのか。デロイト トーマツ コンサルティングのコンサルタントと議論します。(連載の全記事はこちら)
CureAppの保険適用、どう見る?
前田雄樹(AnswersNews編集長):デジタルセラピューティクス(DTx)への注目が高まる中、11月11日の中央社会保険医療協議会(中医協)で、国内初となる治療用アプリ「CureApp SC」(CureApp)の保険適用が了承されました。特定保険医療材料としてではなく、新技術料として既存の技術料を準用する形で2450点(2万4500円)という保険点数がつきましたが、これをどう見ていますか。
増井慶太(デロイト トーマツ コンサルティング・執行役員):薬価ではありませんが、保険適用の対象となったということで、1つのDTxのマイルストーンになった事案だと考えています。
大津遥奈(デロイト トーマツ コンサルティング・マネジャー):数百円、数千円ではなく、万円単位の点数がついたことは大きいのではないでしょうか。ただ、消耗品のCOチェッカーの材料価格もあわせて評価されたとのことなので、今後登場する製品は数百円という評価となる可能性は依然としてあります。
今回は治療用アプリに対する評価に対する考え方が整理されていない中での保険償還でしたが、将来的にはDTxの特性を踏まえた評価制度を整理・構築していく必要があると考えます。現状では、患者にとっての有効性・安全性を大きな判断基準として、出来高で評価していますが、DTxがもたらす「医療従事者の負担軽減」「医療従事者間の技術の平準化」などは、現行の枠組みでは積極的に評価されません。中長期的にDTxが普及していくためには、経済的な側面も含めたアウトカムベースでの評価体系の導入が必要と考えます。
前田:中医協の議論では、「無料の健康管理アプリが山ほどある中、今後も、健康管理なのか治療なのか境目のつかないようなものがどんどん出てくるだろう」との指摘もありました。
大津:DTxは診断や治療を目的とするソフトウェアで、規制当局による承認が必要なものを指します。そのため、明確な臨床アウトカムを示すことが求められ、医療従事者によって薬事承認の範囲内で使われるのが一般的なアプリやデバイスと異なる部分です。
具体的にどのようなものがあるかと言うと、▽慢性疾患における疾患管理・療養指導を医師の代わりに提供するもの▽精神疾患に対する認知行動療法を補完するようなもの▽デジタルバイオマーカーを用いた診断ソフト――などが挙げられます。
機能としては、マーカーとなる何らかの指標をデータとしてトラッキングできることが非常に重要。アウトカムをトラッキングし、それを見ながら介入を変えていくことが重要なので、データをトラッキングするデバイスと連携させることが大きなポイントになるケースが多いと思います。
前田:日本でも近年、製薬企業も参入してDTxを開発する動きが活発化していますが、市場の規模や形成具合はどうなっているのでしょうか。
大津:グローバルの市場規模は2020年の21億ドルから2025年には69億ドルと大きな成長が見込まれていますが、その7~8割は米国です。日本の市場は相対的にかなり小さく、環境的な要因もあって難しい市場だと思います。そのかわり、まだ発展途上なので、ビジネスを展開する上では新規参入の余地が大きいとも言えます。
下の表は米国のデロイトが調査したもので、横軸に疾患領域、縦軸に技術の要素をとり、市場の成熟度合いをプロットしたものです。色が濃くなるほど参入しているプレイヤーが多く、市場形成が進んでいることを表しています。

疾患領域としてプレイヤーが多くなっているのは、内分泌、CNS、循環器といったところ。内分泌はほとんど糖尿病ですが、こうした領域はリモートでのモニタリングと親和性が高い。特に米国の場合、医療費抑制の観点からもデータやデジタルの活用に対する保険者の期待は高いので、重症化予防という面で活用が進んでいます。
技術的な要素としては、まだAIを使って完全自動化というところまではいっていません。アルゴリズムベースでしっかりプログラムを組んで、そこにデータを当て込んで、アウトプットしていくという形式のものが多くなっています。データトラッキングはかなり技術としても確立されてきていますし、コミュニケーション&ソーシャルメディアといったところもある程度進んでいます。
患者支援との境目
増井:活用されるデータもさまざまです。従来から目配せされてきたのはカルテやレセプトのような医療データですが、最近ではウェアラブル端末の進歩などともあいまって健康ヘルスデータが重視されるようになってきました。さらに直近で注目を集めているのが、必ずしも疾病の管理が企図されているわけではないコンシューマーデータ。例えば、CNS領域の患者では、疾患の状態によってクレジットカードの購買履歴が変わることがあります。こういったものを医療上のインサイトに使えないかということで、DTxに引き込んでいくような世界も出てくるのではないかと思っています。

話は変わりますが、ADHD向けの治療用ゲームアプリを開発した米アキリのエディー・マルトゥッチCEOが先日、日経メディカルのインタビューで「デジタル治療は薬物療法と認知行動療法に代わるものではない」と語っていました。併用によって補完的に作用するんだと。そうしたことを考えると、今後、治療のレジメンにDTxが何らかの形で絡んでくるのは避けられないのではないかと思います。
大津:今のところは大きなポイントです。慢性疾患のDTxでは、医療従事者が適切に関与することが重要な要素だということがわかっていますので、既存治療との併用を前提とした設計になると思います。
開発においても、コントロール群に何を置くかは、治療上での位置付けコンセプトの観点で非常に重要。標準治療を対照群に置き、併用(Add-on)でのアウトカムを検証するようなデザインが多くなっていると思います。
増井:そうして考えてみると、DTxと患者支援プログラムとの境目が難しい。オンライン診療をテーマに議論した回でも話題になりました、結局のところ全部同じなのではないかと。患者さんのリアルなデータをベースに、さまざまなソリューションがさまざまな形で出てくる。その1つとしてDTxを捉えるべきなのではないかと考えています。
前田:そうなると、臨床開発のコストをかけてあえて薬事承認を目指す理由は何なんでしょうか。
増井:そこはメーカーも当局も頭を悩ませているところなのではないでしょうか。律儀に開発しようとすると時間もかかるし、数億円単位で開発コストもかかります。解はありませんが、どちらに行くのか戦略をきちんと考えないといけないのは確かです。
大津:医療機器への該当性についてはグレーゾーンもまだ多く、開発者側が目的として何を標榜するかによるところも大きいので、企業の戦略的な意図は重要です。
ただ、非医療の患者サポートプログラムに置いておくと、患者に届きづらくなってしまう可能性は考慮する必要があります。健康意識が高くて自己管理ができる人は使うけど、そうでない本来使って欲しい人はなかなか使ってくれません。そういう意味では、DTxとして医師を介した方が届けやすいし、保険適用されたほうが患者負担も抑えられ、マネタイズもしやすい。製薬企業や医療機器メーカーなど、患者アウトカムの向上をミッションとする企業がそうした道を選ぶのは、合理的な選択と言えるのではないでしょうか。
増井:自費診療のウェイトが大きく、医療格差の大きい米国であれば、その非対称性を突いてDTxを普及させていくことが可能です。しかし、日本の場合、国民皆保険がある種のバリアになっていて、一定の誘導がなければ、患者さんが自ら選択して使うという状況にはなりにくいのではないかと思います。
そうなると、臨床サイドからマーケットを構築していくことになりますが、今度は医療機関側のデジタル化が必要になる。DTxと医療のデジタル化は密接に紐付いていて、臨床サイドから普及させようとすると、そうした環境整備が課題になってきます。
モデルを作る
大津:健康保険組合や民間保険会社を通じて普及させていく道も考えらますが、日本ではまだ難しいのかもしれません。米国ではペイヤーの力が強いので、例えばリボンゴのように、ペイヤーを介してサービスを提供し、医療費削減効果の一部をマネタイズしてもらうというビジネスモデルで成功例が出てきています。一方、日本は出来高払いのシステムなので、こうしたビジネスモデルはまだ確立されていません。
ただ、最近では、健保組合なども重症化予防に取り組むようになってきているので、そこにサービスを提供して健保組合からお金をもらうというビジネスモデルも出つつあります。
増井:リボンゴのように、患者さんのジャーニーを包括的にカバーするサービスが日本で普及することを期待しているんですが、現状ではなかなか難しい。国民皆保険制度の問題もあるし、保険者の力も強いとは言えません。
前田:いろいろと議論してきましたが、結局、日本でDTxを成功させるためには何がカギになりますか?
大津:繰り返しになりますが、マクロな視点では、経済性を含むアウトカムを積極的に評価する仕組み(Value Based Payment)への転換や、医療現場のデジタル化といった環境整備が必要だと思っています。
個別の製品で言うと、マーケット自体がまだ未成熟なので、しっかりとマネタイズやビジネスのモデルを作っていくことですね。あとは、ファーストユーザーを確保することも重要です。ソリューションのタイプによって正解は変わってくると思いますが、こうした論点について、きちんと仮説を立てて進んでいくことが大事なのではないかと思います。
今の製薬企業の取り組みを見ていると、小さいプロダクトでも収益を多様化するという観点でやっているところも多いと思います。また、データの活用は医薬品事業本体にも効いてきますので、DTxそのものの収益にとらわれることなく、試行錯誤しながらやっていく価値はあるのではないかと思っています。
増井:結局は薬に返ってきますからね。語弊を招くような言い方かもしれませんが、「餅は餅屋」、製薬企業の仕事は創薬にあると思っています。DTxは、新しいモデリティとしての役割にとどまらず、製薬のバリューチェーンに貢献する1つの手段です。DTxへの取り組みが、最終的にはイノベーションに戻ってくるという構造ができるといいのではないかと思います。

増井 慶太(ますい・けいた)=写真左。デロイト トーマツ コンサルティング合同会社執行役員/パートナー。米系戦略コンサルティングファーム、独系製薬企業(経営企画)を経て現職。「イノベーション」をキーワードに、事業ポートフォリオ/新規事業開発/研究開発/製造/M&A/営業/マーケティングなど、バリューチェーンを通貫して戦略立案から実行まで支援。東京大教養学部基礎科学科卒業。 大津 遥奈(おおつ・はるな)=写真右。デロイト トーマツ コンサルティング合同会社マネジャー。海外大学院を卒業後、同社に入社し、ライフサイエンス・ヘルスケア領域で事業戦略の策定や製品戦略の策定、組織・オペレーション変革の実行支援など、幅広いテーマに従事。近年では、デジタルヘルス領域の市場調査や戦略策定支援を複数手掛けている。 |